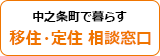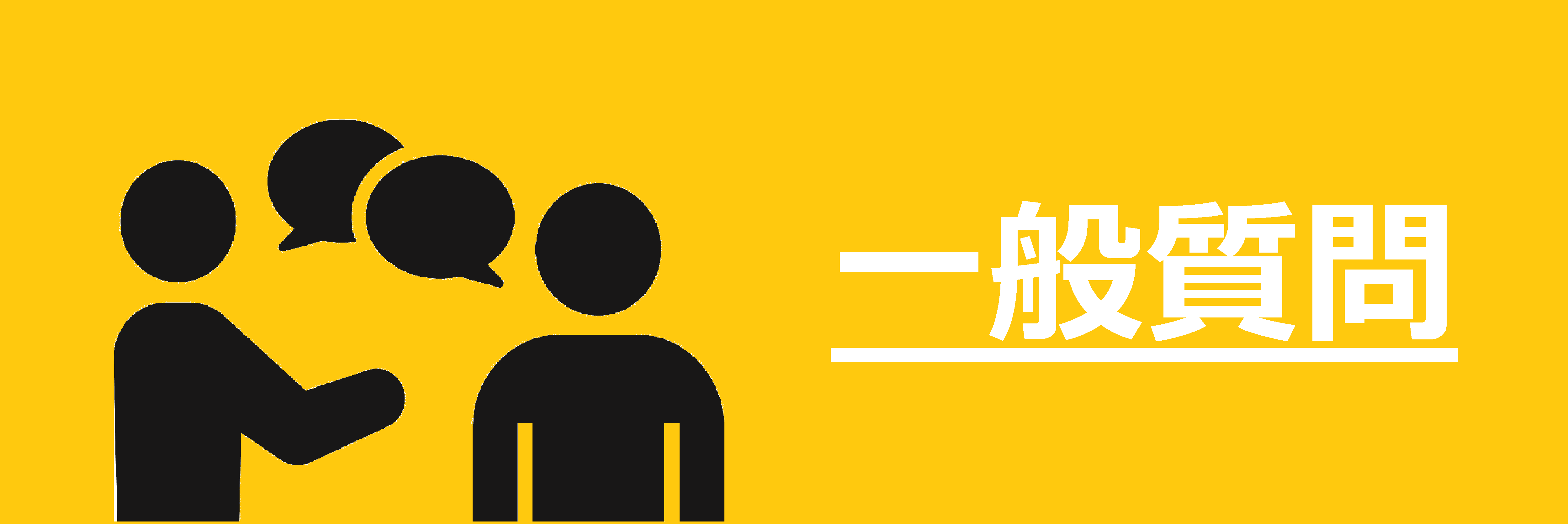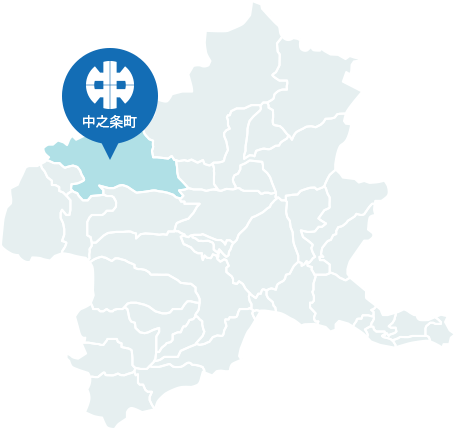本文
令和6年9月定例会議 一般質問(関常明議員)
06 10番 関常明議員 令和6年9月定例会議一般質問
〇10番(関 常明)議長の許可をいただきましたので、今回4点について質問をさせていただきたいというふうに思います。
〇随意契約について
まず、随意契約のことでございますが、中身は非常に厳しく制限されている金額も含めて、決まりがあるということは理解をしております。
しかし、町長の裁量で相当いろんなことができるのではないかというような話をされる方もいらっしゃいます。そういうこともございますので、この際中身のことについてご説明を願えたらというふうに思います。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)それでは、関常明議員のご質問にお答えをさせていただきます。
地方公共団体としての契約は、事務事業の目的達成の手段として締結されているものであり、またこれらの契約の多くは公金の支出を伴うことから、その締結の契約に関しましては不特定多数の参加者を募る調達方法である一般競争入札が原則であります。
一方この原則を貫くと、調達の準備に多くの作業や時間が必要となり、結果として当初の目的が達成できなくなるなどの弊害が生じることもあり得ます。このため、指名競争入札や随意契約による調達が例外的な取扱いとして認められております。
随意契約につきましては、競争の方法によらないで、普通地方公共団体が任意に特定の相手方を選択して締結する契約方法であり、一般競争入札や指名競争入札に比べ、手続が簡略であり、かつ経費面でも一段と負担が少なくて済み、しかも相手方が特定したものであるため、競争入札によってはその全てを満たすことができないような資力、信用、技術、経験等相手方の能力等を熟知の上、選定することができることから、その運用が適切なものであれば、その長所を発揮し、所期の目的を達成することができるものであります。中之条町におきましては、地方自治法施行令第167条の2の規定に基づきまして実施をしております。
〇議長(安原賢一)10番、関さん
〇10番(関 常明)次の質問なのですが、大体お答えをしていただいていますので、重複するのかなという感じもするのですが、当然随意契約を行うということに関して幅広く行えるということもありますので、当然配慮すべき事象があるのかなという感じもしますので、そのへんのお話を伺えたらというふうに思います。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)随意契約において配慮すべき点ということでありますけれども、地方自治法施行令第167条の2におきまして、随意契約によることができる場合が規定されておりますので、この規定に従い随意契約として適しているか、中之条町入札審査会において審査し実施しているところでございます。
〇議長(安原賢一)10番、関さん
〇10番(関 常明)建設関係百二、三十万だったでしょうか。それから、バイテックのほうで緞帳の修理ですか、それ何かも随意契約だったのかなと。違ったらごめんなさい。そういうこともありますので、中身についてはいろいろ前広に説明をしていく必要があるのかなというふうに思います。
それで、随意契約で行っていることについては、議長のほうにも報告が来ています。そのことは、承知をしていますが、件数についてお答えをいただければというふうに思います。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)随意契約の件数についてのお尋ねでありますけれども、令和4年度が約38%の44件、令和5年度は46%で43件、令和6年度は9月1日現在で約39%の29件となってございます。
〇議長(安原賢一)10番、関さん
〇10番(関 常明)ありがとうございます。重複をしますが、町長の裁量でいろいろできるのではないかというようなお話もちょっと聞いておりますが、非常に厳しい制限があると、当然のことでございますが、そういうお答えがあったというふうに理解をしております。そういうことで、随意契約については理解をいたしました。
〇空き家対策について
続いて、空き家対策について質問をさせていただきたいというふうに思っています。これは、折に触れて同僚議員が空き家対策についての質問というのはやられています。初めてのことではありません。かつ、非常に難しい課題であるというふうに理解をしております。確実的な方法がないし、地方、中央も含めてですが、なかなかいい方法がないというのは周知のとおりでございます。ただ、何とかしようという頭に立つとすれば、やっぱり中之条町、地方独自の考え方というのが全面に出て行かないと大変なのかなという感じもしております。
そういうことで、空き家対策の事業について、今までの経緯も含めてお話ししていただけたらというふうに思います。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)空き家対策事業についてのお尋ねであります。空き家対策の事業につきましては、空き家が個人の財産であるため、非常に難しいところではございますが、空き家の利活用や空き家の解体等において支援を行っているところでございます。
空き家の利活用につきましては、令和2年度より空き家バンク制度を導入し、令和5年度末現在10件の登録で8件が売約済みとなっております。空き家の改修補助金につきましても、令和5年度末現在で36件あり、移住定住におきましても成果が出ているところでございます。
また、空き家の解体補助金につきましては、令和5年度末時点で88件の実績となっております。町の防災、防犯の観点から支援により成果を上げているものと認識をいたしております。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)10番、関さん
〇10番(関 常明)この問題については、お話があったように空き家になったからそれを整備をして誰かに活用していただくというようなことももちろん大切だというふうに思うのですが、先ほどから申し上げているようにやっぱり町として何とか中身は要するに経済効果が必ずしも伴わなくてもそれらに向けて何とかユニークな方法があればというふうに思うのです。将来に向けて具体的なことがあればいいのですが、そのへんはまた非常に難しいと思うのですが、それはそれでちょっと区切りにします。
順番がちょっと違いまして申し訳ございません。担当課の話をちょっと通告をしてあります。それでいきます。担当課の変更というのは、これたしか空き家の問題は一番最初は企画だったのですか。ちょっと記憶が間違っていたらごめんなさい。移って、今度はまた課が変わったのですが、そのへんについて、そのへんも踏まえて担当課の意味というか、そこで活動をする意味というのをちょっとお話をしていただければというふうに思うのですが。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)担当課が変更になったというお尋ねでありますけれども、3月定例会議におきまして課の設置条例の一部改正において説明をさせていただきましたが、これからますます増え続けることが想定される空き家に対しまして、課題となる防犯、防災の観点から防災安全課の業務としたところでございます。効果的だったと認識をいたしております。
なお、空き家の利活用等につきましても、ほかの課と情報の共有を図り、連携を取りながら事務を進めていくよう指示しているところでございます。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)10番、関さん
〇10番(関 常明)今までみなさんも含めて議論した中身と一緒で、なかなか先に進むのは難しいかなという感じもします。個人の財産だよというお話もございましたが、将来に向けて現時点で具体的に取組をどうするのか、どう考えているのかという話をちょっとしていただければというふうに思うのですが。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)先ほども申し上げましたけれども、本当にこれから増え続けることが想定をされる空き家に対しましては、個人や法人の財産であることから、所有者の意向もあり、その対応につきましては非常に難しいところでありますけれども、解体等も含めて補助金を有効に活用していただきながら空き家の利活用の推進を図ってまいりたいと考えております。
〇議長(安原賢一)10番、関さん
〇10番(関 常明)これから長い間の取組、中之条だけではなく、地方の課題でもあるし、中央の課題でもあるというふうに思うのですが、いずれにしてもこれ大きな課題の一つだというふうに思いますので、町を挙げてよろしくお願いをしたいというふうに思います。
〇木材活用センター
それでは、ちょっと次に進みます。通告をしてありますように、木材活用センターのことについて、ちょっとお話をさせていただきたいというふうに思うのですが、木材活用センターについては一定の区切りになったと、建物が完成して事業も区切りの状態かなというふうに思うのですが、これからの事業だなというふうに思っています。
私も当時最初のときの委員会に属していまして、非常に中身としてなかなか国の施策も含めて官が民に踏み込む事業かなというふうに、たぶんそれで課長さんぐらいの年の人たち、もう少し下か、係長さんぐらいの年の人たちはたぶんそういう認識ではなくて、これは民間でやることだから私たちはというような感覚でいたのかなという感じもしますが、いずれにしてもさっきも言ったように官が民の問題について手を入れてくると。これから先も例えば農地の問題、耕作放棄地の問題なんかも同じパターンで進むこともあるかもしれません。可能性も高いというふうに思っています。そういうこともありますので、現時点の将来に対する具体的な施策をお考えがあれば、全体的なことでお考えがあればちょっとお聞かせを願いたいというふうに思います。
それから、森林環境税の問題が出ております。その問題も併せて現状をお話をしていただければというふうに思うのですが。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)木材活用センターへのお尋ねをいただきました。木材活用センターの建設につきましては、皆様のご協力いただきまして、令和5年9月30日に開所いたしました。議員お尋ねの具体的な施策についてでございますが、施設部門であるハード事業は完了いたしました。そのため、今後は木材活用センターを利用した森林教育等のソフト事業が主な施策となってまいります。以前の答弁でも申し上げましたように、木材を加工して製品を作り、新たな経済活動を生み出す「Nプロダクト」や森林の持つ機能や魅力を伝える「森の学校」、林業を継続的に行うための担い手の育成のための「林業実践学校」を実施をいたします。
森林環境譲与税につきましては、森林整備等の費用に充てるため、国から市町村に譲与されている国税でございます。中之条町におきましては、令和元年度から令和5年度までの5年間で約1億2,500万円譲与されております。本年度の令和6年度につきましては、昨年末の閣議決定により人工林面積割での交付率が見直され、約4,500万円が譲与される予定となっております。
以上です。
〇議長(安原賢一)10番、関さん
〇10番(関 常明)それで、北区の森の事業ということを聞きました。そういうお話があるということで、これは友好区の話なので、北区のみなさんに協力をいただいたという話になろうかというふうに思うのですが、初めてのケースかなというふうに思います。
交流だとか北区のお子さんだとかということも含めて現在、将来について全体的な説明解説をしていただければというふうに思うのですが。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)きたくの森事業についてのお尋ねでありますけれども、きたくの森事業につきましては、森林環境に対して意識の高い都市部自治体に町有林を活用していただくことで都市部自治体の森林環境譲与税も活用しながら一緒に事業ができないか模索しておりました。
令和6年3月に友好都市交流協定を結ぶ東京都北区と森林整備を協同で実施する新たな協定を結び、令和6年度から芸術の森近くのおよそ3.7ヘクタールの町有林を北区も出資の上、整備する事業を進めております。整備した町有林は、きたくの森として北区区民の環境教育に利用されるほか、中之条町民と一緒に植林を行う等、お互いが交流できるソフト事業を企画できればと考えております。
なお、きたくの森整備につきましては、吾妻森林組合に施業をお願いしております。林業を効率化する仕組みであるタワーヤーダを使った施業について、県内各所から視察者が訪れ、林業関係者も勉強させていただきました。
以上でございます。
〇議長(安原賢一)10番、関さん
〇10番(関 常明)既に視察の方が見えているということでございますが、タワーヤーダとかいう文言があったのですが、これの説明をちょっといただければというふうに思うのですが。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)詳しくは、もし違っていたら農林課長からちょっとしてもらいますけれども、集めてきて、要するに集積です。それをしたやつをためていく、その集積する機械というふうにざっくり聞いておるのですけれども……そのとおりだそうです。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)10番、関さん
〇10番(関 常明)さっきも言ったようにもう事業として進んでいるということでございます。非常に中身として有意義な話になろうかというふうに思うので、このへんは積極的に進めていただくということかなというふうに思います。できれば答弁にもあったように都市部の林業に、あるいは森林に興味のある自治体にというお話だったので、このへんも併せて進めていただければというふうに思います。
チップの問題についてちょっと触れたいというふうに思います。ご案内のように、チップはこれは委員会にいたので、最初のときの話もちょっと知っているのですが、チップの大きさ、砕いたサイズが合わないとか、乾燥状態が悪いとかいうことで、ちょっとボイラーのほうが稼働できないような時期もちょっとあったのですが、現在は当然順調に生産がされているというふうに理解をしています。これは、たぶん相当の量の能力がチップには、生産という意味であるのだろうというふうに思うのですが、これは将来的に町の設備だとか、あるいはもう少し話を広げれば一般の会社だとかということに活用できるものだというふうにちょっと思っています。
これは、環境問題なんかにも、化石燃料とは違いますので、そういうことに活用していく方向に当然町長も考えているというふうに思っているのですが、チップの活用について、現在の状況、それから将来についてのお考えがあればお聞かせください。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)関議員おっしゃるように、チップも最初の生産のときから比べますと物が非常によくなってきておるということでございますので、今私どものバイオマスボイラーでも順調に使用させていただいておるというところであります。
チップにつきましては、主に木を製材するときに生じた端材を利用してチップ生産を行っております。令和5年度に生産されたチップは318トンで、計画の67%の生産量でございました。計画に満たなかった原因としては、木材活用センターの開所が9月末にずれ込んでしまったことによるものでございます。
今後としては、形状や含水量の改善が図られたチップを製造することでバイオマスボイラー運用が安定し、町施設以外でもチップの利用が増え、木材活用センター事業の効率化や事業拡大が雇用の増加や町内の木材産業全体の生産額増加につながり、さらには周辺地域への経済的波及にも貢献していくことを大いに期待をしておるところでございます。
〇議長(安原賢一)10番、関さん
〇10番(関 常明)事業的には、あまり派手な事業ではないのかもしれませんが、将来非常に有望かつ希望のある事業だというふうに思いますので、積極的にチップの利用については推進をしていただければというふうに思います。
答弁の中にも開業の目的の中に林業の担い手、なかなかこれ大変な事業だというふうに思うのですが、林業の担い手、町長が町の説明をするときに町の森林面積があるという話を結構されるのですが、そういうことで担い手というのは非常に現状厳しいかもしれないのですが、担い手の話もちょっとお聞かせいただければというふうに思うのですが。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)林業の担い手についてのお尋ねでございますけれども、林業の担い手につきましては多くの経験を要するものでありまして、すぐに育成できるものではございません。また、町単独で高度な林業実践教育を行うことは困難と思われます。そのため、もっと身近な林業に目を向けていただきながら地道に担い手を増やすため、林業実践学校の取組を行っておるところでございます。
なお、今年度の林業実践学校につきましては、3回の刈払取扱作業者安全衛生教育の講習会を開催をいたしました。
また、自伐型林業を推進していくために8回のチェーンソー講習を開催し、安全に伐倒できる技術力の向上を図っております。
ほかにも林業を守るために必要となる有害鳥獣対策のためのくくりわな講習会も実施しております。
以上です。
〇議長(安原賢一)10番、関さん
〇10番(関 常明)大変重い任務を背負っているかなというふうに思いますので、担当課のみなさん、積極的に頑張っていただきたいというふうに思います。議会のほうも注目をしていきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いをいたします。
〇自動運転の報道があったが
最後になります。議長の配慮で全協のときは非常にタイトになって大変になるのではないかという話もちょっとしたのですが、大分スムーズに進行しているようなので、最後上毛新聞だったと思うのですが、自動運転の報道がございました。今日ちょっと昼休みにもちょっと話があったのですが、自動運転については割と早く進むかなと。それは、中之条町にイコールになるかというのは全く別の話でして、たぶん今の新しい車になってくると高速道路だと何もしないということはないのですが、自分で運転するし、自分でアクセルは踏まないけれども、前の車の後くっついていったりするというような話も聞いております。課題の町の通学のバスだとか買物のバスだとかというように、折に触れてお話をしているのですが、そういうことも含めて自動運転というのは非常に有望なのかなというふうに思います。それは、さっきも言ったように中之条とは直結をしない、現時点でですね。直結をしないというのは理解はしていますが、非常に注目に値する事象かなというふうに思っています。
元に戻りますが、総務省の事業で四万エリアだという話は聞かせていただいております。なので、町が直接手を出すという話ではないのかなというふうに思っておりますので、機会ですので、みなさんにご披露をしていただいて、奥四万湖を回る話だったというような話も聞いておりますが、ご説明いただければというふうに思います。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)お尋ねの自動運転の関連するご質問でございますけれども、6月の29日の上毛新聞に報道されました自動運転の公道における実証実験につきましては、群馬大学と日本モビリティ株式会社の2者により総務省へ申請し、採択されたものでございます。中之条町としての事業ではございませんので、町から事業にかかる費用は発生をいたしません。町は、四万温泉協会とともに協力団体という関係にあります。概要につきましては、地域共創課長より補足の説明をさせますので、よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)地域共創課長
〇地域共創課長(湯本文雄)地域共創課の湯本です。自動運転の公道における実証実験につきまして、補足の説明をさせていただきます。
資料をお配りさせていただきましたので、ご確認いただきたいと思います。最初に、今までの経過からご説明させていただきます。
現在総務省による自動運転関係の取組におきまして、観光地や中山間地域、特に携帯電話の電波の強度が弱い地域における自動運転の技術検証が求められております。昨年の年末より群馬大学、日本モビリティ株式会社におきまして、四万温泉地内、特に奥四万湖周辺での観光輸送を想定した自動運転の公道実証実験を行いたいとのことで、町企画政策課と四万温泉協会を交えた4者間で打合せを行ってまいりました。今年3月末に群馬大学、日本モビリティ株式会社により総務省へと申請されました。その後、実証実験が採択されましたとの連絡を受けて5月下旬、外丸町長及び篠原副町長へ挨拶と概要説明に来庁されました。6月定例会議の時点では、国道、町道、警察署、森林管理署などへの説明や手続が調整中で具体的なスケジュールも未確定でしたので、総務企画常任委員会のみでの情報提供とさせていただきました。その後、実施スケジュールも明らかになり、様々な手続も調整が済みましたので、日本モビリティ株式会社へ資料の提供を依頼したところ提出されましたので、お配りいたしました。
それでは、この実証実験の概要を説明させていただきます。この実証実験は、自動運転レベル2で走行中はドライバーが乗務し、緊急時等には直ちに手動で必要な操作を行えるようにして実施するというものでございます。実施期間は、単年度の実証実験ということと、積雪時には実施できないことから、12月上旬までの実施となっております。検証走行の後、本番走行には一般の方の乗車を予定しておりますので、議員のみなさんもご試乗いただければと思います。実施場所は、2つのルートとなっております。資料の3ページ、ルートAが温泉街のゆずりは地区と奥四万湖を結ぶルートで往復3.8キロ、資料の4ページ、ルートBが奥四万湖を周回するルートです。実施体制については、自動運転システム提供者が日本モビリティ株式会社で所在は前橋市内です。運行管理者は、関越交通株式会社となります。実験車両は、2種類の車両で行います。
資料6ページ、ルートAの国道、トンネルを通る車両は7人乗りのワゴン車、トヨタヴェルファイアを予定しております。
資料7ページ、ルートBの奥四万湖の周回車両は11人乗りのバス、桐生市にございます電気自動車専門メーカーのシンクトゥギャザー、車両e―com10を予定しております。この11人乗りバスにつきましては、時速20キロ未満での走行を予定しております。
そして、自動運転システムを搭載した車両を走行させるため、環境の1としてGPS基準局を設置します。これは、GPS受信機やアンテナ、ポール、ケーブル、ノートパソコン、機器ボックスなどの装置となります。
環境の2として強反射塗料を道路の面に塗布します。これは、GPSの入りの悪い箇所などで自動運転の走行を安定させるために日本ペイント株式会社製のターゲットラインという15センチ幅の灰色のラインの特殊塗料を道路の面に塗ります。特殊塗料を塗る場所は、奥四万湖の周囲1周とトンネル2か所となります。また、この塗料につきましては、積雪で路面が隠れた状態では認識できないこととなり、激しい雨で路面に水が多い状態でも認識できないとのことでございます。
環境の3として、トンネル内に通信機器を設置します。
最後に、資料5ページの本番走行概要(案)のダイヤ表の見方ですが、上から1行目の出発地の欄はゆずりは地区の出発の時間帯です。
2行目の周回の欄は、奥四万湖の集会の出発時間帯で1時間に1本、毎回15分出発となります。
3行目の温泉街の欄は、ワゴン車がゆずりは地区からダムへ出発する時間です。
4行目のダム側の欄は、ワゴン車がダムからゆずりは地区へ戻るために出発する時間です。
以上が事業の概要となります。日本モビリティ株式会社からは、総務省の採択による単年度の実証実験ですが、継続で実証実験を続けられる可能性もあるとの説明でございました。
補足の説明は以上でございます。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)10番、関さん
〇10番(関 常明)以上で終わります。