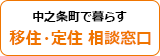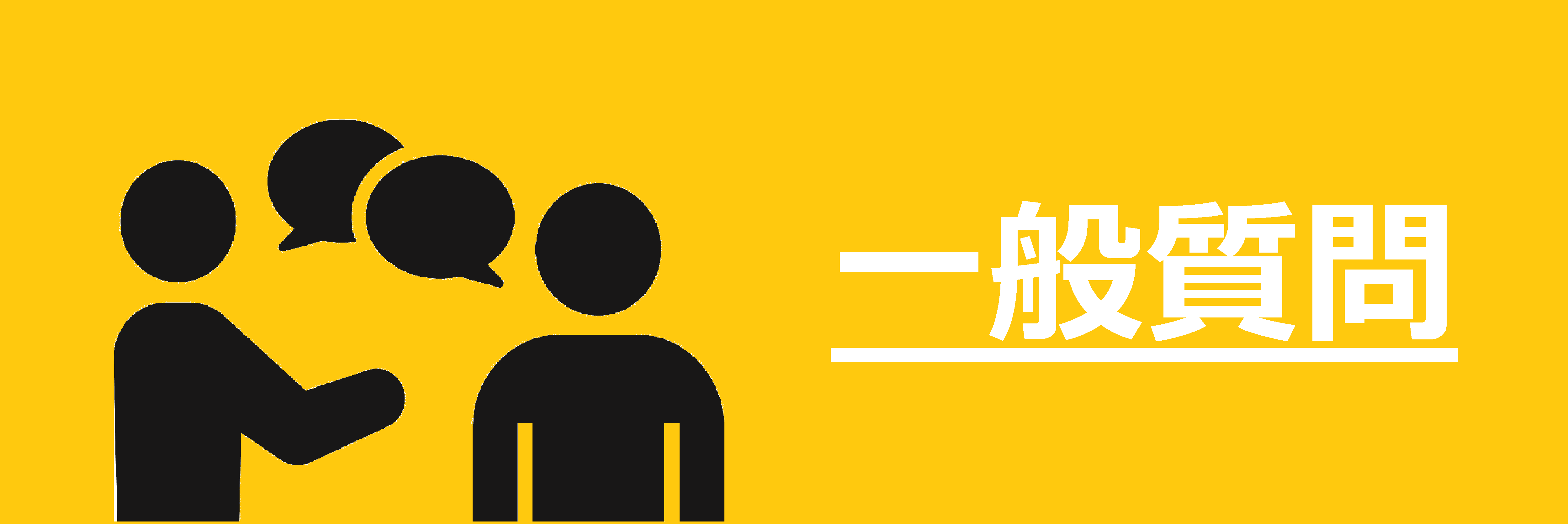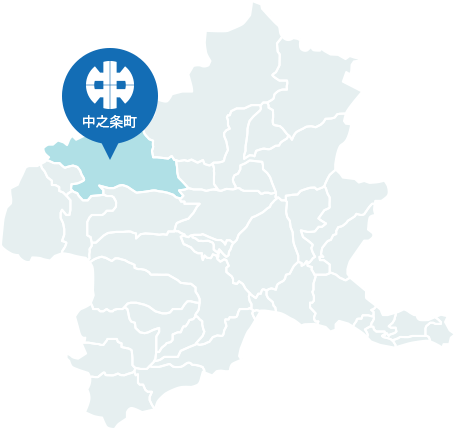本文
令和6年9月定例会議 一般質問(割田三喜男議員)
03 4番 割田三喜男議員 令和6年9月定例会議一般質問
○4番(割田三喜男)それでは、議長の許可をいただきましたので、具体的には5項目の質問をさせていただきます。この一般質問は、政策議論をする場だと思っておりますので、政策面で大きなくくりとして2点です。
〇政策形成のトレーサビリティー(プロセス)について
まず、1の政策形成のトレーサビリティーについて、プロセスです。トレーサビリティーは、食品加工の面でよく聞く話だと思いますが、追跡可能性です。政策決定の過程で地域の課題を的確に把握し、どのようなエビデンスで誰がいつどのように決めたかのプロセスの透明性が欠かせないと思います。それには、計画段階から官民共創で仕上げていくことが町ぐるみで納得し、政策の質を上げるためにも必要ではないでしょうか。その観点から3項目の質問をさせていただきます。
まず、(1)、町道沿線危険支障木伐採補助金についてです。令和5年度にこの制度が開始されましたが、これまでの申請状況と事業効果の検証はどうかお伺いいたします。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)それでは、割田三喜男議員のご質問にお答えをさせていただきます。
支障木伐採の補助金についてでありますけれども、令和5年度の実績は2件で20万円の支出となってございます。これらの2件は、枯れ木支障木につきまして所有者において除去対策を講じていただいたため、町道への倒木被害の防止が図られたものでございます。
〇議長(安原賢一)4番、割田さん
○4番(割田三喜男)ありがとうございました。枯れ木支障木は危険ですので、この補助金を活用し、伐採をさらにしていただくよう慫慂(しょうよう)をお願いいたします。今後この補助金がさらに活用されることによる倒木被害の軽減を願っております。
そこで、倒木が危険な枯れ木は原則補助対象でありますが、通行に支障がある枯れていない、年々大きくなっている草木が多く、住民からの苦情を聞きます。民有地の枯れていないが通行に支障がある木は、所有者に速やかに対策をしていただくようお願いしているようでありますが、なかなか進まない面があると思います。対応はどのようにしているかをお伺いします。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)支障木によって通行に支障がある草木の対応についてというお尋ねでありますけれども、中之条町における町道の延長、これは約700キロメートルございます。除草、枝打ちなどの対応の予算化は全ての路線まで行き届かないのが現状でございます。
そのため、各行政区の皆様が実施する道路愛護運動や令和2年度から実施している直営伐採事業への参加をお願いし、対応を図っている状況でございます。
また、区長さんや町民の方から通行に支障を来す草木の通報をいただいた場合は、職員が現地調査を行い、建設課直営作業による対応、また業者発注による対応を図っている状況でございます。
一方、通報による支障物件が民有地に存在するケースでは、土地の所有者を特定し、所有者の責務としてご対応いただくよう対策のお願いをしている状況でございます。
以上です。
〇議長(安原賢一)4番、割田さん
○4番(割田三喜男)毎年直営伐採事業等による対応をしていただきまして、地元住民は感謝しております。ありがとうございます。町道沿線に張り出している民有地の草木は、所有者への働きかけを引き続きしていただくとともに、地元との直営伐採による対応もあるかと思います。その町道を使用していない住民が多い区はなおさら自分事と考えていただけない面があるようでありますが、共用している住民が区への協力を募りながらの対策もあると思います。今後とも直営作業等での対応などを進めていただければと思います。よろしくお願いします。
また、道普請と道草刈りも人口減少、高齢化で地元の作業は苦労であると聞いております。道路清掃車などの導入により処理していただくよう併せてお願い申し上げます。よろしくお願いします。
では、次の質問をさせていただきます。次に、移動販売車の導入について質問させていただきます。伊参地区は、高齢化率が52%を超え、中之条町で最も少子高齢化、人口減少が進んでおります。買物に困っている人も多くいると思われ、2年前にはいさまの家プロジェクトで生活に関するアンケートを毎戸実施しました。そのときは、買物に困っているという回答はあまり見受けられませんでした。その後、全国的に高齢者の自動車、運転事故が相次ぎ、自動車運転免許を返納したという話が多く、買物難民が移動するのに難しくなった事例が多くなったのではないでしょうか。
そこで、過疎交付金による移動販売車の購入でありますが、交付金申請時の導入計画はどのようなものかお伺いいたします。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)移動販売車の導入についてのお尋ねでございますけれども、令和6年度より新たな買物支援策といたしまして、主に高齢者の見守りを兼ねた移動販売車による買物支援事業の実施のために10割補助事業である国の過疎地域持続的発展支援交付金を活用するべく申請を行ったところ、採択となったところでございます。
導入時における計画といたしましては、町内でも人口減少、少子高齢化が特に進行している地区であり、地区内において買物を行うための商店が極めて少ない伊参地区及び六合地区を主な対象地域といたしました。事業内容は、町が事業者へ移動販売車の貸出しを行い、定期的に移動販売を実施することによって独り暮らし高齢者等の見守りも兼ねた買物弱者への支援を実施するものでございます。
また、移動販売車による販売所を個人宅だけでなく、地域の公民館等のコミュニティー拠点も活用することによって地域住民の交流を促進し、健康維持やコミュニティーの活性化も目指すものとなっております。
なお、買物の支援の需要を把握するために、令和6年6月に該当地区におけるニーズ調査を実施したところでございます。
〇議長(安原賢一)4番、割田さん
○4番(割田三喜男)ありがとうございました。現在買物支援バスを運行していただいておりますが、集落ごとに移動販売車を運行していただければありがたいお話だと思います。
そこで、交付金の決定後に先ほどのアンケート調査を行うということでございますが、政策形成時のエビデンスとの違いがあるかお伺いいたします。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)買物需要を把握するためのアンケート調査でございますけれども、伊参地区及び六合地区の全世帯となる932世帯を対象に6月に実施をいたしましたところ、372の世帯から回答があり、回収率は39.9%となってございます。
結果といたしましては、個人宅への移動販売を利用したいと考えている世帯が両地区合わせて167世帯、公民館等のコミュニティー拠点での移動販売を利用したいと考えている世帯が154世帯となり、約4割の世帯が移動販売を利用したいというアンケート調査結果が出てございます。
また、自由意見といたしまして、現在は車を自分で運転して買物に行くことができるため不便を感じることはないが、今後運転ができなくなった際には移動販売を利用したいといった意見も多くございました。
アンケート調査の結果から、移動販売の需要は高く、地域において自立した生活を営む一助として移動販売の実施は効果が高いものと考えております。今後も移動販売を通じて地域における買物弱者や見守りを必要とする住民が安心して暮らすことができる町づくりを進めていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
〇議長(安原賢一)4番、割田さん
○4番(割田三喜男)ありがとうございました。各地区の公民館などに見守りを兼ねて運行する計画もあるようですが、住民のみなさんのニーズを伺いながら健康で安心して暮らせるための運行をお願い申し上げます。
次に、(3)の耕作放棄地対策について質問させていただきます。伊参地区は、耕作放棄地が激増しており、耕作放棄地草刈り補助金を新設いただきまして、感謝を申し上げます。今年度この制度が開始されたところでありますが、これまでの申請状況と検証はどうかお伺いさせていただきます。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)耕作放棄地の対策のご質問でありますけれども、当補助金は耕作放棄地の解消を目的として本年の6月3日から申込みを開始いたしました。この事業は、耕作放棄地の解消が町内で完結できるよう、町在住の個人や町内所在地のある団体が施工業者として役場に登録し、草刈りができない農地の所有者が登録された個人や団体に作業をお願いするという仕組みでございます。8月20日現在、草刈りを請け負う施工登録者は9件で、草刈りを依頼された方が2件、面積約1,200平方メートルでございます。
なお、申請まで至っておりませんが、補助金の問合せは10件以上来ている状況でございます。問合せの中で農地でない雑種地や農地であっても耕作していない一部分を草刈りしてほしいという方もおりましたが、現在のところ補助対象としておりません。
また、申請方法を簡略化してほしいという意見もございました。今後当事業の認知が広まりましたら件数と面積は増えるものと思われますが、町単独の事業でございますので、皆様が利用しやすいよう柔軟に要綱を整備することも検討してまいりたいと考えております。
〇議長(安原賢一)4番、割田さん
○4番(割田三喜男)今後利用しやすいように検討していただけるという答弁をいただき、誠にありがとうございます。不在地主や高齢者所有の耕作放棄地の申請方法や費用負担など難しい面があると思います。
また、請け負う人も自分の所有地で手いっぱいの場合もあるのではないでしょうか。自分も所有地の耕作放棄地の草刈りをしておりますが、今後もずっと草刈りを続けなくてはならないのか苦慮しております。何かよい作物を植えられないか、活用できないか、国では粗放管理や適正な林地化などを推奨しているようでありますが、今後の対策はどのようにしたらいいかということで考えております。
ここで、耕作放棄地草刈り補助金の政策決定時の議論の道筋と、耕作放棄地の今後の対策についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)耕作放棄地の今後でありますけれども、参考までに現在中之条町の耕作放棄地の面積をお伝えしたいと思います。これが農家台帳を基にした面積でありますが、2,015ヘクタール、これが町全体の農地であります。そのうち約600ヘクタールが耕作放棄地となってございます。大体3分の1ぐらいが耕作放棄地というような状況ということを押さえておいていただければと思います。
令和5年度の未来戦略ミーティングの中でも草刈り等の管理がされずに土地が荒れているという意見がございました。草刈りをしたくても高齢のためできない、また遠方に住んでいるため、管理が難しいという方がいらっしゃる現状がございます。そのような中で草を刈ってほしい方と地域の管理のために草刈りができる方をお互いにつなげていこうということから本事業を立ち上げさせていただきました。
なお、草刈りの作業を安全に行っていただくことも重要であり、未来戦略ミーティングにおいても機械の正しい使い方等知識や技術を学べる場が欲しいという意見がございまして、町では5月から7月にかけて3回の刈払取扱作業者安全衛生教育の講習会を開催をいたしました。参加の方は男性57名、女性7名、計64名の方が受講をしていただきました。
耕作放棄地の今後の対策といたしましては、町では耕作放棄地対策草刈り補助金制度を設けましたが、農業者に農地を利用していただければ耕作放棄地ではなくなるわけでございます。食料の生産基盤である農地を保全するためにも国、県と一緒に担い手に農地を集約したり、新規就農者を増やす取組等、政策面において協力していきたいと考えておりますので、割田議員にもよろしくお願いいたします。
〇議長(安原賢一)4番、割田さん
○4番(割田三喜男)ありがとうございました。粗放栽培として、長野県ではヘーゼルナッツの植栽を大々的に推進しており、隣村でもこのヘーゼルナッツの植栽をしている方が何人かいらっしゃるとお聞きしました。自分もこれに注視したいということで考えております。
耕作放棄地が増えてくると野生動物の活動が広がり、鳥獣害被害が拡大すると思います。鳥獣被害対策実施隊関係で質問させていただきます。日頃から鳥獣被害対策実施隊の方々には、有害鳥獣を駆除していただき、深く感謝を申し上げます。先日ある実施隊の方からお話をお伺いしました。その方は、今年度既にサル、イノシシ、シカを約100頭捕獲したということです。年齢は70歳代後半で、あと5年しか活動ができない、自分の後をやってくれる後継者がいないと今後有害鳥獣のやりたい放題になるということで、後継者問題に苦慮しておりました。
そこで、鳥獣害被害対策実施隊の高齢化が懸念されておりますが、行政としてこの対策はどうかお伺いをさせていただきます。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)有害鳥獣についてのご質問をいただきました。中之条町では、町の鳥獣害対策体制の充実を図るため、狩猟関係者だけではなく、区長会や森林組合等もメンバーに含んだ鳥獣被害対策協議会を組織してございます。当協議会におきましては、国庫補助事業を活用し、わなや追い払い資材等をそろえ、有害鳥獣対策に役立てております。また、実施の有害鳥獣の捕獲、駆除活動は、当協議会の傘下となります有害鳥獣対策実施隊によって行っていただいております。実施隊は、狩猟免許の所有者により令和6年8月1日現在92名の隊員で組織されております。実施隊につきましては、70歳以上が51名、全体の55.4%を占めておりますが、熟練した経験を有し、活躍をいただいております。令和5年度におきましては、新規隊員4名に加入していただきましたが、後継者となりうる20代、30代につきましては、令和5年度は1名が加入し、令和6年度は2名が加入予定でございます。
なお、実施隊を増やすため、新規で狩猟免許を取得する方に対しまして補助を行っておりまして、令和5年度は4名の方がご利用されております。
以上です。
〇議長(安原賢一)4番、割田さん
○4番(割田三喜男)狩猟免許取得補助制度など、行政として対策をしていただいていることを確認させていただきました。ありがとうございました。この耕作放棄地問題は、全国的にも非常に難しい問題だと思います。地元のある人は、農地が原野になってしまったものを含め、鳥獣害被害対策のためにも公共事業、公費負担で農村環境整備をしてほしいと要望している方もいらっしゃいます。誰が何でどうやって農地を守るをこの後質問させていただきます地域計画で議論する必要があると思いますので、よろしくお願いします。
〇政策のワイズスペンディングについて
続きまして、2の政策のワイズスペンディングでございます。ワイズスペンディングは、政策効果が乏しい歳出を徹底的に削減し、政策効果の高い歳出に転換するものであり、政策効果を高め、予算の質を向上させる取組として重要であります。
昨日の財政の健全化比率の報告がありまして、適正で堅実な財政運営をしていただいておるところでありますが、今年度は自主財源の町税が見込みが20億円を割るという見込みであります。このため、一段とワイズスペンディングが必要と思いますので、この観点で質問させていただきます。
まず、(1)、地域計画についてです。計画行政と言われるように、官民共創で計画策定を行い、事業を実施していくことやいわゆるPDCAで需要効果を高めていくことで各種計画策定は非常に大切なものだと思っております。
国が法令で定める計画は、本年度策定する第3期総合戦略やこの地域計画など多数あります。7月17日の上毛新聞一面に「農地利用地域計画進捗に差」という見出しで掲載されておりました。地域計画策定までの流れとして、(1)で意向調査、(2)で現況図作成、(3)で座談会、(4)で結果取りまとめの公表、(5)で計画案作成、(6)、説明会開催、(7)、策定公表とありましたが、来年までにこの計画策定する必要があるということですが、当町での進捗状況はどうかお伺いします。
また、策定に向けて課題となっておるものは何かお伺いさせていただきます。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)議員お尋ねの地域計画でございますが、農業者の高齢化や後継者不足により農地を維持することが難しくなっている中、将来にわたって農業と農地を残していくためには誰が耕作し、耕作する人が経営しやすい環境をどう整えるか、地域が一体となって考えていく農地の将来計画でございます。
具体的には、地域ごとに農家の方々にご参集いただきながら、10年後地域の農業をどうしていきたいか、そしていつ誰がどの農地を担っていくかを話合い、その結果を目標地図という地図に落とし込んでいきます。
進捗状況といたしましては、既に町では地域ごとの計画策定の協議の場を設けまして、目標地図の作成に取りかかっており、議員おっしゃる意向調査、現況図作成、座談会まで進んでおります。8月に成田・美野原地区において実施し、9月中にも順次他地域で実施してまいります。地域ごとに2、3回協議の場を設け、目標地図を作成し、将来展望を共有いたします。
策定に向けての課題ですが、地域の中心的な農業者に参加をお願いしても人が集まらない、10年後なんて考えられないと関心を持っていただけないことがございます。成田・美野原地区におきましても、56%の出席でございました。地域計画策定後は、農地は目標地図で予定した耕作者に集約されると思われます。また、今後国庫補助事業が地域計画と連動する予定がありますので、計画策定は必要でございます。なお、地域計画は1回作成すればよいのではなく、策定後も見直していく予定であります。耕作を予定していた方が耕作できなくなった場合など、状況に応じて随時見直すことや新規の耕作者を追加することも可能であり、現時点においてできる範囲で取り組み、計画完成となります。
以上です。
〇議長(安原賢一)4番、割田さん
○4番(割田三喜男)ありがとうございました。農地を農地として集約、維持していくことについて今後も見直しをしながら進めていただきたいと思います。
さきの一般質問で話をさせていただきましたが、地域計画の策定で懸念されるのは耕作者がいない空白地の多発だと思います。伊参地域では、特に集約できない農地、耕作放棄地が多発するのは不可避だと思います。非常に難しい問題ですが、耕作放棄地の適正管理、粗放栽培など粘り強く検討を進めていく必要があると考えます。
食料・農業・農村基本法がこの6月に四半世紀ぶりに改正されました。1つとして、人口減少下における農業生産の維持、発展と農村の地域コミュニティーの維持の実現を目指し、基本理念の見直しと基本政策等が定められたところでございます。法定計画に沿って自治体ごとに計画を策定し、国が定めた事業に交付金を出す流れとなっております。いわゆるひもづけです。
この地方から出される企画を中央で評価し、交付金を分配する仕組みについて、中央集権的と批判されておりますが、この制度をうまく活用する必要があるのではないかと思います。この地域計画も各種事業交付金とのひもづけが予定されているようです。地域の課題を的確に反映させた政策効果の高い計画策定が求められております。
急速に進む少子高齢化、人口減少により農山村の過疎化は著しく進んでおりまして、前年同様に政策を続けていっては集落を維持することは難しいと思います。この地域計画に基づく地域の総合対策が必要とも思います。地域としてもしっかり取り組むとともに、行政においても伴走支援やプッシュ型支援をお願い申し上げます。
続きまして、(2)の健康増進施設についてでございます。6月議会の文教常任委員会にも質問が出ていたと思いますが、整備計画はどのように進んでいるかをお伺いさせていただきます。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)健康増進施設へのお尋ねでございますけれども、健康増進施設につきましては、既存の施設を活用し、女性や高齢者が気軽に健康維持のために利用できるよう整備を進めております。
4月には、場所の検討を行い、施設の立地条件や利便性、利用状況の有無等から判断し、バイテック文化ホールの吾妻広域圏事務所で使っていた跡の部屋を活用したいと考えております。
5月から7月にかけて導入する機械器具など施設内容及び利用計画の検討を行い、8月からは必要とする事業費について算出を進めている状況でございます。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)4番、割田さん
○4番(割田三喜男)ありがとうございました。
次に、どのようなエビデンスやニーズに基づいて政策立案されたのか、専門的なスポーツトレーナーや運動療法士などの方の意見を聴取されたようですが、施設整備の経緯と規模及び設備機材等利用計画などはどのように決まったのかお伺いさせていただきます。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)どのような計画をされているかというお尋ねでありますけれども、既存施設利活用の施策として健康増進施設の整備を生涯学習課と保健環境課で連携して進めております。既にあるものを活用し、最小限の投資による施設整備を基本に検討しております。
具体的には、施設内容の検討には町民の意見を反映するため、ライフコーダー利用者とスポーツ推進委員の方々にスポーツジムへの視察体験モニターとしてご協力をいただいております。
また、健康運動指導士の方に運営管理を含め適切な運動と施設内容に関して専門家としてのアドバイスをいただきながら進めているところでございます。
〇議長(安原賢一)4番、割田さん
○4番(割田三喜男)ありがとうございました。最近テレビ等で健康サプリメントや健康増進器具のコマーシャルが多くなったと感じております。健康維持、増進は今非常に高まっているということを考えております。
そんな中でこの政策はタイムリーな住民のニーズに合ったものと思っております。高齢者のフレイル予防にもつながると思います。利用しやすい施設になりますようお願い申し上げます。
さて、国は健康増進、健康づくりを推進しておりまして、スポーツ庁においてもスポーツ・健康町づくりの事業メニューがあるようです。昨年一般質問で法定計画であるスポーツ推進計画について質問させていただきましたが、計画策定はどうか、またスポーツ庁のこの交付金などを活用できないか教育長にお伺いさせていただきます。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)教育長
〇教育長(山口暁夫)施設整備にあたっては、本事業が対象となる補助金や起債等を検討し、より有利な財源で進めてまいりたいと考えております。議員からご提案いただいたスポーツ庁の交付金や推進計画策定も含め、今後検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
〇議長(安原賢一)4番、割田さん
○4番(割田三喜男)ありがとうございました。超高齢社会になり、健康寿命を延ばすことが重要であり、スポーツによる健康づくり、生きがいづくり、仲間づくりは効果があるものと考えております。
中之条町では、歩く健康づくりの研究が有名であり、これとコラボしたスポーツ町づくりの推進を進めていただければと思います。それには、健康づくり協議会や老人クラブ、スポーツ関係者など幅広い連携が必要と思います。関係者でスポーツ、健康、町づくりをどういうふうにしていくか、子どもから高齢者まで総合的にスポーツ推進をどうしていくかの計画づくりは重要と考えますので、今後も計画策定を検討していただくようお願い申し上げます。
以上で私の質問は終わりにさせていただきます。ありがとうございました。