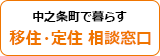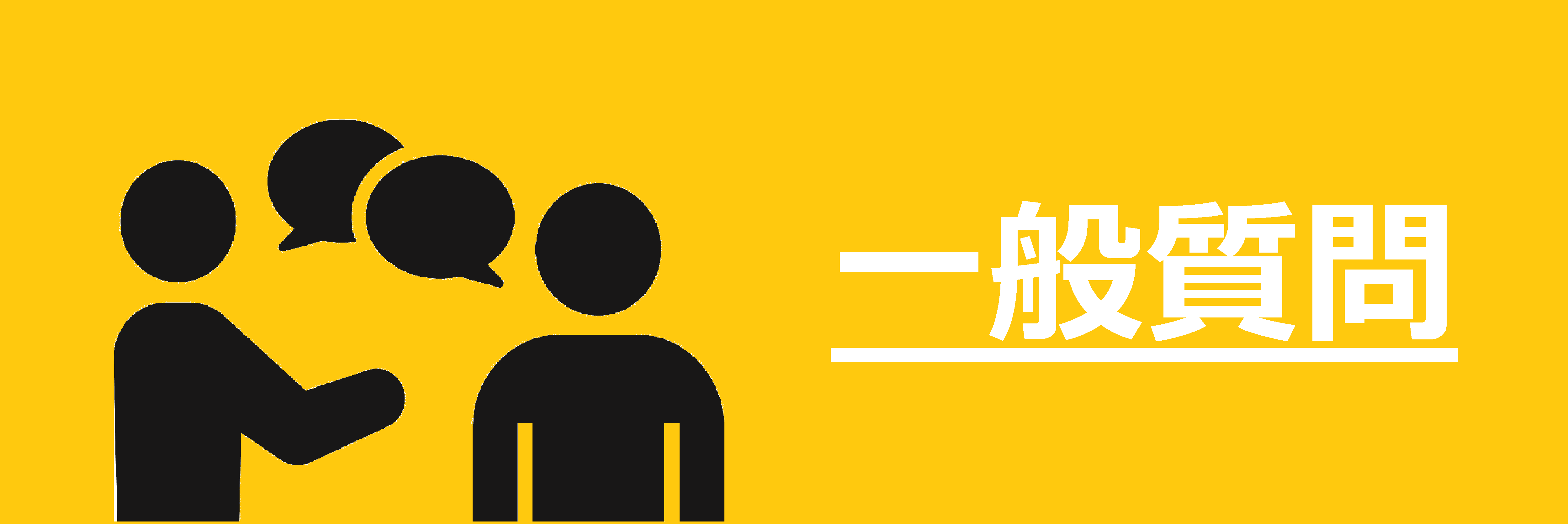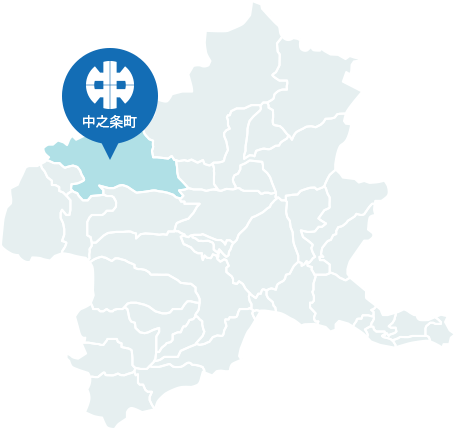本文
令和6年6月定例会議 一般質問(原沢香司議員)
03 1番 原沢香司議員 令和6年6月定例会議一般質問
○1番(原沢香司)今回の一般質問では、通告に従い、3点について伺います。
1点目が町職員の働き方についてです。次に、補聴器の購入補助について。最後に、3月議会に続いてとなりますが、六合中学校の教育事務について質問をいたします。
町職員の働き方について
4月に人口戦略会議が消滅可能性自治体を発表しました。この統計によれば、20代から30代の若年女性を子どもを産める世代の主力と位置づけ、その割合が一定割合、今回の統計では50%ということですけれども、これを下回ると早晩、その自治体は破綻するとされています。中之条町は、2020年と2050年とを比較すると63%若年女性が減るため、消滅可能性自治体に分類されています。この統計について、事前の通告しておりませんので、コメントはなくても結構なのですけれども、町長の受け止めなどあればぜひお聞かせをいただければと思います。
私は、この統計を性的役割分担として子どもを産むことを女性に押付け、結婚を選ばない非婚、晩婚化や出産の高齢化が進んでいる実態も顧みない、大変無礼であり、無神経な統計であり、自治体にとっても非常に失礼なものだと思います。中之条町でもこの地域の存続のために人口減少への対応策や独自の地域づくりを目指し、町民と行政とが懸命に知恵を出し合い、あらゆる努力を行っている最中です。10年前に消滅可能性リストが発表され、政府は地方創生に力を入れ始めたように見られますが、自治体間で移住者を奪い合うような実態になっていなかったか、しっかりと国の施策を振り返るべきだと思います。
このような統計に一喜一憂せず、この町に合った形で独自性のある地域づくりを今後とも追求していくべきだと考えます。そのためには、外丸町長の掲げる「共創のまちづくり」をより一層発展させることが必要だと考えます。今回一般質問で取り上げるいずれの問題も町民の生活を守り、安心して住み続けられる町づくりに欠かせないことだと考え、質問をさせていただきます。
まず、町職員の働き方についてです。私がこの町議会に一員として加わり、1年が経過するわけですが、町民のみなさんから最も多く聞く声の一つが町役場で働く職員に対する心配の声です。幾つかの声を紹介いたします。「近年若い職員の退職が目立つことが気になる。」、「役場に用事があって立ち寄っても職員が忙しい様子で声がかけられなかった。」、「土、日もボランティアとしての仕事が多く、見ていてとても大変そう。」など、どれもが町民が職員を心配する声です。
昨年6月の議会でも男女共同参画についての質問で触れましたが、町の職員の働き方はそのまま町民の福祉や生活に直結するものです。仮に町民の幸福度は高くても、それを支える立場である職員の犠牲の上に成り立っているのであれば、その幸福度は真実のものとは言えません。町民が心配することなく職員のみなさんが生き生きと働けるように、まずは現状の問題点をしっかりと捉え、持続可能な働き方を追求していかなければいけないと考えます。
最初に伺います。最近5年間での職員の時間外労働の増減はどのようになっていますか。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)それでは、原沢議員のご質問にお答えさせていただきますが、一般質問の通告にはございませんでしたけれども、せっかく登壇していただいてご質問いただきましたので、今回は人口減少の関係について考えを申し上げさせていただきたいと思います。
今日でしたかの新聞でしたか、出生率が1.20で東京都は0.99というような数字も出ております。中之条町も従来私が申し上げているのですが、20年後には1万人を切るだろうという推計がされております。そういった中で中之条町、生き残りをかけて頑張っていかなければならないということはもうもちろんなのですけれども、だからこそ高齢者の方々に元気で長生きをしていただき、そしてまた子どもを育てる、そういう世代をしっかりと応援していく子育て支援、やっぱりこの子育て支援がしっかりできることによって高齢者を支えるということに間接的になるのだと思うのです。
子ども達が生まれるのが、令和5年度が出生者が57人でした。令和4年度は47名でした。これが極端に増えるということは考えられないと思いますけれども、だからこそそういう子ども達を地域で育てて、その子どもさん達が大きくなって、例えば東京に就職されたり仕事しても、我が町中之条町はこんないい町なのだというものを植え付けて、そしていつかは帰ってきていただいて、ふるさと中之条町を愛していただけるような、そういったまちづくりをしていくのが我々の今求められている責務だと思っております。ですので、ぜひ中之条町議会議員として原沢議員にもそういったことを考えながらご助言いただければ大変ありがたいと、このように思っております。よろしくお願いします。
それでは、原沢議員の町の職員の働き方、これについてのお尋ねでありますけれども、職員の時間外労働の推移ということでございますけれども、年度ごとで事業内容や事務量も異なりまして、また人事異動などにより初めて事務に携わる職員と長く業務に携わり知識や経験が豊富な職員とでは同じ業務であっても差が出てまいります。さらに、部署によっては育児休業や休暇等による人員削減など、人的要因によって変わってまいります。そのため、年度や部署ごとについて単純に比較するのは難しい面もございます。いろいろな複雑化した事情を加味せずに単純に直近の5年間を全体的に比較したとすれば、令和元年度の総時間外数が2万時間を超えていたのに対し、令和5年度では1万時間強程度であり、減少傾向にあります。最もコロナ禍においては、コロナ対策における業務は増加をいたしましたけれども、一方でイベントなどの各種事業が中止や規模縮小となり、また会議等も書面決議で行われるなど、そういった要因もあるかと考えております。
以上でございます。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)まず、冒頭に通告にない人口減少についての町長の受け止めということでコメントをいただきまして、誠にありがとうございます。私もやはり中之条町で生まれ育った子ども達がまたこの町で生活したい、そういうふうに帰ってこられたり、そういう町というのはよそから見た場合も大変魅力的に映ること間違いありませんので、町長がお話しされたようにこれからも精一杯この町がより住みよく、そして外から見てもいい町だと思ってもらえるような施策について様々議会でもご提案していければと思っております。どうもありがとうございました。
そして、時間外労働についての増減、答弁をいただきました。減っているということで、大変それはいいことではありますけれども、この間コロナ禍という特殊状況ありましたので、単純な比較は難しいということなのだと思います。この新型コロナウイルス感染症が5類に移行して1年、徐々にイベントや会議も復活していると思います。残業時間の推移については、これからも注視をしていただき、基本的に業務は時間内に終了できるように管理を徹底していただきたいと思います。
時間外労働についての質問を続けます。町役場の業務は、本当に多岐にわたります。部署によっては、イベントの準備があったり、年に1度の確定申告などで局面的に時間外労働が増えてしまう、そういう実態もあろうかと理解をしております。労働法規では、働く人の健康を守るために時間外労働について月当たりの時間を定めています。労働基準法で定める45時間、過労死ラインと言われる80時間に比べて特に時間外労働が多い職員数を把握していますか。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)時間外労働につきましては、原則として各課の所属長が命令した期日や時間を該当日ごとに総務課長に連絡する方式を取っております。月初めにタイムカードや時間外命令簿と付き合わし、月ごとに集計を行っておりますので、各課や個々の職員ごとに時間外労働時間等について管理をいたしております。災害対応や選挙事務など、業務の実施時期、その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務、いわゆる「他律的業務」を含め、国等の政策に伴う自治体への付託事務や大規模なイベントなどにより業務量が一時的に増加することもございます。「他律的業務」とは別に、議員ご指摘のとおり、慢性的に一定の基準を超える職員がいた場合には、所属長等とも意見交換を行い、健康面や業務遂行上の改善など、その都度本人へ直接指導や注意を実施しております。
以上です。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)労働基準法第36条を根拠とする36協定、これの締結と提出をしていても、残業時間が月45時間を超えた場合には、労働時間について定めた労働基準法第32条違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。36協定を締結せずに残業や休日出勤をさせていた場合も同様の罰則があります。この辺りは、十分労務管理上ご存じのことと思いますが、まずは職員の健康があっての役場の仕事です。慢性的に残業が多いということは、必ず理由があると思います。それが人員配置と業務量のミスマッチなのか、業務の効率化を図ることができないのか、様々な角度から検証が必要だと思いますので、時間外労働を少しでも減らしていけるように重ねて要望をいたします。
次に、職員の数と構成について伺います。最近5年間における職員数の推移と年齢構成の変化はどのようになっていますか。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)最近5年間における職員の推移ということでありますけれども、特別職、再任用職員及び会計年度職員を除く職員数で申し上げますと、職員数は減少しております。
年齢構成の変化ということですが、20代前半の若年層については定期的な採用もございますので、比較的大きな変化はございません。20代後半から30代前半の職員、また40代後半から50代の職員においては増加傾向となっております。一方で30代後半から40代前半にかけての職員数が大きく減少しておりますので、人事関係や効率的な業務の遂行など今後の行政運営への影響は懸念しているところであります。組織運営につきましては、今後の動向を見据えながら検討してまいりたいと考えております。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)30代の後半から40代前半、まさに中核として働き、これからの役場の業務を支えていく方々が大きく減少しているということでした。今後の行政運営にも影響が懸念されるという答弁でしたが、10年後やそれ以降も見越して職員の年齢構成を見ていかなければいけないと思います。
事前の通告にないのですけれども、職員の離職の状況について近年の傾向が分かれば答弁いただけますでしょうか。
〇議長(安原賢一)総務課長、お願いします。
〇総務課長(朝賀 浩)原沢議員の離職の状況ということでございます。先月になるのですけれども、吾妻郡の総務課長会議のほうが開催されました。まさにその中で職員の離職について意見交換をする機会がございました。定年を前に1、2年を残しまして早期退職ですか、そういったことは今も昔もあるわけなのですけれども、特に若年層、それから中堅職員、こういったところの退職というのは実際中之条町に限らず郡内でも比較的増加傾向にあるというような印象を持っております。日本の場合、終身雇用というのが一つの特徴であったわけなのですけれども、そういったこともだんだん崩れ始めておりますし、また私の主観ではありますけれども、私が就職した頃から比べれば比較的転職等に抵抗がない、そんな世代になったのかなというふうな印象も持っております。
いずれにいたしましても、今議員からご質問いただいたとおり年齢層ということになりますと中間層につきましては、経験であったり、それから知識、また機動力、そういった面でも町行政の中枢をなす年代層でございます。そういった中間層の退職といいますか、人材の流出というのはいずれにいたしましてもやはり町行政につきましては、大きな痛手であることは間違いありませんので、そのように感じている次第でございます。
以上です。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)ありがとうございました。通告なかったのですけれども、離職の状況について課長から答弁いただきました。
若年層や中堅職員の退職が郡内、中之条町に限らず増加傾向にあるようだということだったのですけれども、過日毎日新聞が報道したデータなのですけれども、総務省が集計したところによると教員や警察などを除く一般行政職員のうち2022年度に主に自己都合で仕事を辞めたのは1万2,501人、これが2013年度では5,727人ということで、比較すると10年で2.2倍に増えているということです。新聞報道によれば、待遇への不満や業務量の増加が影響していると見られる。30代までの若手が全体の3分の2を占めているという報道でした。冒頭に町民の心配の声として紹介をいたしましたが、若い職員さんの退職、これは中之条町や吾妻郡だけに限らず、全国的に増えている傾向のようです。若い職員の退職が多いとなると、これから役場組織を持続的に運営するには大きな課題があると思います。
ここで、伺います。近年の職員採用で抱えている課題はありますか。中途採用が増えているかどうかを併せて伺います。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)答弁をさせていただきます。
国や県、あるいは他の市町村の現状を細かく把握しているわけではございませんけれども、町職員の志願者は民間企業をはじめとする社会全体の景気や動向等に大きく左右される印象がございます。
職員採用における課題ということですけれども、採用したい人材が必ずしもその年度の採用試験に応募していただくとは限らず、また採用年ごとでも年齢や男女差、学歴や前職歴のある方など、応募に差異がございます。特に有資格者の採用や専門的な技術職については、さらに採用に苦慮している状況であります。応募者側からすれば、人事やその他の事由から必ずしも資格が生かせる部署への配置とならない場合もありますので、せっかく取得した資格や培った技術を生かし、民間企業への就職を希望する人もおると思います。また、採用試験の段階で国や県、他の自治体等と併願し、最終的には町を選択してもらえないなど、厳しい現実もございます。
中途採用につきましては、特にここ数年の傾向では多くなっているという印象でございます。人材育成という点では、既に社会人を経験しているということはプラスに働くことも多く、実際に採用試験においても広く人材を確保できるように応募年齢を引き上げるなど、一定の配慮を行っているところでございます。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)採用での課題ということで、いろんな局面お答えいただきましたけれども、社会人の経験が人材育成にプラスに働くことが多いという答弁いただきました。この視点とても大事だと私考えていまして、とにかく広範囲にわたる町の業務ですから、多様な経験をしてきた社会人がそのチームに加わることで得られることは非常に多いと考えています。町民のみなさんも今本当に多様な働き方していて、生活のスタイルも多様化しています。社会人として様々な経験を積んできた人達が多様化する住民の暮らしに行政職員として対応し寄り添っていく、そのことが町民の生活の安心や状況の向上にも必ず寄与することと思います。ぜひ多様な人達が町職員として働いていけるよう広く門戸を開いていただきたいと思います。その際に既に町役場で経験を積んでいる方を積極的に常勤職員として採用することをぜひ検討していただきたいと思います。
伺います。会計年度任用職員を常勤職員として採用するための手立ては取られていますか。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)町として会計年度任用職員の方に対しまして、常勤職員への任用替えということは実施をしておりません。常勤職員を希望される方は、ほかの方同様に採用試験を受けていただくこととなりますが、フルタイム、パートタイムを問わず、いろいろな理由により会計年度任用職員のままを希望している方も多くおります。
参考までに申し上げますと、過去にも臨時職員や会計年度職員から採用試験にチャレンジし、正規職員となって活躍いただいている職員は一般職や専門職を問わずおりますので、今後も希望されている方は応募の上、受験していただきたいと考えております。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)既に会計年度であるとか臨時職員として働かれていた方が町の常勤職員として力を発揮されている、そういった現場私も見ております。ぜひこれからもそういったチームとしていろんな方が中之条町役場の仕事を支えていけるよう手立てを取っていただきたいということを要望してこちらの質問を終えたいと思います。
補聴器の購入補助について
次の質問に移ります。補聴器購入補助の実施について伺います。人と人とのコミュニケーションを円滑に行う上で補聴器の存在意義は本当に大きいと思います。補聴器を利用する本人にとってはもちろんですが、同居する家族やご近所や友人などあらゆる人との付き合いで聞こえの問題はトラブルになりがちです。声をかけたけれども、相手が聞こえなかったのか無視されたような気持ちになってしまった。細かい話ができなくて、気持ちのすれ違いや事実の誤認が生じてしまうなど、補聴器さえあれば防げるトラブルについて、私も相談を受けたことがあります。一度トラブルが生じてしまうと、自分の気持ちを表に出せない、人に会うのがおっくうになってしまう、そういったことで外出を控えがちになったり地域のコミュニティーに顔を出しづらくなってしまったりという実例を見聞きいたします。
ここで、伺います。聞こえの問題から来るトラブルを防ぎ、健康寿命を延伸するためにも補聴器の購入に対する補助を行うべきと考えますが、現状において障害者手帳の交付を受けて補聴器を購入された方の実績、それから手帳交付を受ける基準はどのようになっていますか。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)それでは、お答えをいたします。
補聴器の購入につきましては、聴覚または平衡機能に障害があるということで、身体障害者手帳を所持している方を対象に一部の方を除き、基準額の1割負担により購入していただいております。基準額の9割は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、補装具交付・修理事業において国2分の1、県4分の1、町4分の1の負担割合により支援しているところであります。令和5年度におきましては、24件が対象となり、そのうち21件が高度難聴対象者、3件が重度難聴対象者となっております。
障害者福祉法施行規則に基づく聴覚または平衡機能の障害を持つ方の身体障害者手帳の交付基準といたしましては、一番軽い状態の身体障害者手帳6級の障害程度として両耳の聴力レベルが70デシベル以上、または一側耳の聴力レベルが90デシベル以上で他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のものとなっており、おおむね40センチメートル離れて会話ができる程度となっております。聴力レベルにおいて、身体障害者手帳の2級から6級までに分類をされております。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)国、そして県、町、この補助の対象基準が「身体障害者手帳を所持している」ということでした。両耳の聴力レベルが70デシベルということですけれども、世界保健機構、WHOは71デシベル以上は重度の難聴ということで指定しています。WHOでは、41デシベル以上の中等度の難聴者に対して補聴器の装用が推奨されています。今全国各地、群馬県内でもおおよそ40デシベル以上を基準に自治体独自の補聴器購入補助制度が実施されています。中之条町では、独自の助成を検討されているでしょうか。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)当町の独自の助成を検討しているかというお尋ねでありますけれども、群馬県内におきましては、自治体によって多少の支給要件は違いますが、前橋市や太田市、渋川市などをはじめとして聴覚障害者による身体障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の方を対象とした独自の補聴器助成事業を実施している自治体がございます。現状では、補聴器購入に関する相談をいただいた際に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具交付・修理事業を案内し、活用をいただいておりますが、相談いただいた方が全員が身体障害者手帳の該当となり、補助制度を利用し、補聴器の購入ができている状況にあります。
町独自の事業として補聴器を交付する場合も対象とする方や条件など、どこかで線を引く必要があろうかと思います。いずれにいたしましても、近隣町村では行われていない事業であり、必要性等を今後も継続して研究をさせていただきたいと考えております。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)町が独自に助成を行うことが聞こえに不安を持つ方やその家族にとって補聴器利用の大きな後押しになると思います。障害者手帳の交付を受けるのは、心理的に負担が大きいという方もいらっしゃいます。近隣町村では行われていないという答弁でございましたけれども、隣の渋川市でも実施されておりますし、吾妻郡内で中之条町が先んじて助成を行えば他の町、村にも広がり、喜ばれる方が増えることと思います。ぜひ今後の実施に向けて前向きに検討いただくことをお願いいたしまして、この質問を終えます。
六合中学校の教育事務を長野原町に委託することについて
最後に、六合中学校の教育事務を長野原町に委託することについて、質問をいたします。3月の定例会議でこの問題、一般質問で取り上げましたが、その後3月25日に長野原町長に教育事務委託の申入れを行ったことが地元紙の一面で報道されました。
4月から新年度となり、今年度六合中学校に入学した生徒さんたちは、3年生に進級したタイミングで長野原中学校に通うことになると思います。このことについて、生徒や保護者、地域住民から町に寄せられている声はありますか。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)こども未来課長
○こども未来課長(山本伸一)現時点で生徒や保護者、地域住民から直接町や町教育委員会に寄せられている声はございません。しかし、六合中学校の教職員へ教育事務の委託に向けた方針を説明した際には、生徒数の推移からも委託に向けた方針は致し方ないと理解をいただいた一方で不安になっている生徒もいるので、そのことを受け止め、取り組んでもらいたいとのご意見をいただいております。
以上です。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)六合中学校の現場から生徒に対してのケアをしっかりやって欲しいという意見があったということだと思います。生徒さん達は、まさに当事者ですから、この事務委託によって通学する学校が変わることにいろんな危惧や心配をされていることと思います。ぜひしっかりと声を聞いてケアをしていただきたいと思います。
次に、このことについて行政区程度の規模で住民に対して説明をし、意見を聞く機会を設けるべきと考えますが、教育長、町長のお考えはいかがですか。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)教育長、お願いします。
〇教育長(山口暁夫)六合地区の中学校生徒の教育事務を長野原町に委託する方針につきましては、令和5年11月19日に六合地区の住民全員を対象とした説明会を実施しております。
また、令和6年2月6日に六合地区区長会の役員の方へ詳細に説明をし、2月20日には六合地区区長会の総会において区長の皆様に説明させていただいております。今後は、長野原町への教育事務の委託に向け、生徒や保護者の不安をできる限り小さくしていけるよう六合中学校と長野原中学校の交流や保護者及び学校との協議の場を設けることなどの取組に力を注ぎたいというふうに考えております。このことからご質問の行政区程度の規模での住民説明を開催することは、考えておりません。
以上でございます。
〇議長(安原賢一)町長、お願いします。
〇町長(外丸茂樹)私といたしましても、総合教育会議での協議を受け、長野原町への教育事務の委託に向けた方針を決めたわけでございます。六合地区の皆様に対しても今まで教育委員会においてしっかり説明をし、ご意見を伺う機会を設けてきたと考えております。六合地区区長会の総会においてご説明した際には、私も同席しておりましたが、区長の皆様から異論などの意見はございませんでした。今でも様々なお考えをお持ちの方がいらっしゃることは承知をいたしております。しかし、長年にわたって検討されてきたことであり、決断を先送りすると地域や保護者、子ども達の不安がもっと大きくなってしまうと思われます。このため、教育長の答弁にもございましたとおり今後は子ども達や保護者の不安を少しでも小さくできるよう取り組んでいくことが最優先と考えております。議会の皆様にもご理解とご協力を賜りまして、関係する皆様とともに検討を重ね、長野原町への教育事務の委託に向け、しっかりと取り組んでいきたいと考えております。
原沢議員におかれましても、今後も大所高所からご指導、ご協力をお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)これまで住民のみなさんですとか保護者のみなさん、そして区長会の総会等で説明してきたということは3月の定例会でも一般質問で伺い、私も理解をしております。しかしながら、今回3月の新聞報道を受けまして私地域の方からいろんな声伺っています。
まず、新聞報道を受けて初めてそんなことになっているということを知ったという方もいらっしゃいますし、これから六合中学校の生徒達は長野原中学校に行って長野原中学校の卒業証書をもらうんかいというようなことですとか、長野原町と中之条中学校では子育ての支援や就学支援など違う部分もあると思うけれども、どっちが対応になるのだいですとか、様々みなさんから話を伺っているのです。地域のみなさんやっぱり子どものこととても心配をされています。いざ長野原町に業務委託をすることになって地元のみなさんたちが具体的にこれからどういうことになるのかと、やっぱりいろいろと心配になってきているところだと思うのです。こういう具体的な疑問に対してぜひ直接の対話の機会をつくっていただきたいというのが私の質問の意図でございます。
町長が先ほど答弁で議会への理解と協力ということでお話しされましたけれども、私も議会の一員として町の施策がきちんと町民に理解されて行政も町民も一緒に進むべき方向を探して目指していく、そのために議員としてやれることをやっていきたい、こう思ってこの問題について度々質問をしています。行政の決定を受け、いろいろと疑問が出てくる。その声をきちんと聞いて行政としての考えを直接町民に伝えていく、そのことが外丸町長の目指す共創のまちづくりにつながることと思うのです。
私は、決定を批判しているわけでも変えて欲しいと求めているわけでもありません。3月議会で公開を求めました総合教育会議、令和5年度3回、令和6年度1回、議事録が公開されましたので、私もつぶさに確認いたしまして、この決定が町長や教育長をはじめ教育委員のみなさん本当に考え抜いて子ども達の未来を思って決定した、やっぱりそういう経緯、ちゃんと見ることができます。この町長や教育長の思いですとか決定された内容をやはり直接住民のみなさんにもお話をしていただきたい。そして、今回の六合中学校の教育事務を長野原町に委託し、そしてその後吾妻郡ではどのような教育環境をつくろうと考えているのか。そういったことをぜひ直接町民に教育長や町長の声で届けていただくことできないでしょうか。町民が疑問に思っていることに直接答える、そのような機会ぜひつくっていただきたいと思っています。行政区の単位とはいかなくても、この問題で地元の住民に説明をして意見を聞く場を設けることが私はやはり必要だと考えます。首長が直接住民と意見交流するタウンミーティング、そんな形で検討いただけませんでしょうか。町長、いかがでしょうか。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)先ほどの答弁でお答えしたのが主な内容でありますので、また教育委員会のほうでそういったことを精査することもあるかと思いますけれども、今の現時点では教育長の答弁を考えさせていただいて、いろいろな場面では今までも説明をしてきたわけでありますので、またそういう機会があることも考えられますけれども、今の時点ではそういうことについては教育委員会の考え方を尊重させていただきます。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)答弁いただきました。現状がやっぱり変わっているという状況だと思います。もう実際に受入れに向けて長野原町のほうも動いていることと思いますし、それを受けましてやはり子ども達、そして保護者、そして地域の住民のみなさんがいろいろとやはり不安を持ったり、これからどうなるのだろうという思いを持っているところだと思いますので、ぜひ教育委員会におかれましても、そのような子ども達の意見や地域住民のみなさんの意見を聞く場所をぜひ設けていただきたい、このことを重ねて要望いたしまして、私の一般質問を終わります。