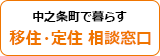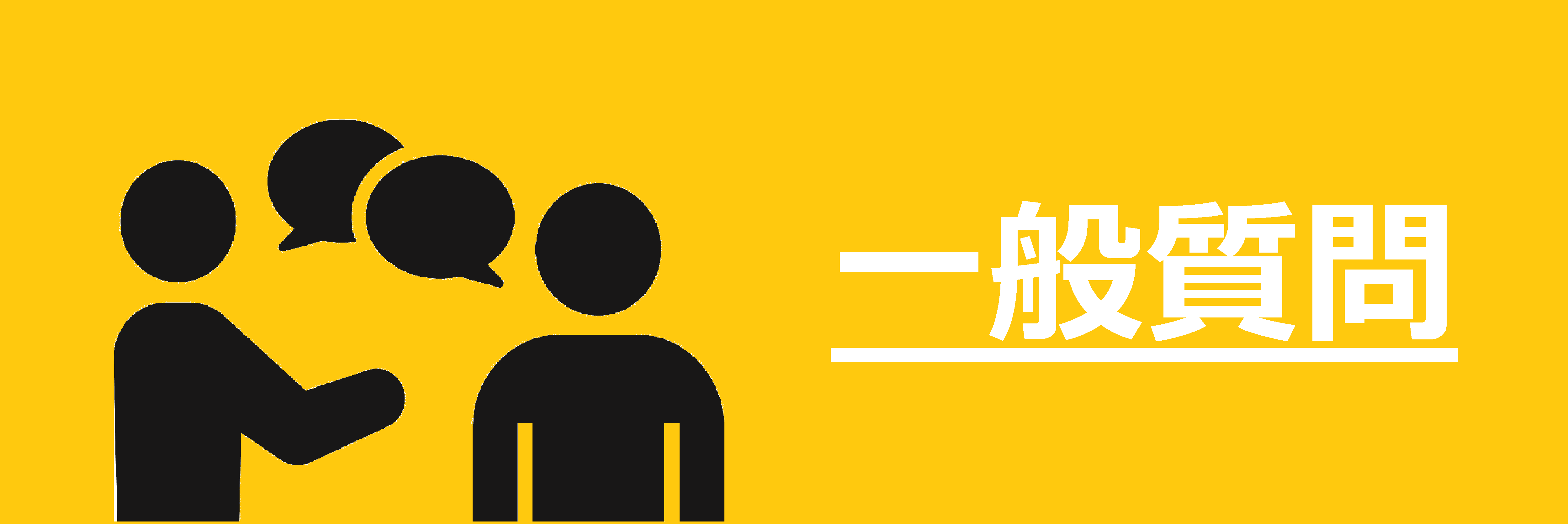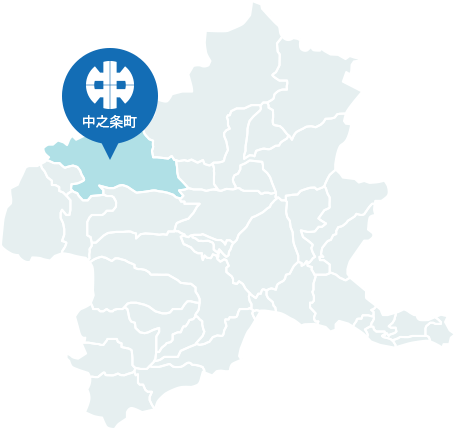本文
令和6年6月定例会議 一般質問(関美香議員)
02 7番 関美香議員 令和6年6月定例会議一般質問
〇7番(関 美香)議長よりお許しをいただきましたので、通告に従い、一般質問させていただきます。
質問の内容は、1、学童保育の充実について、2、災害への備えについて、3、熱中症対策についてです。よろしくお願いいたします。
学童保育の充実について
初めに、学童保育の充実について質問させていただきます。学童保育は、児童が放課後や長期休暇を安心安全に過ごす上で重要な役割を担っていると考えます。また、中之条町の保育所の利用状況から、共働き世帯が増加傾向にあり、学童保育は子育て支援においてその役割が今後ますます重要になってくると考えます。この観点から、学童保育の充実について伺っていきたいと思います。
まず初めに、学童保育の利用状況について確認をさせていただきたいと思います。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)それでは、関美香議員のご質問にお答えをさせていただきます。
学童保育の利用状況についてということでありますけれども、中之条町には学童保育所が中之条地区に民間で2か所、六合地区には公立で1か所ございます。現在待機児童もなく、希望する方の受入れはできている状況にあります。利用状況は、4月1日現在で民間のろばの子クラブが70人、学童保育所ひまわりが66人、公立の六合学童保育所が9人となっております。利用者の合計は、令和3年度が105人、令和4年度が111人、令和5年度が118人、令和6年度が145人と子どもの人数が減少傾向にありながらも学童保育の利用希望者は年々増加している状況にございます。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)学童保育の利用状況について確認をさせていただきました。その中で利用者数の推移でありますが、令和3年度から令和6年度において毎年利用者数が増加しており、答弁いただいたように子どもの人数は減少傾向でありますが、学童保育の利用希望者が増加していることからも、共働きで子育てをされている世帯が増加していることが分かります。
昨年同僚議員の学童保育についての質問の中で利用者から夏休み期間中預けたいとのご相談に対して、学童保育所では令和5年4月当初から利用者が多く、また職員が不足していることも重なり、長期休暇中のみの子どもさんを安全に受け入れることは困難と判断し、お断りをしたとの答弁がありましたが、今年度の長期休暇中の受入れについてお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)長期休暇中の希望者に対する今年度の受入れというお尋ねでありますけれども、今年度の長期休業中の受入れにつきましては、4月から利用希望者が昨年度と比較して123%と多く、職員間で事前にお子さんの状況を把握し、安全に受け入れるために可能な限り4月からの入所をお願いしているところであります。しかしながら、各家庭によって状況が異なるため、各学童保育所へ問合せをして相談していただくよう広報紙等でお知らせをしている状況でございます。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)今年度の長期休業中等の受入れについて確認させていただきました。その中で今年度の利用希望者が昨年度と比較して123%と増加が見られる状況、また昨年度において夏休み直前に夏休み中預けたいとの相談があったことからも、長期休暇中の利用希望者が一定数いらっしゃることが推察でき、今後の学童保育を考える上で長期休暇中の学童保育について検討が必要であると考えます。
時短勤務やパートタイムで働いている保護者からは、普段は子どもの下校に間に合うので、学童保育を利用していないが、長期休暇中は子どもの預け先がないので、学童保育を利用したいとのお声を伺っております。長期休暇中の学童保育を考える上で小学校での学童保育を検討していただきたいと思っております。
同僚議員から学童保育を小学校でできないかとの質問に対して、教育長からは学校や関係各所との十分な協議が必要であるとの答弁でありました。長期休暇中の学童保育を小学校で行う理由として、子どもの送迎についてはスクールバスを利用することで保護者の負担が軽減されると考えます。また、配置されている支援員さんに関わっていただくことにより教職員の負担についても軽減されると考えます。
以上の点から長期休暇中の学童保育を学校で行うことを検討していただきたいと思いますが、教育長の見解をお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)教育長
〇教育長(山口暁夫)学校を使った学童保育については、議員の質問にもあったとおり学校や関係各所との十分な協議が必要であると考えております。
本町においても、少子化により学校に空き教室が生まれてきており、管理方法や運営方法などをしっかりと検討、協議すれば実施は可能かと思われます。ただし、学童保育の運営にあたって安心安全は欠かせないことになります。そのためにも学童保育の支援員が子どもの特性を把握しておくことや子どもや保護者との信頼関係を築いていることは大切なことと思われます。このため、学校に配置している特別教育支援員などが長期休業中に関わるとしても、普段から学童保育を運営し、子ども達と関わりを持っている運営母体との連携が必要であると考えます。学校を使った放課後の居場所づくりに力を入れている千葉県千葉市などの事例では、市から委託を受けたNPOが運営を行っているようですので、中之条町でも民間の力を借りるなど方法は様々あると思われます。
いずれにせよ学校施設を使わせないといった考えは全くございませんので、学校を使った学童保育の設置に向けた方針が示されれば中之条町の子ども達にとってよりよい方向性となるよう関係各所と協議していきたいと考えております。
以上でございます。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)教育長から配置している特別教育支援員などが長期休暇中に関わるとしても、普段から学童保育を運営している母体との連携が必要であるとのお考えを示していただきました。また、学校施設を使わせないといった考えではなく、中之条町に子ども達にとってよりよい方向性となるよう関係各所と協議していきたいとのことでありますので、ここからは町長にお伺いしたいと思います。
国が推し進めた新・放課後子ども総合プラン及びそれを引き継ぐ放課後児童対策パッケージにおいて、学童保育と放課後子ども教室を一体的に学校施設を活用して行っていく事業が目標として掲げられております。その背景には、近年の女性就業率の向上によりさらなる共働き家庭の児童が見込まれ、子どもが保育園から小学校に上がることで仕事と子育ての両立が難しくなる小1の壁の打破と待機児童解消のためとされておりますが、子どもの居場所づくりを考える上でこの事業について町長の見解をお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)それでは、お答えをさせていただきます。
放課後の児童の居場所づくりとして学童保育や放課後子ども教室等を行っております。放課後子ども教室は、中之条町小学校の余裕教室を利用して地域の方々にサポーターとして参加していただき、子ども達の体験活動や地域住民との交流活動を行っております。現在は、それぞれが違う場所で連携を取りながらお子さんの安全を第一に考え、活動をしております。
学校施設を利用した学童保育の実施につきましては、現在民間の学童保育所2か所が運営しており、待機児童もいないことから新たに学童保育所を開設する予定はありません。新規開設の必要性が生じましたら、学校施設等での施設も視野に入れて検討してまいりたいと考えております。
今後も子ども達が放課後を安全安心に過ごせるように皆様からご要望等を伺いながら多様な居場所づくりを検討してまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)町長から子どもの居場所づくりにおいて、新規開設の必要性が生じたら学校施設等での設置も視野に入れ、検討していきたいとのお考えを示していただきました。
放課後児童対策パッケージの背景には、子どもが保育園から小学校に上がることで仕事と子育ての両立が難しくなる小1の壁の打破があるとされております。中之条町の学童保育利用において、先ほど申し上げたように時短勤務やパートタイムで働いているので、学童保育を普段は利用しないが、長期休暇中の預け先がなく、学童保育を利用したいとの現状があり、中之条町においても仕事と子育ての両立が難しくなる小1の壁の打破への取組が必要であると考えます。学童保育は、子育て支援において重要な役割を担っており、子育て支援に力を入れる中之条町だからこそ子育てと仕事が両立できるよう学童保育の充実を求めたいと思います。そして、子ども達が安心安全に過ごせる多様な居場所づくりを考える上で小学校を使った長期休暇中の学童保育の検討を要望させていただきます。
それでは次に、中之条町において比較的軽度の障害がある児童に対して、きめ細やかな教育を行う少人数のクラスが設置されていると認識をしておりますが、支援を必要とする児童の学童保育の利用状況について確認させていただきたいと思います。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)ただいまお尋ねの答弁をさせていただきます。
学童保育所において、保護者から申出があり、支援が必要なお子さんにつきましては、現在3名であります。お子さんの状況を確認して、各事業所において支援員を配置しているところでございます。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)支援を必要とする児童の学童保育の利用状況において、各事業所に支援員が配置され、実際保護者から申出のあった3名の利用があることを確認させていただきました。中之条小学校において、少人数のクラスで学ぶ児童が増加傾向であると伺っております。それに伴って今後学童保育の利用についても増加が予想されます。子どもさんが特別支援クラスで学んでいる保護者から、学童保育に対して利用人数が多いことや現在の職員数で手が回るのだろうかという懸念から、自分の子どもを見ていただくことに対して不安があるとのお声を伺っております。
以上の点から、支援が必要な児童に対する学童保育の今後の受入れについて町長の見解をお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)学童保育の今後の受入れというご質問でありますけれども、学童保育所の入所面談時においてお子さんの状況や親御さんの希望を確認した上で各事業所において可能な限り支援が必要なお子さんを受け入れております。福祉サービスの観点から、支援を必要とするお子さんや発達に特性のあるお子さんが利用する放課後等デイサービスといった通所支援サービスもございます。支援が必要なお子さんやご家庭のニーズに応えられるよう学童保育所はもとより、関係機関で連携を取り、安全に放課後を過ごせるようにしていきたいと思っております。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)各事業所で支援を必要とする児童を可能な限り受け入れていること、また福祉サービスの観点からの放課後等デイサービスの支援があり、支援が必要なお子さんや家庭のニーズに応えられるよう関係機関で連携を取っていくとの答弁をいただきました。支援を必要とする子どもさんの学童利用においては、繊細な部分があり、保護者が相談しやすい環境づくりが重要であると考えます。答弁にもあるように、学童保育所はもとより関係機関での連携が大切であると考えます。保護者がより相談しやすいきめ細やかな相談体制への取組とともに、支援を必要とする子どもさんが安心して学童保育を利用できるよう職員の確保についても、これは難しい部分あろうかと思いますが、重ねてお願い申し上げ、次の質問に移ります。
災害の備えについて
災害の備えについてお伺いいたします。令和元年10月に発生した台風19号は、群馬県内において4名の尊い命を奪い、吾妻郡内においては嬬恋村で国道144号線やJR吾妻線の寸断、河川の氾濫など大きな被害が発生し、中之条町においても大雨特別警報が発令され、生活道路や農地、家屋にも被害が及びました。令和元年12月定例会議の一般質問で台風19号への対応について質問をさせていただき、答弁として反省会を開催し、直ちに対応できるものについては改善がなされ、実施に時間を要するものやさらに協議が必要なもの、また予算を伴うものは優先順位を定めて進めていくとのことでありました。これから本格的な梅雨、そして台風シーズンを迎えるに当たり、台風19号の対応について改めて振り返り、災害への備えについて伺っていきたいと思います。
まず、避難所開設において各地区の避難所を早期に開設する必要があったとのことでしたが、刻一刻と変化する気象状況下での避難所開設の判断について、町長の見解をお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)関議員おっしゃるように、本当に毎年毎年異常気象が当たり前のような地球環境になってまいりました。日本もその中に巻き込まれているわけでありますけれども、災害への備え、これについては避難所開設の判断、お尋ねであります。地球温暖化の影響によりまして線状降水帯やゲリラ豪雨、台風の大型化など大雨災害が激しさを増している近年でありますが、関議員お尋ねの避難所開設の判断につきましては、台風などの進路や風雨の状況がある程度事前に予測できる場合には、避難をされる方の安全を考慮し、風雨の強まる前に避難所の開設を行い、避難を呼びかけてまいります。
また、ゲリラ豪雨等状況が急激に変化する場合には、状況にもよりますけれども、まずは中之条地区においては役場を、六合地区においては六合支所を自主避難所として開設をし、その後の状況を前橋気象台と連絡を取りながら各地区に避難所の開設を行ってまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)ゲリラ豪雨等状況が急激に変化する場合は、まず自主避難所を開設し、その後の状況を前橋気象台等と確認を行いながら各地区の避難所開設を行っていくと確認させていただきました。
令和元年の台風19号の際、身近な避難所の開設が遅かった、暗い中、そして大雨になってからの避難は困難であったとのお声について、令和元年12月定例会議の一般質問でお伺いしたところ、各地区において避難所を早期に開設する必要があったとの答弁をいただいていることからも、各地区の避難所開設は避難される方々の安全を考慮し、早めの判断をしていただくようお願いいたします。
台風19号の反省点として、避難所のうち名久田公民館においては停電が発生し、避難所が暗闇になってしまったこと、また和式トイレしかなく、膝の悪い方が利用できない状況であったと記憶しておりますが、地区ごとの避難所開設における停電への備えやトイレの整備状況について確認をさせていただきたいと思います。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)避難所の停電への備え、あるいはトイレの整備状況についてのお尋ねでありますけれども、避難所における停電への対応につきましては、指定緊急避難所や指定避難所として町所有の公共施設と地域の公民館等がございますが、役場、バイテック文化ホール、ツインプラザにつきましては、停電対策として自家発電装置を有しており、六合支所においてはポータブル発電機を常備しております。地域の公民館等の避難所につきましては、防災備品によるランタンを配備して停電対策を行っております。
また、避難所におけるトイレの整備でございますが、町所有の公共施設につきましては、既に洋式トイレへの改修が済んでおりますけれども、地域の公民館等につきましては、改修ができていないのが現状であります。そういった施設に対応すべく、令和元年における台風19号の反省を生かし、足腰の弱い高齢者の方等への配慮をし、和式トイレを洋式トイレとして使用できるポータブルタイプの便座を準備しているところでございます。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)地域の公民館等の避難所における停電対策は、防災備品のランタンを使用すること、またトイレの整備については和式トイレを洋式トイレとして使用できるポータブルタイプの便座を準備していること、確認させていただきました。避難所生活において、トイレの使いやすさは重要であると考えます。足腰の弱い高齢者が安心してトイレを使用できるよう準備を着実に進めていただきたいと思います。
また、地域の公民館等において、洋式トイレへの改修ができていない状況とのことでありますが、先ほども申し上げましたが、避難所生活においてトイレの使いやすさは重要であり、地域の公民館等のトイレの洋式化を進めるべきと考えます。ポータブル便座の準備を進めていただくとともに、避難所充実の観点から地域の公民館等のトイレの洋式化についての検討を要望いたします。
それでは次に、令和6年度当初予算において非常用電源としての活用を視野に入れたハイブリッド車の購入が予算計上されておりましたが、災害現場においてどのような活用を想定されているのかお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)ハイブリッド車の災害現場における活用についてのお尋ねでありますけれども、能登半島地震をはじめ昨今の全国的に度重なる災害を考えますと、いつ同様の災害が起きても不思議ではないほど、日本全土が災害列島化していると言わざるを得ません。そうした状況に置かれたときには、町の行政だけでは到底対応できるものではなく、他の自治体や企業、団体等と災害協定を締結し、また各地域においても有事に備えた避難計画や避難所訓練等のご協力をお願いしているところでございます。ニュース番組や新聞等を見ますと、そうした災害現場や避難所においてスマートフォン等による情報収集が不可欠なツールとなっておりますが、多くの場面でバッテリーの充電等に苦慮している現場を多く目にいたします。一例ではございますが、そうしたスマートフォンの充電等にも購入予定の車両が役立つのではないかと期待しているところでございます。しかしながら、購入した1台の車両で広範囲を網羅できるとは思いませんので、先ほど述べましたとおり町でも自動車関連企業とも災害時の連携の体制を整えておりますので、そういった企業とも協力することが不可欠であると考えております。
車両の購入につきましては、当初予算においてご議決をいただいており、現在購入に向けた作業を進めておりますけれども、半導体をはじめ車両の納期が延びている現状もありまして、年内の納車に向けて取り組んでおるところでございます。
以上です。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)いつどこで災害が起きても不思議ではないとのお考え、私も同感であります。だからこそ災害への備えが大切であり、答弁いただいたように行政だけではなく、企業や他の自治体との連携が災害に強い町づくりには必要であると考えます。
昨年5月に町と群馬トヨタは、公共交通や防災など9項目に関する包括連携協定を結ばれておりますので、答弁にもあるように災害時の電力供給への備えの協力体制を整えていただきたいと思います。
ハイブリッド車の購入については、年内の納車に向けて取り組んでいるとのことでありますので、非常用電源としての活用について、引き続き検討していただきたいと思います。
それでは次に、ペットとの同行避難についてお伺いいたします。平成25年に環境省から災害におけるペットの救護対策ガイドラインが示され、災害が起こったときに飼い主はペットと同行避難することが基本であるとされています。また、一方で他の避難者への迷惑にならないように努めなければならないともありますが、避難所においてペットとの同行避難の受入れ、またペットによる他の避難者への生活に及ぼす影響を最小限にするための対策についてお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)ペットと同行避難についてのお尋ねでありますけれども、平成23年3月11日の東日本大震災におきましては、緊急避難を余儀なくされたため、ペットが自宅に取り残されたり飼い主とはぐれ、放浪するケースが多数生じたようであります。
また、飼い主とペットがともに避難できた場合であっても、避難所において動物が苦手な人やアレルギーの方等、多くの避難者が共同生活を送るため、平成25年に環境省から災害におけるペットの救護対策ガイドラインが示されました。大切な家族の一員として災害発生時に飼い主がペットを同行し、避難場所まで安全に避難することとなっており、中之条町では指定避難所のイサマムラと六合支所をペット同行避難所に指定しております。また、ガイドラインにはペットによる他の避難者に及ぼす影響を最小限にするよう記載されておりますので、人とペットは別々の空間になるように配置をしております。具体的に申し上げますと、イサマムラでは避難をされた方は校舎に、ペットにつきましては体育館に避難していただき、六合支所につきましてはペットを車庫にとしており、他の避難者に影響ないよう配慮しているところでございます。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)災害発生時に飼い主がペットを同行し、避難所まで安全に避難することとのガイドラインに従い、指定避難所のイサマムラと六合支所をペット同行避難所として指定されていることを確認させていただきました。
1点、関連で質問させていただきたいのですが、ペットの同行避難所においてハザードマップや町のホームページに掲載がされておりませんが、周知に対するお考えをお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)町のホームページに掲載をし、また町広報紙等により周知をさせていただきたいと考えております。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)ペットとの同行避難所について、町のホームページに掲載し、広報紙での周知を考えているとのことでありますので、ペットの同行避難についての周知徹底をよろしくお願いいたします。
また、他の避難者への配慮として、避難所においては人とペットは別々の空間で過ごすことについても町のホームページや広報紙に掲載していただくよう重ねてお願いいたします。
それでは、災害の備えについて、最後の質問になります。いつ起こるか分からない、そして激甚化している災害への備えとして、町民に対する防災意識啓発への取組が重要であると考えますが、町が行っている防災意識啓発の取組と今後の課題について、町長の見解をお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)防災意識啓発についてのお尋ねでございます。
6月の広報でもお知らせをさせていただきましたけれども、令和5年度の取組事例といたしましては、行政区における地区防災訓練、避難所体験を16回、保健環境課が各地区で行っております「健康づくりさろん」や社会福祉協議会で行っております協議体等での防災講話を計30回実施をさせていただきました。さらに、令和5年度当初9地区でありました自主避難計画の策定につきましては、39地区となっております。しかしながら、防災訓練や防災講話、自主避難計画策定過程での座談会におきましても説明しておりますが、近年の激甚化する災害を踏まえて「自らの命は自らが守る」意識を持って自らの判断で避難行動を取り、住民主体の取組強化による防災意識の向上を図ることが重要であると考えております。
今後も引き続き行政区での防災訓練や防災講話、自主避難計画の策定支援を行い、地域コミュニティーの向上、防災意識の啓発に取り組んでまいります。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)町長がおっしゃるように、近年の激甚化する災害を踏まえ、「自分の命は自分が守る」という意識を持ち、自らの判断での避難行動や住民主体の防災への取組の強化が重要であると考えます。そのためには、地域での防災訓練や避難所体験を定期的に行っていくことが大切であると私は考えます。定期的に防災訓練等を行うことで防災意識の向上が図られ、地域コミュニティーの充実にもつながると思います。そして、行政と地域が連携し、知恵を出し合い、ともに行動していくことが災害に強いまちづくりへつながっていくと考えますので、防災を各とした地域コミュニティーづくりの取組をお願い申し上げ、次の質問に移ります。
熱中症対策について
熱中症対策についてお伺いいたします。近年の気候変動の影響により、国内の熱中症による救急搬送者は毎年数万人を超え、死亡者数も高い水準で推移している状況であり、中之条町においても下四万地区において農作業中の高齢者が亡くなったことを記憶しております。国において、令和3年度から環境省と気象庁が共同して熱中症警戒アラートの運用が始まり、令和6年4月より熱中症警戒アラートに加え、気温が著しく高くなり、熱中症により健康に対する重大な被害が生じるおそれのある場合に新たに熱中症特別警戒アラートの運用が開始されたことからも、熱中症の被害を防ぐため、中之条町においても熱中症対策をさらに充実させるべきと考え、この点について質問をさせていただきます。
まず初めに、中之条町では熱中症対策においてどのような取組を行っているのかお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)昨年は、地球が沸騰していると言われるぐらいの異常な暑さを我々経験したわけでありますけれども、近年の気候変動の影響によりまして、国内の熱中症による救急搬送者が増えているということは承知をいたしております。熱中症対策といたしましては、高齢者の熱中症対策としてエアコンの購入に対する補助を行っております。また、議員がおっしゃいます熱中症警戒アラートや熱中症特別警戒アラートにつきまして、気象庁から情報が届きました際には防災安全課が防災無線とメールにより町民への情報を提供させていただいているところでございます。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)町が行っている熱中症対策、確認させていただきました。町民への熱中症の注意喚起を防災無線とメールを使った情報発信についてですが、テレビ等で熱中症の注意喚起されておりますが、呼びかけはより多いほうが有効であると考えますので、町民のみなさんを熱中症の危険から守るため、引き続きの取組をお願いいたします。
また、令和4年度から開始された高齢者世帯エアコン購入費補助金については、75歳以上の独り暮らしの方と高齢者のみの世帯を熱中症の危険から守る制度であります。冒頭申し上げましたが、下四万地区で農作業中の高齢者の方が熱中症で亡くなっておることからも、高齢者を熱中症の危険が守るべきと常々考えております。中之条町は、この制度を県内で先駆けて開始していただき、大変ありがたく思っております。
そこで、高齢者世帯エアコン購入費補助金の利用状況について、改めて確認させていただきたいと思います。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)高齢者世帯へのエアコン購入費補助の利用状況につきましては、初年度の令和4年度が21件で99万7,300円、令和5年度は同じく21件で105万円の補助金支給実績となっております。今年度も20件の利用があるものと見込んで予算化させていただいておりますけれども、5月末現在の実績は1件5万円となっております。
以上です。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)令和4年度が21件、令和5年度においても同じく21件の利用があったということで、高齢者世帯を熱中症の危険から守るための取組が着実に進んでいること、確認させていただきました。
昨年9月定例会議において、同僚議員からエアコン購入費補助拡充についての質問がありました。先ほども申し上げましたが、気候変動の影響により熱中症の被害は命の危険を伴う状況であることから、中之条町においても熱中症対策のさらなる充実が必要であり、74歳以下の低所得世帯に対するエアコン購入費補助を検討していただきたいと考えております。その理由として、長引く物価高騰による経済的な負担は低所得世帯に対して大きな影響があり、エアコンは高額な商品であるために購入を控えてしまうことが考えられます。また、エアコンを使い、室内の温度を適切に保つことが熱中症対策において大変有効であることから、74歳以下の低所得世帯へのエアコン購入費補助の検討が必要であると考えますが、町長の見解をお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)それでは、お答えをさせていただきます。
現在補助を実施しております高齢者世帯のエアコン購入費補助につきましては、75歳以上の独居老人か75歳以上の高齢者のみ世帯であることと町民税非課税世帯であることを要件といたしております。これは、エアコンは家電製品であり、基本的には購入した方の個人的な財産となるものでございますので、本来補助の対象となりにくいものでございます。しかしながら、本町では補助金の交付要綱の趣旨にあるように、家族などの支援が得られづらく、エアコンの購入が家計を大きく圧迫してしまい、エアコンを購入する機会を逃してしまった高齢者が劣悪な環境下に置かれ、命の危険にさらされてしまうような事項を未然に防ぐために実施しているものでございます。補助対象世帯の拡充につきましては、今後の補助金の申請状況や町民の皆様のご意見などを伺いながら、併せて県内の様子なども確認した上で必要に応じて検討させていただきたいと考えております。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)答弁いただいたように、エアコンは購入した方の個人的な財産であり、本来補助の対象になりにくいものでありますが、中之条町では75歳以上の独り暮らしと高齢者のみの町民税非課税世帯を熱中症から守るため、エアコンの購入費補助を実施していただいていることから、町民に寄り添った町政運営の姿勢が伝わってまいります。今後の状況を見てこれから補助について検討していくとのことでありますが、物価高騰、本当にこれ長らく続きそうな予想がされております。本当に経済的な負担の影響は、未だ先の見えない状況であることからも、74歳以下で例えばひとり親家庭や子育て世代の低所得世帯を対象としたエアコン購入費補助金の検討を要望いたします。
また、高齢者世帯エアコン購入費補助金は、75歳以上の高齢者のみの世帯を対象とした制度であることから、エアコンの使用を補うことへの検討が必要であると考えます。その理由として、室内にエアコンが設置されているのにもかかわらず、エアコンを使用せず、高齢者が熱中症で亡くなるケースを報道で見聞きしております。実際我が家の父もエアコンを使わず、暑い部屋の中にいるといった状況があり、家族が同居していれば対応できますが、高齢者のみの世帯においてはエアコンが設置されていても適切に使えないリスクがあり、その対策が必要であると考えます。高齢者のみの生活を支えるグッズとして、スマートリモコンがあります。家電製品のリモコンをまとめて管理し、スマートフォンで遠隔操作できる機器がスマートリモコンです。高齢者のみの世帯において、家族がエアコンを遠隔操作し、エアコンの使用を補うことが必要であると考えます。以上のことから、高齢者世帯エアコン購入費補助におけるエアコン使用を補うことに対する町長の見解をお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)それでは、お尋ねにお答えをさせていただきます。
現在町からの支援メニューとしては、議員おっしゃる支援はございません。しかし、高齢者の見守りや安全安心な生活を送ることは非常に大切なことだと思っております。こうした支援は、高齢者のみならず、町民の安心安全な生活を支援していることであろうと考えておりますので、役場の様々な部署でこうしたスマート機器やデジタル技術の活用によって可能となる支援につきまして情報を収集いたしまして検討をしてまいりたいと考えております。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)高齢者の見守りや安心安全な生活を支えることは、非常に大切なことであるとの答弁をいただきました。エアコン購入の支援とともに、高齢者を熱中症の危険から守るためには、エアコンの使用を補う視点も大切であると私は考えます。高齢化が進む中之条町において、高齢者の安心安全な生活を支援するためのデジタル技術の活用について情報を収集していただき、その中で高齢者を熱中症から守るため、エアコン使用のサポート機器、スマートリモコンの活用についても検討していただきたいと考えます。
最後になりますが、町民のみなさんを熱中症の危険から守るための対策の充実をお願い申し上げ、私の一般質問を終了いたします。ありがとうございました。