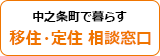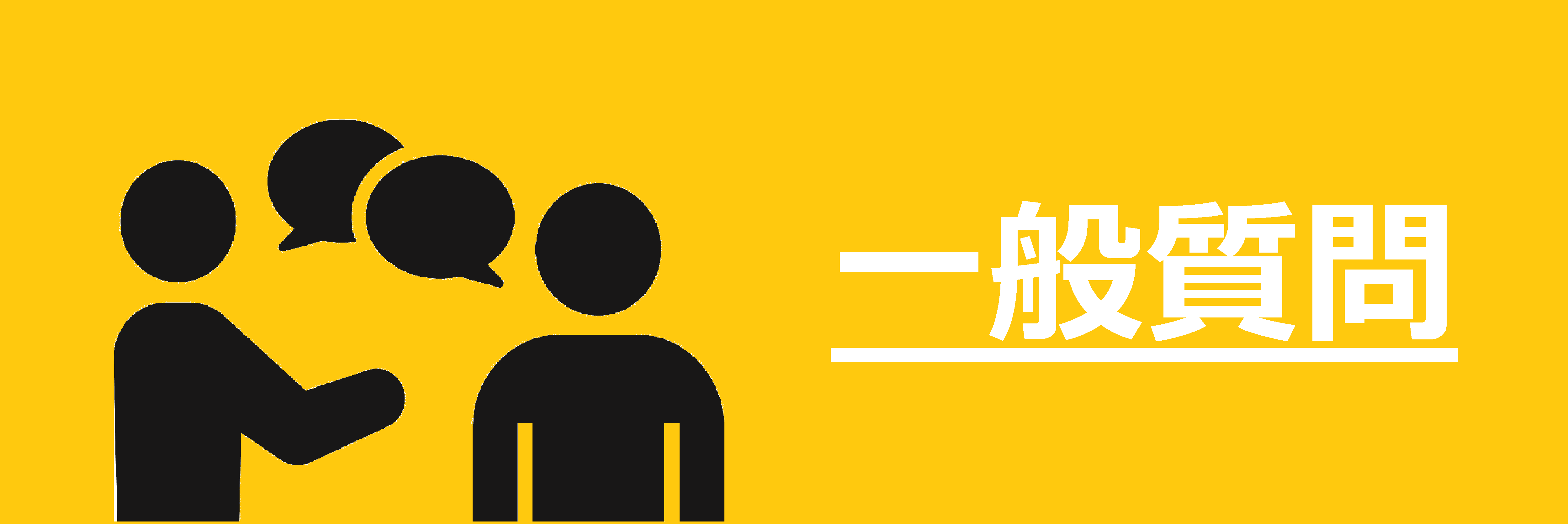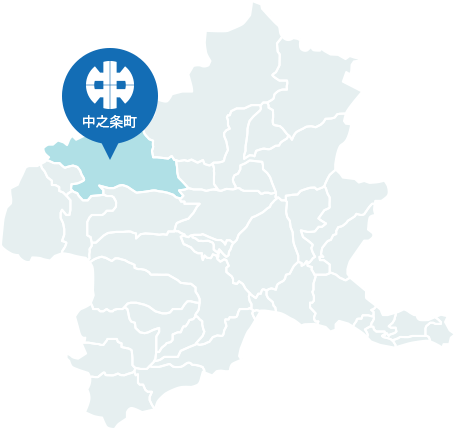本文
令和6年6月定例会議 一般質問(山田みどり議員)
01 5番 山田みどり議員 令和6年6月定例会議一般質問
〇5番(山田みどり)みなさん、おはようございます。通告に従いまして、6月定例議会一般質問を行いたいと思います。
私が質問するのは、1つ目、持続可能な農業への取組、2つ目、町営住宅について、3つ目、自治法改正についての3点を質問いたします。
持続可能な農業への取り組みについて
昨日の議会終わりに通っていましたら、小学生がどろんこになりながら田植えをしている姿を拝見しました。どの子ども達も一生懸命足を取られながらも本当に楽しそうに取り組んでいる姿を拝見させていただきました。こうした体験ができるというのが中之条町の魅力だと感じました。
今農業を取り巻く環境は、大きく変わっています。担い手の不足、市場の変化、輸入品など複合的な原因は多々ありますが、打開のための一手とは何だろうか。この質問をつくりながら考えました。幾つかの本を読みながら、東京工業大学教授の真田純子氏の著書の中に「なぜ中山間地の人ばかり頑張らねばならないのか」という言葉がありました。今の国が行っている農業支援は、地域の農業を本質的には守れていません。中山間地では、地域を維持していくためになぜこれほど苦労を強いらなければならないのか。人が減っている、若い人がいない、山や畑が守れない、こうした課題になぜ当事者の我々が責任を感じなければならないのか。このような農村になったのは、国が進めてきた農業振興が明らかに間違っているということです。中山間地域等直接支払交付金とか多面的機能支払交付金など様々な交付金があり、農業支援は行われていますけれども、しかしこれが今の農業問題の解消にはつながっていないと思います。つまり、国が進めていくことにただ従っていても我々に明るい未来はないということです。今まさに必要なのは、町独自の支援を一緒に議論していくことが大事だと思います。
まず最初に、この物価高騰によりどの業種にも影響出ていますが、農業というのは作物ができるまでに苗から肥料、収穫までに多くのコストがかかっています。農家には、厳しい状況が未だ続いています。農業の持続的な支援が必要となりますが、今現在具体的な農業支援は何をしているかお答えください。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)それでは、山田みどり議員のご質問にお答えさせていただきます。
昨日のみらい米プロジェクト、昨年実施をしていただいたようでありますけれども、今年は小学生にまた参加していただきながら農業体験をしていただくということで、本当に意義のある事業だと思います。山田議員と共々、私もそういったことについては支援をしていきたいと、このように考えております。
それでは、昨今の情勢によります農業を取り巻く肥料や資材等の価格高騰は、全ての農家が直面しており、大きな課題となっております。中之条町におきましても、令和4年度に全ての販売農家を支援するために町単独事業として農業資材等価格高騰対策補助事業を立ち上げまして、対象106名、合計893万8,000円の支援をしてまいりました。今後の支援策につきましては、社会情勢を見ながら支援が必要との判断となれば、再度検討してまいりたい、このように考えております。
また、議員おっしゃる担い手不足等については、農業分野の労働力不足ということになりますが、大規模な農家であればIT化による効率化を図るスマート農業や大型機械の導入、技能実習生の活用等の検討が考えられます。しかしながら、中之条町は1経営体当たりの経営面積が小さいため、労働力不足を補うための機械の導入はハードルが高くなります。特に水田の耕作につきましては、農業従事者の高齢化に伴い、難しくなることが想定をされます。そこで、町では水稲農作業の受委託についてコーディネートを行っております。地区ごとに担い手が円滑に作業を受託できるよう調整を行いまして、耕作希望者が耕作できるように取り組んでいるところでございます。
〇議長(安原賢一)5番、山田さん
〇5番(山田みどり)物価高騰による農業資材の支援ですとか補助事業というのは、非常にやっぱり効果があったのかなと。非常に支給もこれだけあるということで、それだけの一定の評価ができているのかなと思うのですけれども、今のこの現状が続いている中ではやはり農業への支援というのは引き続き検討していっていただきたいなというふうに思います。物価高騰がまだまだ今後続くこともありますし、また先ほどやっぱり委託をして水田を守るような形で農業が続けられない、高齢になってできないという方に対してもこういった取組をしていますけれども、それをさらに広げていきながら活用をしていっていただくということが耕作放棄地ですとか、そういったことの対応にできるのかなというふうに思いますので、引き続き資材の支援とか補助とかというのを検討していただきたいと思うのですけれども、今のところ今後予定としてそういった支援を検討しているのかどうかちょっとお聞きします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)答弁させていただきました昨年の農業の肥料、農薬、資材、この上げ率、極端に昨年は影響されました。多少、今年度というのですか、今年に入ってから肥料なんかも若干下がってきたり、いろいろこの状況が影響が少しずつ変わってきたのかなと思いますけれども、いずれにしても物価高騰は農業の生産性に極めて妨げになっているということは私も承知しております。こういった状況の中でもう少しJA、それから農業をされている方々との情報を共有しながら今後対策を考えるときがあれば考えていきたいと、このように思っております。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)5番、山田さん
〇5番(山田みどり)コストがかかって、本当に作物ができるまでにものすごくお金がかかっていても、なかなか商品に思い切り添加できないというような状況もあると思うので、ぜひこういった支援が持続的に行っていただけるといいなというふうに思います。ぜひ農家のみなさんの声を聞きながら検討していただければと思います。
支援の中で1つ、農家の方から以前ぜひやってもらえないかなということで質問されたことがありまして、生分解性マルチ、マルチはみなさん農業の方よく使われていると思うのですけれども、生分解性マルチの購入の補助を結構進めている、隣の町もそうですけれども、自治体があります。廃プラスチックの問題もあって環境に配慮した生分解性を農林水産省でも推奨していますけれども、生分解性って本当に1年ぐらいですぐに劣化してしまって破けてしまったりだとかあまり状態がきちんと保てないというのがあって、なかなか使いづらいというのが、そういう声を聞きます。そういう事でなかなか町内でも積極的に使っておられる方というのは少ないというふうに、現状であるということを聞いています。しかしながら、環境のことを配慮した場合にこういったプラスチックを片付ける手間ですとか、それを廃棄処分するということも考えると、生分解性に切り替えてもらうような、働きかける施策というか、購入補助などもぜひ検討していただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)生分解性マルチ、最近そういうお話をよく聞きますけれども、私も実は農業者でしたから、生分解性マルチは2、3年使用させてもらった、その経験もまた後ほどちょっとお話をさせていただきます。
生分解性のマルチ普及を目的として購入補助を行っている自治体があります。中之条町においては、現在のところ購入補助等は行っておりませんけれども、生分解性マルチは自然に配慮した農業資材として注目をされておりますが、通常使われておるポリマルチ樹脂のマルチ等よりは販売価格が割高となっております。生分解性マルチの場合、使い古したマルチは自然に分解するので、畑にすき込んでしまえば処分でき、地面から剥がす手間がありません。また、ポリエチレン樹脂のマルチ等のように処分費用がかからないため、町内で利用している農家もあるようでございます。しかしながら、生分解性マルチは栽培中に分解してしまうというようなこともありまして、栽培期間が長い作目には不都合なことがあるため、全ての作目に使えるとは限っておりません。また、分解する途中に強い風が吹くと破片が飛んでしまう、こういったことがありまして、配慮が必要な場合もございます。プラスチック排出を抑制し、持続的農業の推進をするために生分解性マルチを使用することは有用なことではありますけれども、使用者が限定的であり、費用面や使用目的等において課題もありますので、町としては作目に応じた使用等、今後研究してまいりたいと考えております。
私も野菜を作るのに3年ぐらい生分解性マルチを使っていました。山田議員おっしゃるように土に混ぜると分解してしまうということですので、ただ使用勝手が性質上使用しているときに裂けてしまったりとか耐久性の面からいくと、なかなか使い勝手の悪いという面もあります。掘ると確かに土に混じって分解するのですけれども、全部が全部きれいに掘らないと、先ほど申し上げましたように風であちこち飛んでいってしまうというようなことも実際私も体験をしていましたけれども、ただ環境に優しいというのは、今の農業は環境に優しい農業、これをやっぱり農業者は目指していますので、これは非常に必要なことかなと、こんなふうに思いますけれども、ちなみに私調べさせてもらいましたら、生分解性マルチ、JAのほうに問い合わせると黒の95センチ幅の200メートル、これが9,160円であります。通常のポリマルチはといいますと95センチ、200メートルが2,260円、この差が6,900円ございまして、なかなか小さい農家には難しいかなという面もあります。この差が4倍ということでありますので、確かに環境に優しい農業を進める上においてはこういったものをこれから考えていかなければならないということは重々承知をしておるのですけれども、先ほど申し上げましたように中之条町の農業の経営体がやはり小さいものですから、そのへんも含めながら、ただこれから恐らく農業関係も含めていろんな品質が改善されることがあると思います。そういうものをやはり注意しながら私どもも導入ができるものであれば考えていかなければならないと、そういったときにはまた山田議員からもいろいろご指導いただければと、このように考えております。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)5番、山田さん
〇5番(山田みどり)町長の答弁のように、本当に金額がこんなに違うのです。なかなか、では使おうかというふうにならない。本当にこれだけ違えばちょっと購入するのには、うんと検討される方が多いと思うのです。こういう状況なので、なおさらに購入補助が必要なのではないかなというふうに思うのですけれども、ちょっとこのマルチを廃棄処分するにあたっての処分費というのは、数字がもしあればどのぐらいの金額で処分して、今たぶん産廃で出すとして、どこかの事業者さんが、JAとか、農協がたぶん取りまとめて事業者さんに対して持っていって処分しているような状況だと思うのですけれども、廃棄処分の処分費についてはどのぐらいかかるのか教えてください。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)町で廃ビニール、廃ポリの補助ということで、協議会がございまして、JAで年に暮れに1回だと思うのですが、ポリマルチはことによると年2回あるかもしれませんけれども、1回は必ずあります。そこのところへ廃ビニール、廃ポリ合わせて、どちらもそうなのですが、13円の補助を役場としてはJAのほうにというか、協議会のほうへお支払いをして、あとは生産者の方の負担だとかJAのほうの補助とかいろいろ合わせるのですけれども、総額的なものはちょっと分からないのですが、町としては13円を補助させていただいております。予算的には、議案書にもあると思うのですが、廃ビニールについては2万5,000キロ、ポリが2万キロ、13円ですので、掛けますと60万5,000円を廃ポリ協議会のほうへ町として支出をさせていただいております。あとは、そちらで運用しながら利用者からも負担金をもらって処理しているのだと思いますけれども、全体に幾らかかるかちょっと数字捉えていないのですけれども、町の支出はそういうことになっております。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)5番、山田さん
〇5番(山田みどり)捨てるにしてもこれだけ金額が、まとめてですけれども、かかってきていて、プラスチックの処分というのが、調べますと焼却、埋立て、もしくは海外へ輸出して処分を行っているそうなのです。ただ、中国に輸出して中国側は輸入してそれを処分していたのが、中国が輸入を禁止したがために国内で処分しなければいけないということで、国内での処分、埋立てだとかそういったことで結構逼迫していることもあって、今後処分費というのも今後高くなるのではないかというふうに想定されます。こういった状況から鑑みても、本当に環境にはなかなか優しくない状況なので、生分解性の切り替えっていうのの後押しになるような支援、町長はやっぱり成分的なものもなかなか今もうちょっと開発してもらって、もうちょっと使いいいような形に商品が変わっていけばもうちょっと使用ももうちょっと促せるのだろうと思うけれどもとおっしゃっていましたけれども、そういうことも含めて今後ぜひ生分解性の切り替えの後押しになるような支援を検討していただければというふうに思いまして、求めまして、次の質問に移りたいと思います。
持続的に農家を支援するということは何だろうかというふうに考えた場合に、生産した野菜を積極的に消費してもらうということ、地元野菜を地産地消、この地で、中之条町で消費してもらうということを積極的に進めることがまず大事だなというふうに考えます。そこで、地元野菜を町内の学校や施設、様々なところで使用していただくということはいかがでしょうか。今現在地産地消の取組というのは、どんなことをやっているかお答えください。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)地産地消の支援は、どのようなことかというお尋ねでありますけれども、中之条町におきましては農産物の品質の向上による農産物のブランド化に取り組んでいるところでございます。そうした取組の一方で出荷数量がまとまらないことや出荷規格に合わない農産物が生産されてしまう、こういう現実もございます。このような農産物の味に遜色ないものは道の駅や直売所等において生鮮野菜として販売するほか、加工原料として活用することは単にもったいないからという理由だけではなく、農家経営の安定を支援することとなると思っております。地元農産物をなかのじょうマルシェやりんご祭り等のイベントで地元産の花、りんご、米等の販売を行っており、嵩山の麓のそば処けやきでは、中之条産のそば粉を使用させていただきまして、天ぷらとして提供する野菜の一部は地場産のものでございます。近所から新鮮な農産物を得ることができ、生産者と消費者が身近に感じられ、例えば六合地区の入山きゅうりや花いんげんのような伝統的な農産物を知り、農業への関心を深めることになります。地元の農産物を食べてそのおいしさを知っていただくことは、すばらしいことでありますので、今後とも活用することにできればと考えていきたいと思います。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)5番、山田さん
〇5番(山田みどり)イベントなどで、なかのじょうマルシェだとかりんご祭りとか、こういったイベントでかなり地元野菜が見られて多くの方が喜んで買っていっていただくという姿を見て、生産者のほうもそういった作った野菜をそういうふうにみなさんに買っていただくというのは非常に喜びだと思うのですけれども、ぜひこの企画ではなくて、常にやっぱり野菜が常にちゃんとお店に並んで常に買えるような状況だとか仕組みとかというのももっと作っていって地元野菜の消費につなげていっていただきたいと思うのですけれども、ただ販売というのはなかなか売れるときもあれば売れないときもあったりっていって安定的ではないです。安定的に消費していただくという意味では、学校給食だとか施設などに提供していくことがいいのかなというふうに思いますので、これはちょっと文教のほうになってしまうので、あまりあれですけれども、これはでも仕組みとしては農林課が主体となって幾つかの農家さんが集まって供給する枠組みを作っていただいて、ぜひなかなか役場だけではできないところを民間も一緒になりながら官民で一体でこういった取組を、枠組みをつくっていくということが地産地消の大きな後押しになるのかなというふうに思いますので、ぜひ検討していっていただきたいなというふうに思います。今は、でも給食にはたぶん地元野菜も使われて、特別な日なのかな、誰々さんちの野菜ということで使われていると思うのですけれども、それが常に使われるといいなというふうに思います。
町長が農業を守っていく上では、観光農業としてのということも推進していくということでおっしゃっていましたけれども、中之条町だからできること、強みを生かした事業展開ができないかということで、今例えばアグリツーリズム、農業体験をしながら宿泊をしてもらうということが大きく町の6次産業の発展にも、後押しにもなるのではないかなというふうに考えます。今現在では、農家民泊ができるような施設とかはないのですけれども、今後空き家だとか利活用にもつながりますし、また耕作放棄地の解消にもつながって、そういった活用につながっていくと思います。そういった体験がやっぱりどうしてもしたいというふうに、農家体験やったりとか田舎の暮らしに憧れてとか、なかなか移住はちょっとできないけれども、そういう農家体験みたいなのをしたいという声は結構聞くのです。そういった農家民泊みたいなことが、もしそういった施設があればかなりそういった声があるので、需要があるのかなというふうに感じますので、今後のぜひ施策としてやって、事業として検討していただければなと思うのです。
また、今Nコネクトが行っている子ども向けの収穫体験だとか、こういったことも始まっていますけれども、体験を通して土に触れるということは本当に子ども時代に土に触れるというのはすごく本当に大きなことを学べて五感でもいろいろ感じていい機会だなというふうに感じています。ガーデンズにおいてもすばらしいガーデナーがいて、花を育てるためのこういった講習会なんかもぜひ検討していただければと思うのです。こういういろいろな様々な体験ができるということが中之条の強みですので、地域の農業存続のためには様々なあらゆることをまずみんなで考えて実践してみる、やってみるというのが私は今後の農業存続のためには大きな力になるのかなというふうに思いますので、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。町長、いかがでしょうか。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)おっしゃるように、今までの農業、昔の農業と違いまして、今はもう農業と観光というものを引きつけたり、農業と、それから体験だとか都会の方と農業交流をするというのは非常に大切だと思います。今農家の方も非常にそういうところに目を向けていまして、Nコネクトももちろんそうなのですけれども、米づくり研究会なんかもやはり昨日のみらい米のプロジェクトには大きな支援をいただいておりますし、例えば米のコンクールをした後の金賞米などをPRしながら伊勢神宮へ奉納するとかいろいろなPR活動して、農業に対するみなさんの目をこちらへ向けていただこうという、農業者自身がそういう取組をしておりますので、今山田議員おっしゃるようにこれからやっぱり農業も観光も含めて農業にもう一度目を向けてもらう、地産地消してもらう、一番心配されるのがこれからどんどん農業者数が減っていくということになりますと、中之条町全体の面積は439.3キロ平方メートルありまして、群馬県で4番目に広いってちょくちょく言うのですけれども、そのところを維持していく上において農地が荒れてきますとやはり安心安全のまちづくり、そういったことにも影響するということもありますので、農業というのは地域の環境保全、これにも非常に大きな役割を果たしておるということがありますので、やはり農業をもう一度しっかり見直して、人口減少が進んでも中之条町に住んでいて安心安全で、そしておいしい食材を食べられる、そして中之条町で体験をすれば中之条町でおいしい米や野菜を食べられると、そういったものをPRするということも非常に大切だと思っておりますので、これからもいろいろ情報共有しながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)5番、山田さん
〇5番(山田みどり)人口が減る中では、本当に厳しい状況にありますし、農業人口も本当に減っている中でどうやって町の景観を維持していくか、この風景を維持していくかというのは非常に課題だと思います。みんなが知恵を出し合ってやっていくということで、本当にこの環境を守っていく、景色を守っていくということが我々の責任かなというふうに思いますので、ぜひみなさんと力を合わせてやっていきたいというふうに思います。
町営住宅について
次の質問に移りたいと思います。町営住宅の入居の際の保証人を立てるというのが今原則となっています。町営住宅には、住む際には中之条町町営住宅管理条例10条3項では、保証人の連署が必要であるが、町長の特例で保証人を必要としなくてもよいと明記していますが、どの条件の場合にそういったことが適用されるのか質問したいと思います。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)保証人を必要としないという要件についてというお尋ねでありますけれども、保証人を不要とする適用条件につきましては、町営住宅への入居におきましては保証人の選任を必要としておりますけれども、ご自宅の火災や自然災害等により住居が被災した場合等の被災者につきましては、町営住宅入居申請書類に保証人の選任は不要としております。
被災者の入居に際しましては、入居時から1年間は住宅使用料を全額免除いたしております。1年を経過してその後、継続して入居の希望がある方におきましては、申し出た場合はその時点で保証人を選任していただくことになりますし、住宅使用料も発生するということになります。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)5番、山田さん
〇5番(山田みどり)もちろん被災者の方の支援のためには、もちろん保証人を明記しないというのは当然なのですけれども、今家族環境の変化によって身寄りがない方がいらっしゃったりだとか外国籍の方とか、多様な状況があると思うのです。国交省の指針では、平成30年に保証人の規定を削除していることや公営住宅というのは住宅セーフティーネットとしての役割もあることから、条例の保証人についての明記を変更するべきではないかというふうに考えますけれども、町が今進めている移住促進にもこういったことはつながっていくことになると思いますので、ぜひ検討をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)そういった側面もあると思いますので、今後研究をさせていただいて担当課のほうで少し調べさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)5番、山田さん
〇5番(山田みどり)ぜひそのへんのところも保証人の問題でなかなかちょっと入居ができないようなケースがあったりもしますので、ぜひそのへんのところも検討して変更いただければというふうに思います。
また、町営住宅の築年数がかなり経っているところもあると思います。建て替えの検討などを行っているかどうかということと、あと公営住宅等整備基準というのが改正されて、入浴設備を設置することが義務づけられているのですけれども、しかしながら改正前に建てられたものについては入浴設備がなくて、入居者が入居する際に設置して、また退居する際に撤去するということが未だにあるのかどうかということも含めて答弁をお願いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)町営住宅、だいぶ中之条町でも所有しておりますけれども、だいぶ古くなってきております。古い町営住宅の建て替えの検討についてというお尋ねでありますけれども、町営住宅の建て替え事業の計画策定は具体的にはしておりません。町営住宅につきましては、耐震性が確保されていない古い住宅は、入居者が退居した後、随時建物の解体を進めております。また、古くても耐震性が確保される住宅については、老朽化が進行するわけですけれども、安価な家賃で大変人気のある施設ですので、建物の内外に不具合が生じた際には、その都度修繕を行い、既存住宅の維持管理を適正に行い、できる限り人気のある建物を存続させていきたいと考えております。現在では、具体的な建て替えを計画する時期ではないと判断している状況であります。
それから、入浴の浴槽については、担当課長のほうからちょっと説明をさせていただきます。
〇議長(安原賢一)建設課長。
〇建設課長(本多宏幸)建設課長、本多でございます。ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。
町営住宅の関連ということになりますけれども、公営住宅法が法律ができたのが非常に古い話で昭和20年代の話になるわけです。当時の背景からすると、生活に必要なもの、そして部屋が提供できる、最小限のものを整備をして貸し出すというのが基本原則になっている状況でございました。
また、大きな改正が平成8年度に公営住宅法が改正をされまして、大幅なこれ改正だったわけなのですけれども、徐々にそれ以降、公営住宅の物件に関して入浴施設、当時昔は浴槽のない浴室のみを整備して貸出しをしていたのですけれども、浴槽の設備等を含めた建設も可能になってきたというような状況の中から町で建設している公営住宅につきましても新しい建物については浴室に浴槽等の設備、そういったものを整備して貸出しをしている団地がございます。例えば中之条団地、それから西中之条団地、こういったところはそういう対応を図っておるところでございます。しかしながら、古い物件につきましては、建設をした当時から同じような形で運営をさせていただいておりますので、浴室内の設備等につきましては、入居者負担として管理運営を現在もいたしておるところでございます。
以上でございます。
〇議長(安原賢一)5番、山田さん
〇5番(山田みどり)お風呂が普通にあるというのが今みなさんの暮らしの中で当然だと思うのです。ところが、この建物がその当時から変わっていないものですから、入浴設備がないということで、未だに入居の際にそういった入浴設備を設置しなければいけないということなのですけれども、こういった整備基準が改正されている中では生活する上ではもう風呂は当然必要ですし、当然町が請け負う施設管理だと考えるのです。なので、入居者に求めるというのが間違いではないのかなというふうに感じます。なので、設備をきちんと整備して入居者負担ではなく、こちら側がしっかり、町側が施設管理をするということが大切ではないのかなというふうに思いますので、今後もちろん入居者の声も聞きながらぜひ検討していっていただきたいと思いますが、町長いかがでしょうか。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)担当課とまたいろいろ調整をさせていただいて、検討させていただきます。
〇議長(安原賢一)5番、山田さん
〇5番(山田みどり)ぜひよろしくお願いいたします。
地方自治法改正について
最後の質問に移りたいと思います。地方自治法改正によって、自治体への影響はどうかという質問をさせていただきます。
今国会では、審議されている、衆議院では可決されまして、今参議院では審議が入っているという状況の自治法改正です。この自治法改正によって、自治体への影響がどのような影響があるのかということを考えなければいけないのかなというふうに思います。改正案では、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における生命等の保護の措置について、国が特例として自治体に必要な指示を行う補充的指示権を定めるとしています。自治体に指示できるものとして大規模災害、感染症の蔓延、その他としています。そもそも国と自治体は、対等として地方分権改革が進められてきたはずです。それに逆行することではないでしょうか。
岸田首相は、大規模災害や感染症を理由にしていますけれども、災害に対しては災害対策基本法があり、その中で必要な指示権があるはずです。また、コロナなどの感染症に対しても国が行った対策の号令が本当に正しかったのかということを検証する必要があると思うのです。一斉休校などがそれに当たると思いますけれども、こういったことが本当に正しかったのか、そういったこともぜひ検証していかなければいけないと思います。
自治体には、それぞれの近隣との連携、また姉妹都市などの情報連携、様々な横のつながりを大切にしてそれぞれの自治体が持つ能力があると思います。それぞれの首長が持つ独自の施策というのは、地域の特性を生かしたものですし、国が介入して壊していいものではありません。国の方針によって町民生活に大きく影響を与えることに対して、町長としてその見解をお聞きします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)自治法改正案が今国会で審議されていることは、承知をいたしております。国では、第33次地方制度調査会の答申を受けて「DXの進展を踏まえた対応」、「地域の多様な主体の連携及び協働の推進」及び「大規模な災害、感染症のまん延その他及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例」、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称されますが、こうした規定を整備し、地方自治法の一部を改正する法律が公布をされました。
特に議論となっておりますのは、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」で、主な改正点といたしましては、1つとして、事態対処の基本方針の検討等のため、国は地方公共団体に対し、資料または意見の提出を求めることを可能とする。
2つ目としては、適切な要件、手続のもと、国は地方公共団体に対し、その事務処理について国民の生命等の保護を的確かつ迅速に実施するため講ずべき措置に関し、必要な指示ができること。
3つ目といたしましては、国民の生命等の保護のため、国の指示により都道府県が保健所設置市区等との事務処理の調整を行うこと。
4つ目といたしまして、国による応援の要求、指示、職員のあっせん等を可能にすることなどが上げられております。
地方分権一括法により国と地方の関係は、上下、主従から対等、協力となり、地方自治の発展を図ってきたところでございます。こうした時流に反するのではないかと危機感を示している首長や弁護士会からは改正に異を唱える声明など、各方面から議論がされていることは承知をいたしております。根本には、改正の内容が曖昧であり、具体性に欠けているといった問題があるとの指摘もございますが、いずれにいたしましても現段階では課題も含め、実態がまだまだ不透明であります。他方で多くの自治体が、例えば災害時など、先ほどおっしゃいましたように互いに支援をし合えるような協定の締結や協力体制の確立、あるいは交流を通じての結びつきの強化など、独自に横のつながりを図っております。そういったことも大切な共助であると考えております。
中之条町も含め、自治体に対しての影響についてどのように考えるかというご質問でありますけれども、法が施行され、具体的な事務への影響等を見据えながら国と地方の理想的な関係について今後も注視してまいりたいと、このように考えております。よろしくお願いいたします。
〇議長(安原賢一)5番、山田さん
〇5番(山田みどり)指示的運用によっては、時の政府が指示すれば、こういった情報提供だとか事務作業というのが負担になってくる。動員も閣議決定だけで可能になってきます。今公務員というのは、どんどん減っていて、業務も多忙になり、いろいろなDXも入ってきて本当に多忙な中でこういった国の一声で町の自治体職員を動員して協力していかなければいけない。だから、こういったことを許していいのか。例えば事例として挙げているところがありましたけれども、自衛隊が道路封鎖などを行う際に国が求めれば自衛隊職員の動員協力までもが可能となるわけです。職員が減っている中で現場の状況も鑑みず、このような横暴なやり方を許していいのか。町長としても危機感を持ってぜひ注視していっていただきたいというふうに思います。
私の質問は以上です。
◎ 発言の訂正
〇議長(安原賢一)ここで、先ほど山田みどりさんに対する町長の答弁の中で、自治法の関係で訂正がありますので、お願いします。町長
〇町長(外丸茂樹)大変申し訳ございません。先ほど山田みどり議員からいただきました自治法改正案の答弁の中で「地方自治法の一部を改正する法律が公布」というふうに私申し上げてしまったのですが、「現在審議中」ということでありますので、ご訂正をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。