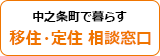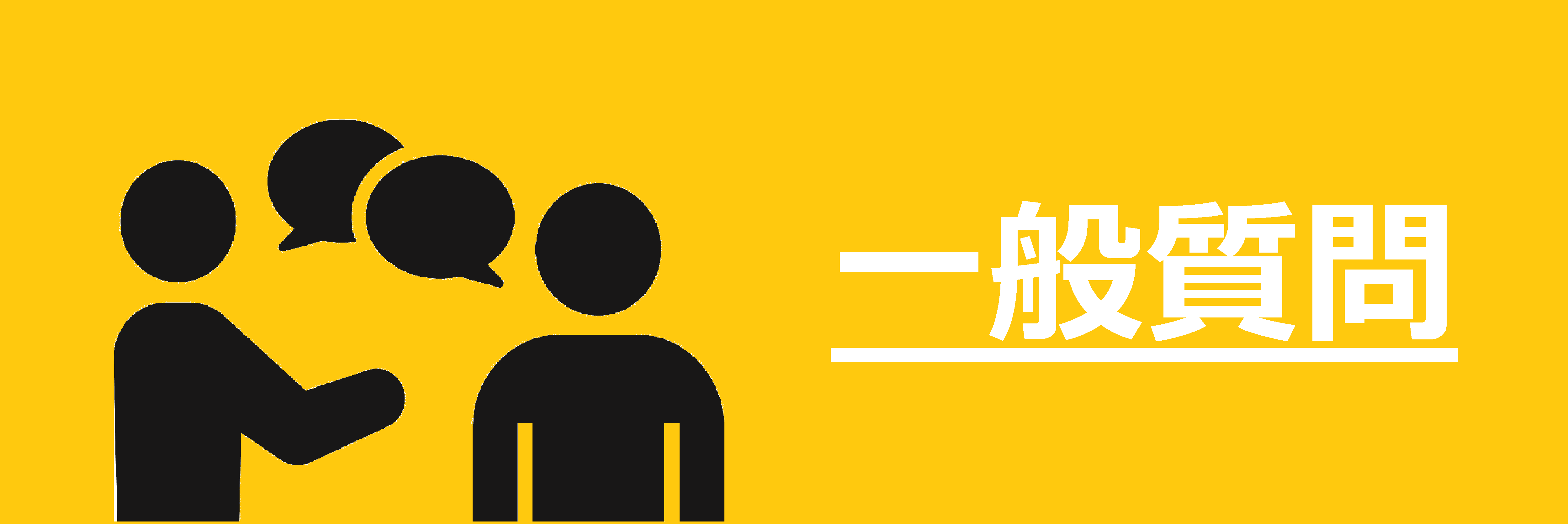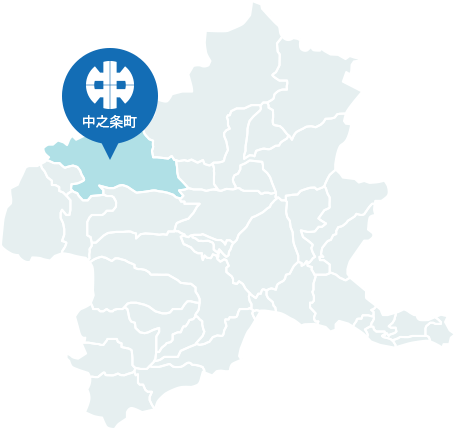本文
令和7年6月定例会議 一般質問(山田みどり議員)
03 5番 山田みどり議員 令和7年6月定例会議一般質問
〇5番(山田みどり)それでは、通告に従いまして、一般質問を行います。
私の質問は、高齢者が安心して暮らせる町づくりに関する質問。もう1つ目が、学生の通学支援について、この2つで質問をさせていただきます。
高齢者が安心して暮らせる町づくりについて
まず、高齢化が進む中、住民が安心してこの町に住み続けるための高齢者支援について。少子高齢化が急速に進む本町において、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる環境を整備することは喫緊の課題であると認識しております。
そこで、お伺いいたします。本町における高齢者支援の具体的な取組として、現在どのような施策が実施されており、その効果をどのように評価されているか。特に在宅での生活を支えるサービスや地域での孤立を防ぐための取組について、説明をお願いいたします。
○議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)それでは、山田みどり議員のご質問にお答えをさせていただきます。
現代社会におきましては、地域のつながりが希薄化していると言われておりますが、中之条町では都市部に比べますと地域のつながりがまだ残っているものと認識をいたしております。今後高齢者が生まれ育った地域で生活していく上において、在宅での生活を支えるサービスや孤立を防ぐための方策の一つとして、高齢者と地域とのつながりをより強く深くする必要があると考えております。そのためには、各行政区での付き合い、老人クラブなどへの参加などが考えられますが、町では介護保険特別会計における生活支援体制整備事業におきまして、行政区単位より広い中之条、伊勢町、沢田、伊参、名久田、六合の6つの単位で第2層協議体を募り、居場所づくりを出発点に地域住民主体による活動を行っております。また、地域の老人クラブや町老人クラブ連合会に対して活動費の助成を行い、高齢者の生きがい創出に取り組んでおります。このほか買物支援事業として買物支援バスの運行や高齢者の栄養管理を兼ねた弁当などの宅配業務委託を実施しており、移動販売車による買物見守り支援事業につきましても現在協議を進めているところでございます。また、見守り活動として民生委員・児童委員の方々による独り暮らし老人に一声かける運動や町社会福祉協議会による配食サービスを行っており、加えて令和7年度からは包括支援センターに業務委託した高齢者見守りネットワーク事業による第三者の目と行政をつなぐ施策を実施しております。今後人口減少により支える側の人材も減少していることが見込まれますことから、みなさんにご意見を伺いながら住み慣れた地域で住み続けられるような施策を今後も検討してまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。
〇議長(安原賢一)5番、山田さん
〇5番(山田みどり)ご答弁いただきましたように、様々な取組をされているというふうにお聞きしました。今年度から始まった見守りネットワーク支援というのは、昨日お聞きしたら8団体、8事業者というのでしょうか、が名乗りを上げていただいてそういったご協力をいただけるということで、たくさんのやっぱりそういった目を増やしていって見守りをしていただくということは非常に大切だなというふうに思います。
山間部の地域では、非常に集落数が減少しており、助け合いや地域の声かけができているところも一方ありますけれども、町場では地域のつながりが困難なところもあります。若い方が住まわれていたりとかして、やっぱりこういった声かけ、どこに誰が住んでいるかちょっと分からないというような、そういった地域もあります。地域ごとの課題をどのように対策していくかと考えると、やはり地域で今中之条、伊勢町、沢田、伊参、名久田、六合の5つのところでやっている第2層協議体の取組というのは重要であると考えます。この第2層協議体が立ち上がったときも非常にどのように進めていくのかということで、地域でかなりいろいろ議論がされていて、またこの取組が始まってから間もなくでコロナ禍があって、コロナを挟んで動きがなかなか取れなかった時期もあり、非常に困難な状況であったと伺います。しかしながら、これからは団塊の世代が後期高齢者になる時期に来ておりまして、より一層地域の高齢者への支援や見守りというのは必要であると考えます。第2層協議体は、地域の主体的な取組ということですけれども、誰がどのようにやっていくのか。その役割が非常に重たくなってしまわないように、そこのところの解決ができないと持続的に長い期間でやっぱり実施をしていくということが非常にかなりハードルの高いことではないかなというふうに考えます。地域ごとの悩み、それぞれがあると思うのですけれども、それを解決していくために、簡単なことではないですけれども、町づくりを担う行政として地域のみなさんの声をぜひ聞いていただければというふうに考えます。
高齢者の皆様の生活の実態、こういったことを正確に把握するということが非常に大事だと思います。状況を把握して、また効果的な政策につなげていくということが重要です。そのためには、高齢者の生活状況、どのように把握されているか。アンケート調査など具体的な取組が行われているかについて、説明をお願いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)高齢者の方の暮らしの実態についてどのような調査をしているかというお尋ねでありますけれども、高齢者の暮らしの実態調査についてお答えをさせていただきます。
町では、例年民生委員・児童委員の方々のご協力の下、6月1日を基準日としたひとり暮らし高齢者調査を実施しております。これは、町内のひとり暮らしや高齢者の実態を把握し、今後の高齢者福祉対策や防災対策などの基礎資料を得ることを目的としているものでございます。調査項目につきましては、緊急時の連絡先、既往歴や受診医療機関、日常の困りごとなどとなっており、今年度は災害時に1人で避難することが可能かどうか、項目を追加しております。なお、この調査結果につきましては個人情報ではありますが、緊急時に安否確認に必要な場合には関係機関へ情報提供させていただくことに同意をいただいているものでございます。このほか高齢者の方の暮らしの実態を把握するための調査につきましては、現在のところ体系的な調査は行っておりませんが、民生委員・児童委員や町社会福祉協議会、県吾妻保健福祉事務所などと連携して実態把握に努めているところでございます。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)5番、山田さん
〇5番(山田みどり)おひとり暮らしの方を把握して、地域での声かけ、見守り、必要なサービス提供につながるようにすることが非常に重要であるというふうに考えます。今こういった調査を行って、必要な情報は緊急時には安否確認としてそういった関係機関への提供をしているということでありますけれども、必要なやっぱりその人が望むサービスだとか、必要なニーズについてはしっかりとそういったものをつなげられるような情報提供というかが必要かなというふうに考えます。
また、今おひとり住まい、おひとり暮らしの方の把握というふうにおっしゃられましたけれども、単身住まいだけでなくて高齢者ご夫婦で高齢者であったりだとか、今、兄弟、あとは超高齢社会なので、親子でも高齢者だけでという、そういった様々な暮らしをされている方が多くいらっしゃると思います。万が一のとき、困ったときに助けてほしいという声を上げることができればいいのですけれども、本当に隣近所すごく遠く離れているだとか、そういったすぐに来てもらえる人がいないとか、そういうこともあったりだとか、あとはみなさんやっぱり遠慮深くて迷惑をかけてしまうかもしれないと我慢されてしまっている場合もある。本当に重篤化してからやっと声を上げるような、そんなことにもなっていることも、ケースもあったと聞きます。我慢せずに気軽にこういう困ったという声を出せる、やっぱりそういった地域づくりというのが非常に理想ではあると思います。伊参の地域、非常にやっぱり高齢化が進んでいて、伊参地域議員団のみなさんもこういった取組を、こうした地域づくりの取組を今進めておられるというふうにお聞きしています。町場でも決して人がたくさんいるから安心というわけではなくて、やっぱり孤立されている方もいらっしゃると思いますので、どこに住んでいても安心して生活ができる町づくりというのが行政の役割だと、繰り返しになりますけれども、役割だと思っています。地域課題に行政は何ができるか、引き続き皆様の声をお伺いして取り組んでいただければと思います。
答弁いただいたように、高齢者の施策、本当に非常に様々取組をされて、おひとり暮らしへの声かけだとかいろんな関係機関、郵便局だとか今ヤクルトさんとかいろんな事業者さんとの連携をして声かけや見守りをされているということが分かりました。あとは、そういった方々が必要なサービスに必要なときに受けるということができるように、そういうニーズに応えられるように引き続きの取組をぜひお願いできればというふうに思います。
次の質問に移ります。高齢者施設の運営状況と今後の支援についてという項目で設問します。新型コロナウイルスの感染症の影響によって、町内の高齢者施設の運営環境というのは非常に大きく変化し、各施設事業者、大変な努力をされていると伺っております。コロナ交付金や物価高騰交付金、様々あって、こういった交付金などで運営は非常に助かっているけれども、今後の運営については依然として不安を抱えているというふうにお聞きしました。感染症が施設内で発生する、そのたびにやっぱり利用者状況も減少してそういったもので経営的にも影響が出ているというようなお話です。施設では、どこでも運営が厳しいという状況にあると思います。高齢者施設というのは、高齢者が中之条町、住み慣れた地域で生活を持続するために不可欠な存在であり、その安定的な運営というのは行政サービスと密接に結びついているというふうに考えます。高齢者施設の存続は、高齢者の大切な居場所を守ることにもつながります。現状町内の高齢者施設というのは、民間事業者ではありますけれども、地域のお年寄りを支える、生活を支える上で極めて重要な役割を担っています。
そこで、町と施設がより一層連携し協力し、相互の情報を有意義に活用していくことが望ましいと考えますが、例えば町が高齢者と施設のマッチングの場を提供するなど、具体的な取組を進めることで双方にとってよりよい環境を築けるのではないかというふうに考えますが、町の取組としてお聞かせください。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)高齢者施設との連携等についてはというお尋ねでありますけれども、高齢者施設との連携が必要な場面を取り上げますと、実際には限られた事態であろうかと思われますが、そのときに備え、日頃から町と高齢者施設との連絡体制が確保されるよう定期的に開催されます地域密着型サービス運営推進会議への町職員の参加や包括支援センター情報交換会に高齢者施設の職員等にも参加をしていただき、情報提供、それから情報交換をするなど円滑な連携体制の確保に努めているところでございます。
〇議長(安原賢一)5番、山田さん
〇5番(山田みどり)情報交換や情報提供などを行っているという答弁ですけれども、施設の方とこの質問をする上で様々な方とお話を伺っているのですけれども、やっぱり非常に入所の利用者さんがすごく激減して減っていると。何で減っているのかというのが分からない。高齢者はたくさん、高齢者のみなさんいらっしゃるのだけれども、利用がなかなか、利用する方が少なくなったりだとか、あとはいろいろコロナを挟んでなかなか運営状況が非常に厳しいというのがどこの施設聞いてもそうですし、約7割、8割ぐらいの入所状況で、やっぱり空きがあるということをお聞きしました。どこの施設も大体そうです。空きがあるのですというお答えでした。いろいろ伺うと、ぜひ町と連携していろいろなことをやりたいのだというご希望をたくさん伺ったのです。防災、災害のときには防災拠点に全然使ってくださいとか、うちではこういうことができますよなんていういろいろなご提案をいただいて、そういったことをやっぱりぜひ町長にも後でおつなぎしたいかなというふうに思っていますけれども、いろんなアイデアを持ってこの地域でいろいろな役割を持ちたいと施設側のみなさんは思っておられるのだなというふうに感じました。
町のホームページに出ている「介護関連施設等の一覧」というのがあって、それを見させていただいたら、掲載されている施設というのが、ちょっと社協も入っていますけれども、50、一覧がばあっと並んでおりました。それぞれに条件とか施設の目的も違っていますけれども、これどこを見て何がいいのか、どこがいいのか、介護事業者がこれだけ多いとどういうものがいいのかというのは直接相談してお伺いしないと、こういった機能がありますよ、こういった方は入所できますよ、できませんよというのは相談しないと分からないのだなというふうに感じました。施設側のみなさんから出た意見で、介護事業者が直接出向いていって話ができる場をつくってほしいというお声をいただきました。町が特定の事業者にあっせんすることはもちろんできませんけれども、利用したい方のニーズであったりだとかサービスを選択してもらう手助けや情報提供というのは必要であるかなというふうに考えます。今役場の窓口に行きますと物すごくそういった情報があふれ過ぎていて、逆に選択しづらい。どれがいいのかが分かりづらいというような印象を受けました。やっぱり先ほど申し上げたように必要なところにきちんとつなげる、そのニーズをちゃんとつなげるということができる取組がぜひ今後検討いただければというふうに考えます。
今回の質問をする上で様々な方とお話をさせてヒアリングをさせていただいたのですけれども、みなさん口々におっしゃるのは介護ケアや医師、看護師、そういった方々が人手不足で本当にとにかく人がいないと。何でこんな状況なのかというと、やっぱりいろいろ加算されて、処遇改善の加算とかあるのですけれども、それでも労働条件とか賃金の処遇とかがまだまだもっと評価されるべきなのに処遇が低いということをみなさん口々におっしゃられておりました。介護施設では、職員の不足から外国人の方が多く働いていて、一つの施設をお伺いしたところでは、10人の外国人の方が働いておられるということなのです。超高齢化社会を支える上で、この人材確保ということも非常に課題であるというふうに感じました。引き続きこういう施設の運営を直接的にはいろいろ支援することは難しいかなというふうには思うのですけれども、やっぱり施設がなくなってしまえば高齢者の居場所がなくなってしまうということにつながります。50ある施設もやっぱり施設のそれぞれのいろいろの職員が取り合いっこになってしまったりだとかにはならないようにとか利用者さんの取り合いっこにならないようにうまくニーズにつなげていけるようにしていただいて、やっぱり今の施設がきちんと維持ができるように町としても見守っていただければというふうに思います。
今、高齢者支援でやっぱり切っても切り離せないのが医療の問題だというふうに感じています。吾妻の医療体制というのは、非常に脆弱になっていると思います。これは、要望としてもぜひ町長にご答弁いただきたいのですけれども、町の今後として医療問題どのように考えるか。病院がないからとか、いざとなったときに心配だからといって都市部に人が行ってしまうとか、そういったことがないようにやっぱり都市部との医療格差が生じないように各方面にこれまでたぶんたくさんそれこそ声を上げていろんなところに各方面お声かけいただいていると思うのですけれども、引き続き働きかけを求めたいと思いますが、町長の見解を、今までの取組などの事例もちょっとお話しいただければと思います。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)山田議員おっしゃるように、吾妻地域は医療過疎という状況にあることはもう私も十分承知をいたしております。広大な面積を有する吾妻郡、中之条町も広うございますので、そういったことからすると本当に医療過疎の状況にあるということは認識をいたしております。高齢者の支援と医療というのは、これはもう切っても切り離せないものでありますので、しかしながら吾妻の医療、医師、医療従事者、これは不足するという状況にあります。先ほど言ったように医療過疎というような状況にありまして、高齢者の医療ばかりに限らず救急医療、あるいは周産期医療などをはじめとして十分ではないというふうに認識をいたしております。中之条町におきましても、心の不調や認知症に対応し入院の受入れも可能である中之条病院を吾妻広域町村県振興整備組合の一員として運営しております。四万地区では、無医地区を解消し住民に安心して暮らしていただけるよう四万へき地診療所を運営し、六合地区におきましては地域医療振興協会の協力をいただきながら六合診療所を運営し、中之条町の医療を直接的に支えております。
また、都会との医療格差が生じないような取組が求められていることは承知しておりますが、先ほども申し上げましたように吾妻地域では格差を埋める前に医療過疎とも言えるような状況にあり、地域住民が安心して暮らす上で必要とされる医療の維持、確保さえ難しい状況にあります。こうした状況の中、少しでもこうした状況を少しでも解消し医療の維持確保のために中核病院である原町赤十字病院と救急医療をはじめとした吾妻西部の医療の要となる西吾妻福祉病院に対して補助金を交付し、病院運営の支援を行っているところでございます。なお、2つの病院とは定期的に話合いを持ち、意見交換を行いながら厳しい病院経営の中でも救急医療の維持、充実や医師の確保に努めていただくよう申入れを行っているところでございます。また、看護師の養成施設である吾妻准看護学校につきましても補助金を交付し、医療従事者の育成に支援をしておるところでございます。こうした医療の維持や充実への取組、支援につきましては今後も継続し行ってまいりますし、国や県に対しましても機会あるごとに働きかけを続けていきたいと考えております。
先ほどの周産期医療の関係については、小児医療センターが移転をするというような情報がありまして、吾妻郡6か町村の首長として、渋川地域も含めながら周産期医療、これの維持を何とか考えていただきたいということを群馬県知事にも申入れをいたしております。今お話もさせていただきましたが、日赤の運営協議会なんかにも出席をさせていただいたときに、とにかく高齢者になってきますと救急医療が非常に重要だということを院長先生にお話しさせていただいて、補助金を出す支援をするのはいいのだけれども、ぜひそこのところの医師の確保、特に救急の場合はお年寄りは特に利用しますので、そういうところをお願いしたいと。それとあわせて、やっぱり医療スタッフ、これが大変なのだという日赤からもお話がありました。もう我々も一生懸命応援しますので、医療機関として県や、それから関係医療機関にも働きかけをしてくれと口を酸っぱくしてお話をさせていただいております。
以上であります。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)5番、山田さん
〇5番(山田みどり)要望ということでご答弁いただきましてありがとうございます。本当にこの地域医療の問題、吾妻だけではなくて全国的な問題であり、都市部というか東京都内でも医師が不足しているというような話を聞きました。私、この質問をうーんと考えながら昨日たまたまちょっとテレビをつけたら医療問題のちょうど取り扱っていたのですけれども、若い医師が研修を終えてどこに行くかというと美容外科医に行くそうなのです。そういういろんな病院を回ってみても、やっぱり給与面で全然違うのだと。そういうところに医師が流れているという現状があって、これがもう見ていて腹立たしかったのですけれども、命の問題であり、我々のこの地域で命や健康の問題であるということを、関わることなので、やっぱりこの問題を、この議会において何かが変わるわけではありません。この質問をしたから、では医師が確保できるとか、その予算がつけられるとかそういうことではないのですけれども、しかしやっぱり地域の方の命の問題、暮らしの問題であると。この状況に陥っているというのは、やっぱり政治の責任であるというふうに強く思うのです。医師が不足している、医師がそういうふうな状況になっているということをとにかく今の現状、政治を変えていかなければやっぱり変わっていかないというふうに思います。
我々は、確かにこれはもう仕方ないことだなって思うかもしれないけれども、でも議会人であり、町長という立場からもやっぱりこれはこの小さな町からでもとにかくどんどん声を上げ続けていって政治を前に動かしていかない限りは、これ諦めたらもうこれでおしまいだと思うので、とにかく町長が知事にも申し入れたように、こういうふうに引き続き声を上げ続けていくということが非常に大切だなというふうに思いますし、私たち、ここに、議場にいるみなさんもやっぱりその責任があるということで、引き続き議会としてもこの問題については全員で取り組んでいけるような議題だと思っておりますので、引き続きやっていきたいというふうに思います。
この質問はこれで終わりにしますけれども、高齢者を支えていく、超高齢化社会を支えていく上での人手の問題もありますし予算の問題もありますし、それでもみなさんがそういった目できちんと支えていく人をみなさんが支えていくという思いでやっぱりやっていく、これが中之条町の一つのよさかなというふうに思いますので、これからもこの高齢者支援を続けていけるよう様々な取組を続けていっていただきたいというふうにお願いいたします。
学生の通学支援について
次の質問に移りたいと思います。学生の通学支援について質問を続けます。子育て支援施策においては、非常に外丸町政では力を入れていただいているということは認識しております。経済的支援だけでなくてケア的な支援ということも子育てする上ではこういった支援があること、非常に保護者からは評価をいただいて、ありがたいというお声をいただいております。しかしながら、やっぱり多くの保護者から伺うのは、高等教育になって、高校生や大学生になってからなのですけれども、経済的な負担が非常に大きいというお声を聞きます。高校の学費は、今軽減されていますけれども、通学費や学用品、部活動にかかる経費など、保護者の実感としては負担が増しているというふうに感じております。こうした理由から高校に近い地域へ転出してしまうケースもあると聞いております。本町として、経済的な支援と、また定住促進のためにも公共交通を使っている学生への通学を支援する必要があると考えますが、町長のお考えをお聞かせください。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)学生の通学支援というお尋ねでございます。JR吾妻線や路線バスなどの公共交通を利用して通学している学生は、町民の中では高校生や大学生、中之条町立でない小中学生や中等教育学校など町外の学校へ通う学生が考えられます。現在中之条町では、通学に伴う定期乗車券の補助制度は設けておりませんが、隣町の東吾妻町では既に小学生から高校生までを対象にして補助制度を創設し、補助金を交付しているようであります。中之条町におきましては、群馬県立吾妻中央高校があり、公共交通を利用しないで通学できる町民もおります。東吾妻町と同様に補助制度を創設した場合、遠くの学校へ通学する町民と近くの学校へ通学する町民との間で不公平感が生じてしまうことも想定をされますし、さらに遠く離れた学校で寮生活などを送る学生もいることを考えた場合には、やはり不公平感が生じるのではないかという可能性もございます。子育て家庭への経済的支援としては、この不公平感の解消につきましても考慮する必要があることから、ほかの補助制度の拡充も視野に入れながら検討する必要があるのではないかと、このように考えております。現時点では、通学に伴う定期乗車券の補助制度創設を予定しておりませんけれども、近隣の市町村における補助制度の状況等を調査研究した上で慎重に検討してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、私の一つの政策の大きな柱であります子育て支援、これについては群馬県内でも相当力を入れている中之条町ではないかなと。これは、前任の中之条の、前任の町長のときからもそうですけれども、そういった観点からすると子育てをするのなら中之条町といったことはやはり念頭に置いて今後もこういう課題についても研究をしていきたいと、このように考えております。
〇議長(安原賢一)5番、山田さん
〇5番(山田みどり)そうなのです。子育て支援、非常に頑張っているからこそここにもさらにぜひやっていただきたいという声が非常に多かったというのがこの質問をするきっかけなのですけれども、先ほど来からやっぱり不公平感という言葉がありました。通学費かからない家庭には何も恩恵がないではないかということだと思うのです。しかし、通学費の定期代、おおよその数字なのですけれども、渋川まで半年で約4万円ほど、群馬大津までも同じぐらいの4万円ほどかかります。高崎までとなると半年で約5万円の定期代がかかると。こういった負担をかけて学校に通っているその負担の一部を支援することが、それだけ学校に通わなければいけないためにそれだけ負担がかかっているのだから、その支援をすることが不公平になるとは、私は思えないかなというふうに思うのです。やっぱり自分の選択、自分がこういう学びをしたい、こういう部活をやってみたいといういろいろな理由で子供たちは学校を選ぶ、選択したわけです。そうした選択を応援して自由な学びの環境整備をするということは町の役割だと思いますし、それこそ今大津と言いましたけれども、吾妻線の問題では赤字路線ということで吾妻線の協議会が始まっていますけれども、それこそこの吾妻線、今本当に学生が、これちょっと話があれですけれども、学生が主になのです。あとは、観光シーズンになるとお客さんが来るけれども、1,000人ぐらいかなというような、ざっくりとした数字ですみませんけれども、駅の職員の方がお答えになっていましたけれども、非常にこういう問題になってもやっぱりそういう吾妻線がなくなってしまえばそういった学校に通うことさえも非常に困難になってしまうというふうになることにつながるので、ぜひ吾妻線を利用して学生が通っていただいているということが非常にいろいろそういう公共交通にも影響があるものであるというふうに考えますので、ぜひこの通学支援、子供たちの学びの環境の整備の役割、あと公共交通への活性の役割、そういった役割を様々持っているというふうに考えますので、引き続きこの件については研究いただいて、保護者のみなさんの熱い熱いご要望も私必死に受けてここに立っておりますので、ぜひとも検討いただいて、この私の質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。