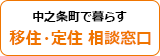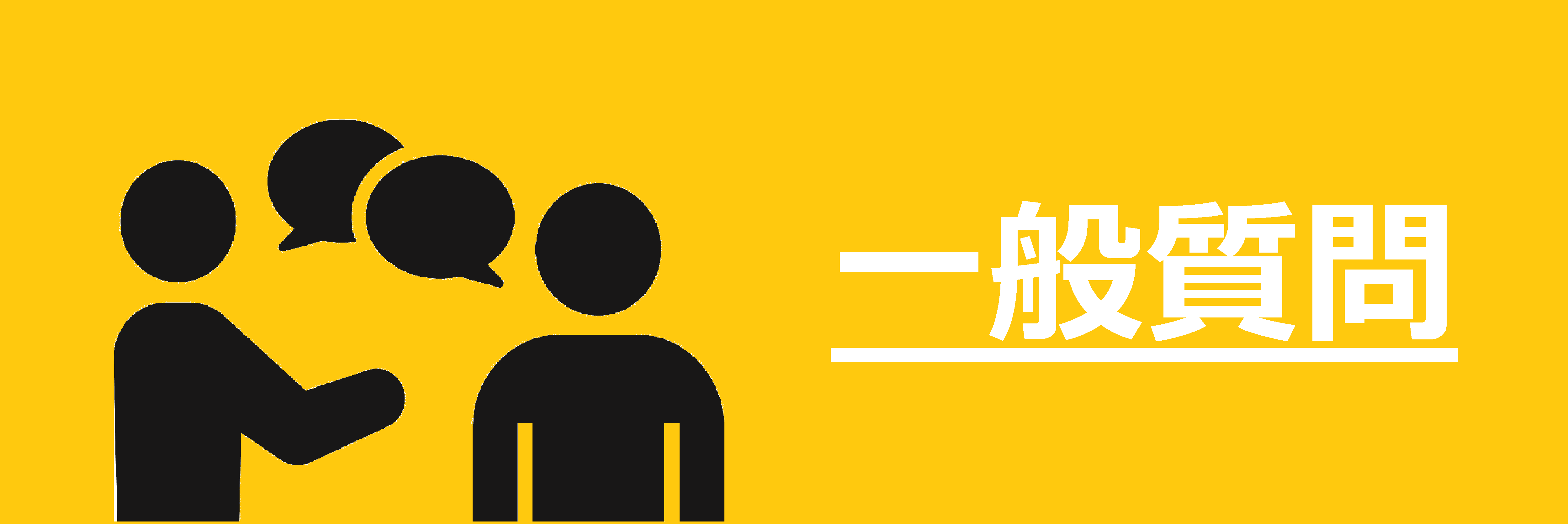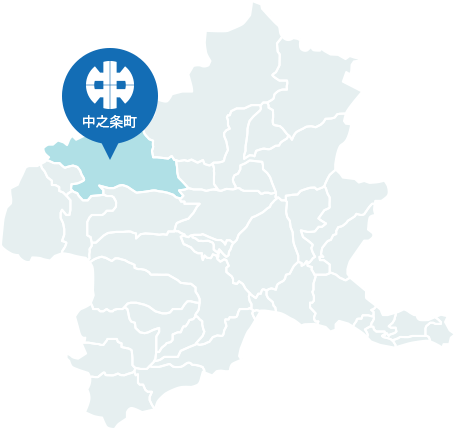本文
令和7年6月定例会議 一般質問(原沢香司議員)
02 1番 原沢香司議員 令和7年6月定例会議一般質問
○1番(原沢香司)それでは、通告に基づきまして、3点について質問をいたします。
最初に、令和の米騒動と称される米不足と米価の高騰について、現状と対策、そして今後の町の農業との関係性を柱に伺います。次に、芳ヶ平湿地群と野反湖における高山植物の食害への対策について、現状と今後の対策について質問をいたします。最後に、本議会に条例案が上程されましたカスタマーハラスメントについて、特に町職員への影響と対策について伺います。
令和の米騒動と称される米不足と米価の高騰について
まず、米の問題です。これまで2年にわたる産業建設常任委員会での議論において、農業政策についてたびたび取り上げてきました。また、日本共産党議員団としても予算要望として農業政策について各種提案を重ねてまいりました。外丸町長におかれましては、農業問題についてご自身の経験も基に積極的に各種補助制度などを実現し、町の農業を守るために意欲的かつ迅速に動かれておりますことにまず敬意を表します。
米の価格が上昇し、消費者、飲食店経営者、宿泊事業者などに多大な影響を及ぼしていることは、言を俟ちません。連日報道もされておりますし、国会での議論もなされております。生活に関わるあらゆるものが高騰し、トランプ関税などで世界経済の先行きも不透明な中で、私たち国民の主食である米が足りていません。日常生活への安心が脅かされているといっても過言ではない状況です。2023年5月の時点で1,890円であった米5キロの小売り平均価格が2025年の4月には4,225円と2倍以上の価格に引き上がっています。これは、異常な事態です。米の価格が高騰している原因については、様々な言説が飛び交っております。また、政府が放出した備蓄米についても報道が加熱しております。そもそも国民の財産である備蓄米です。これまで市場任せにしてきた価格を一転して政府が決めて販売する。また、輸入米について言及するなど、現在の政府が行っていることについては、私は大変問題が多いと感じています。あらかじめ申し上げておきますが、この米問題は、私は国の明らかな失政が招いた事態だと認識しております。ですので、根本的な解決のためには、長らく続いてきた自民党政府の農業政策を根本から転換する必要があると考えております。しかし、だからといってこの問題を国に任せて解決を待つわけにはいきません。なぜなら、米の問題は町民生活にとって大きく、そして深く関わる問題だからです。生産者である米農家もいます。飲食店を経営する方もいます。宿泊事業者の方もいます。これが我が中之条町です。もちろんそのほかに医療機関や福祉施設を経営する方、流通に関わる方、米屋を経営する方など、様々な方にとって米の問題は直接的に、密接に関わってきます。そして、自分で作っているにせよ購入しているにせよ、ほとんどの町民は米を食べています。この米問題は、広く町民に関わってまいります。米の問題を国任せにするのではなく、地方自治体でできる対策を考え講じていくことがこれからの町民の食生活を守り、町の農業を守り育てていく上で欠かせないと考え、今回の一般質問で取り上げます。
まず、外丸町長の認識を伺います。今般の米不足と米価の高騰が生じた原因をどのように考えますか。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)それでは、原沢香司議員のご質問にお答えをさせていただきます。
ご質問の中でいろいろ今までの経緯等も原沢議員からご指摘、あるいはお話をいただきました。本当に連日テレビでどの局も毎日毎日米の問題を取り上げる。これは、非常に国民にとって、我々町民にとっては主食の米ですから、本当に心配されるところであります。これに多くの国民の方々がやはり注目をしているというような現状ではないかと、こんなふうに思っております。かつて平成5年に冷夏によって米が不作になったことがございます。タイ産の長粒米と言われる米が輸入されたことがありました。今回は、米農家の高齢化あるいは政府の生産調整などの米政策、また近年の夏の高温や害虫の発生などによる収量の減少等が複雑に絡み合っており、複数の原因があるのではないかなと、こんなふうに思っております。この問題が昨年の8月以降に取り上げられてからもう既に今年の秋には米の収量の心配がされるといった状況でありますので、やはり主食である米については予断を許さない、そんな状況であるのではないかと、こんなふうにも私、認識をいたしております。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)町長の答弁にあったとおり、米不足の要因、これは単純にこれだけというものではなくて、複数あるのはたしかだと思います。その中で米政策、特に政府の生産調整についての言及がありました。少し詳しく数字を挙げますと、農業者戸別所得補償制度が廃止されたのが2010年、安倍政権のときです。これにより年間1,500億円以上の農業予算が減らされました。米の作付けを減らしたり食料用米に切り替えると補助金を出すなどの減反が押しつけられ、その結果2013年と2024年を比較すると、米の生産量は20%減っています。その生産を担う米作りの時給は2021年、22年は10円となっています。まさに米作って飯食えぬという状況がつくられてしまったわけです。中之条町で米作りをされている方にお話を聞いても、この状況ではとても農業を継いでもらうことはできない、田んぼは自分の代で終わりだと話す方がほとんどです。生産しても次の年に再生産できるだけの収益が得られない構造がつくられてしまえば、その産業が持続するはずはありません。こうやって政策的に米農家が激減し、米の不足と価格高騰が起こり、食卓にそのしわ寄せが来ている、これが現在の状況だと考えます。誰もが安心して国産の米を食べられる状況をつくる必要があると思います。そのためには、農家を支える価格補償、所得補償を行うことが欠かせないと思います。農業予算を思い切って増やし、輸入の拡大をやめて日本の農業を守っていく必要があると考えます。
次に、もう少し時代を遡って農業の構造変化を見てみたいと思います。1960年代に日本の農業の大きな転換点がありました。農業の憲法とも呼ばれる農業基本法が工業との所得格差を解消することを目的に1961年に制定され、利益率の高い産品への転換、生産性の向上、農業構造の改革が政策の基本に据えられました。食糧増産を目的とする法的な農業から経済合理主義的な農業への転換が図られたわけです。日本農業の特質である零細規模、零細経営が生産性の低さの原因であるとされ、規模拡大や効率化を目的とするメニューが並び、市町村長が事業計画を立て地域指定されると、高い率の補助金や低利の融資が受けられるようになったわけです。このことで、大型機械の導入や野菜や果物では市町村ごとの産地の形成が奨励されてきました。この流れが今日まで続き、今でも効率化、集約化などのかけ声の下で農業の大規模化が推進されております。今般の米不足解消にも農地の大規模化やスマート技術の導入を図る農家への支援をしていくと政府は言っています。しかし、典型的な中山間地である中之条町では、この大規模化はそもそも一部を除き不可能で限界があります。町の農業を維持していくためには、大規模化できる条件がそもそもない小規模農業者への支援が欠かせないと考えます。町では、今年度新たに中之条町小規模農業者農業経営支援事業補助金を導入しました。この制度への農家の反応及び活用状況はいかがですか。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)今、長年にわたる農水省が行ってまいりましたいわゆる減反政策、これの話を始めるとどうも1時間ぐらいしゃべっていなければならないので、ちょっとそこら辺は割愛させていただきますけれども、この減反政策も最初の頃と終わる頃では内容もかなり変わってきておると。そのところに対して小さい農家、あるいは大きい米作り農家もなかなかもう対応できなくなってきているという状況があるのかなというふうに思います。それは、もう高齢化もありますし、先ほどおっしゃいましたように中之条町の場合は集約して米を、あるいは米農家が大規模化しようといっても、どうに考えても中山間地ですから、もう現実的にそういうところは中之条には当てはまらないのではないかということも、農家の方々も自分たちで分かっているのですけれども、いかんせんここへ来て高齢化という波が寄せてきています。それに加えまして、やはり燃料の問題、それから機械の問題、肥料の問題、農薬の問題、全てこれ高騰されていますから、農家の米の所得率が極めて低くなってきているということをやっぱり頭の中に置いておかなければいけないのかなと、こんなふうに思っております。町独自の、今回私の思いで小規模農家の補助金を創設をさせていただきました。中之条町には、大きい農家さんもいらっしゃるのですが、小さい農家もしっかり山間部で農地を守ってくれる。これによって、間接的には水田ダムと言われるように災害の防止にもなります。そして、お年を召した方でも一粒でも一生懸命米を作ろうではないかという意欲をやはり持っていただくのだと、そういうことを基本に置きまして今回小規模農業者経営支援補助金、これの創設をいたしました。
そのお尋ねについての説明をさせていただきますけれども、対象は農産物の販売等の収益事業を行っている小規模農家となっております。具体的には、認定農業者や認定新規就農者以外で農業収益の税務申告を行っている農家を対象としております。小規模農業者が機械や施設を導入した場合、その経費の10%を補助するもので、同一年度において補助金の上限を5万としており、上限に達するまでは複数回申請することも可能とさせていただいております。また、条件はございますが、中古農機も補助の対象としてございます。本年4月1日から施行に併せまして農業関係者の集まりにおいて職員が随時説明を行い、ホームページにも掲載し周知を図っており、電話等により問合せ等をいただいておる状況でございます。なお、5月末までに2件の申請について交付決定を行っている状況でございます。これから多くの方にご利用いただいて、本当に金額は些少ですけれども、少しでも農業に対する意欲を失わないように町としても支援をしてまいりたいと、このように考えております。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)4月からのこの制度の開始だと思うのですけれども、この時点で既に2件交付決定もされているということでございました。小規模農家のみなさんが担っている役割は、町長の答弁にもありましたとおり単に経済的なことだけではありません。地域の景観を守り、農地の保水に貢献し、有害鳥獣の発生から町を守り、文字どおり地域を維持するための多角的な役割を担ってくれています。職員のみなさんには、既に補助金の内容について周知すべく、様々なご尽力をされているところです。農家の果たす役割の大きさをさらに発揮してもらうためにも、引き続きの周知をよろしくお願いいたします。また、外丸町長にはより一層の農家への支援策、引き続き研究いただくことを要望申し上げます。
次の項目に移ります。生産者への支援が必要である一方、米を利用する事業者からも悲鳴が聞こえてきます。米が入らないというものです。ある宿泊事業者は、従来から取引きをしている問屋から一切の米がないと言われた。町内の知り合いに聞いても、どこにも米がない。このままでは、宿泊するお客さんに米を提供することができない、そう話しておりました。米が作られている町の宿泊施設で提供する米がない、これは本当に異常な事態だと思います。逆に町内の宿泊施設で地元産の米を提供できるのであれば、これは観光的には非常に大きな利点になります。町内でも各事業者が営業努力をしてなるべく地産地消の食事を提供しようと頑張っています。ここで強調したいのは、旅行者の見る風景と旅行者が食べる食事を一体化させるというものです。自分たちが車窓から見た風景の中で作られている農作物を旅館や飲食店で食べることができる。消費者と地域の風景を守るという価値観を共有することがこれからの観光にはとても大事になってくると思っています。観光客は、温泉地に宿泊するにせよ日帰りで中之条ガーデンズなどに訪れるにせよ、必ず町の中を通ります。中之条町には、今も減ってはきていますが、農地がしっかりと残っている場所が多いわけです。目的地につくまでの時間も立派な観光です。観光客からは、農村の風景が美しいことが思っている以上に高く評価されています。最近では、農業を観光の目的とした農泊やグリーンツーリズムも盛んです。消費者が安心して安全な米や農作物を購入したい意向を増しているのと併せて旅行者も行った先の特産品やその土地でなければ食べられない食事を求めている。この流れは、コロナ禍を経て団体旅行から個人旅行に旅の形態が移っている今、ますます大きな流れになっています。もちろん地産地消といっても全ての食事材料を中之条町産のもので賄うことは不可能ですから、可能なものに限ります。町の生産者が町の飲食店や宿泊事業者に生産物を使ってもらう、これは生産する喜びにつながるのではないでしょうか。野菜や花卉など、様々な生産物でこの地産地消ができれば最高ですが、まずは米からこの取組を始めることはできないでしょうか。
ここで伺います。町内の米生産農業事業者と町内の米を利用する事業者を直接つなぐ支援を町が行うことはできないでしょうか。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)今、原沢議員から中之条町の食に関しての全般的な話から、米からできないかという話ですけれども、四万温泉、あるいは町の若い人がやっているようなお店なんかでも随分中之条町の野菜等を利用していただいております。聞いてみますと、もちろん安いしおいしいねと。四万温泉なんかは、お米なんかも随分中之条町の米農家さんと相対でやっておる状況も聞いております。十数年前においしい米づくり研究会というのを発足して、やはり中之条町もその花ゆかりという名前をつけましたけれども、米をブランド化して、ぜひおいしい米なので、町民はもちろんですけれども、来た人にもおいしいお米を食べていただこうというような活動を農家自らそういう実践をしてきてもう十数年たちます。ですので、今お話のようにこれからもやはり観光に力を入れている中之条町ですから、四万温泉あるいは沢渡温泉、六合温泉郷に来ていただいた方に地産地消ということの中で本当に中之条町のお米は、野菜はおいしいねと言っていただけるようなやはり事業者との連携をしていくのは本当に重要なことだというふうに考えております。
お尋ねの米の関係でありますけれども、議員のおっしゃるように、直接つなぐ支援とは町内の旅館等が米を確保しやすいように町内の米生産農業者とつなぐことだろうと思います。契約栽培のように販路が明確になれば生産者の収入の目途が立ち、消費する方も安定的に仕入れが可能となるため、両者におけるメリットも考えられます。なお、旅館などに納入する場合は、確保する量が多くなりますので、生産者をコーディネートするには生産量の把握が必要になります。そして、米をトラック等で輸送運搬すること、あるいは臭いや虫がつかないような品質管理等、クリアしなければならない事項もあります。既に自力で、先ほど申し上げましたように販路を開拓し、旅館等に納入している生産者の方もおりますけれども、中間的立場を担うべく業者が不可欠であるというふうに考えますので、JAやその他民間業者と協力できないか、これから情報交換も含めて情報収集をして調査研究をしていきたいと、そのように考えております。ありがとうございます。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)答弁いただきましたとおり、米を使う事業者にとって中之条町の米作りを身近に感じてもらう、これ本当に大事なことだと思います。ぜひ農業と観光分野を結び、JAなども巻き込んで前向きな検討を行っていただくことをどうぞよろしくお願いいたします。
引き続き、農業支援の中身について伺います。先ほども町内の米農家の声を取り上げましたが、一番の課題は田んぼの担い手がいなくなることです。法人化するなどして営農をしている方も多大な努力をされています。農業全体の経営を向上させるためには、どうしても政策の転換が欠かせないと思います。一方で法人化するに至っていない小規模農業事業者の営農をどうやって持続していくか、これは簡単な課題ではないと思います。町では、新規就農者への援助を手厚く行ったり、地域おこし協力隊員を活用したりしながら農業の担い手を増やすべく様々な努力をされていることは心得ております。小規模農業者への支援は、その規模や必要としている支援内容が様々であり、難しいことは重々承知です。しかし、ここを支援しないと町の農地はどんどんと荒れていってしまい、風景や治水、有害鳥獣の発生など様々な分野への影響が考えられます。未来戦略ミーティングでも耕作放棄地への対策について意見が挙げられ、耕作放棄地草刈り補助金の創設にもつながっていると思います。若い世代の方や移住された方の中にも農業や農地について高い関心を持っている方がたくさんいます。その方たちは、興味があっても耕せる農地も農器具も生産のノウハウもないというような、そういう方が大変多いわけです。片一方で農業への支援を必要としている人がいて、もう一方で手伝いたい、町の農業を応援したいという人がいる。この両者をマッチングすることが解決策の一助になると考えます。
ここで伺います。小規模農業者の営農を持続するために人材育成とともに地域内の多様な関係者との連携を強めることが必要と考えますが、町長の考えはいかがでしょうか。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)それでは、お答えをさせていただきます。
小規模な農業者の営農持続は、農村地域の景観を保ち、耕作放棄地を未然に防止する一翼になると考えております。そのため、小規模農業者農業経営支援事業補助金を創設するにあたり、町においては小規模農業者を認定農業者や認定新規就農者以外の農業収入の税務申告を行っている農家と定義して、耕作面積要件についてはその規定を設けておりません。その理由としては、中山間地域の兼業や高齢農家といった様々な経営体を支援したいと考えるからでございます。ご質問の人材育成と関係者との連携強化は、耕作放棄地草刈り補助金、これはもう先ほどお話ありましたように未来戦略ミーティングの若い方が耕作放棄地が増えるのを心配してお話をいただいたもので創設をさせていただいたわけでありましたけれども、これにおいては耕作放棄地の解消が町内で完結できるように農業者に限らず町内の方々の連携により実施できればと考えております。また、土に触れ合う体験を求め農家の手伝いをしたいと思っている方は一定数いらっしゃると私も思っております。以前に同僚議員の一般質問におきまして答弁させていただきましたように、手伝いをマッチングをするとなりますと気軽に親戚の家を手伝うようなものではございませんので、調査研究をする必要があるのかなというふうにも考えております。いずれにいたしましても、高齢化は顕著でありますので、既存の団体等でマッチングができるか、取組ができるかということを協力しながら検討を進めていきたいと考えております。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)この問題本当に簡単に解決策が見つけられるものではないと私も考えております。だからこそ様々な関係者や団体の方のお話を聞き、現状を把握してどうすれば解決が図れるのか真剣に考えていく必要があると思います。私も引き続きできる提案を見つけながらこの問題に取り組んでいきたいと思っております。当局におかれましても、より一層の深い検討をどうぞよろしくお願いをいたします。
芳ヶ平湿地群と野反湖における高山植物の食害への対策について
それでは、2つ目の質問に移ります。ラムサール条約に登録されている芳ヶ平湿地群ですが、豊かな生態系と併せて草津白根山系のダイナミックな景色や独特の植生が訪れる人を魅了しています。中之条町の誇るダム湖の一つである野反湖は、その周辺に300種類にも及ぶと言われる高山植物が確認され、天空の湖として多くの方を魅了しています。特に春のシラネアオイや夏のニッコウキスゲ、これはノゾリキスゲとも呼ばれています。また、コマクサは地元の中学生の植栽やボランティアの方による刈り払い作業などにより見事に咲き誇り、来町する方を楽しませてくれています。この野反湖には、ほかで見られなくなったからという理由でシラネアオイやニッコウキスゲ、さらにコマクサなどの高山植物を楽しみに訪れる方がとても多くいらっしゃいます。具体的には、尾瀬国立公園や日光国立公園でかつては見られたニッコウキスゲの群生、これが現地では鹿による食害で見ることができないというものです。尾瀬国立公園では、1990年代半ばからニホンジカが確認されるようになり、2010年頃から被害が拡大し、かつては黄色いじゅうたんと称されるほど咲き誇っていたニッコウキスゲの大群落がニホンジカの食害により激減し、もはや過去の風景になってしまったと言われています。現在では、食害対策として鹿柵の設置や補植などの取組が行われ、一部では回復の兆しが見られる場所もあるとのことです。日光国立公園の霧降高原キスゲ平園地では柵の中でないとニッコウキスゲの群生が見られなくなってしまったという報告もあります。
ここで伺います。芳ヶ平湿地群及び野反湖における高山植物の鹿などによる食害の実態はどうなっていますか。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)ご質問いただきました鹿の食害、これはもう原沢議員、本当に深刻な状況であります。この間も六合の方々とも話合いをする機会がありましたけれども、本当にこれは、鹿の状況は日本全国国立公園、あるいはそういうところを持っている市町村は本当に申告な状況であるということは原沢議員もご認識されていると思いますけれども、私どもも中之条町としても本当に深刻な状況だというふうに捉えております。
芳ヶ平湿地群の食害ということでありますけれども、芳ヶ平湿地群はラムサール条約連絡協議会や白根山系の高山植物を守る会等におきまして、ミズバショウなどのニホンジカによる食害が報告をされております。県林業試験場によりますと、平成30年からニホンジカの生息状況の調査を実施しており、きっかけは尾瀬ヶ原においてニホンジカによる食害でニッコウキスゲやミズバショウが激減している状況にあることから、第二の尾瀬としないために調査が始まったということでございます。野反湖における食害につきましても、野反湖自然休養林保護管理運営協議会等においてシラネアオイやノゾリキスゲ等のニホンジカによる食害が報告をされております。芳ヶ平湿地群や野反湖周辺では、標高や地形、地質、積雪深といった環境の違いに適応した様々な高山植物が生育をしており、生物多様性の観点からも重要度が高い地域であるため、ニホンジカの分布拡大により生態系や景観への影響を与えることが非常に懸念をされており、その対策を講じていかなければならないと考えておりますが、なかなか難しい状況にございます。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)本当に町長も深刻な実態ということでお話しいただきまして、実際にもう食害が始まっているということを確認いたしました。ミズバショウですとかニッコウキスゲなどが激減してしまった尾瀬のようにしないために今調査が始まったということでございました。
それでは、現在芳ヶ平湿地群や野反湖で行っている食害への対策内容はどのようなものでしょうか。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)現在行っている食害への対策内容といたしましては、芳ヶ平湿地群の大平湿原におきまして、令和6年度に協議会により鹿の侵入を防ぐネット柵を試験的に設置をさせていただきました。食害の防止の効果を検証するとともに、県において15台の自動撮影カメラによるカメラトラップ調査やGPSによる移動経路調査を行い、鹿の動きを監視しているところでございます。野反湖では、現在県が10台、国が5台の定点カメラを設置し、鹿の行動範囲の調査を実施しており、野反湖自然休養林保護管理運営協議会において情報を共有し、対策方法を検討しておるところでございます。鹿対策は、移動距離が長いため、中之条町だけで解決できる問題ではありませんので、国、県、関係機関が協力して行う必要がございます。根本的な対策を実施していくには、それぞれが財政的に難しい状況ではありますけれども、他地域を参考にして生態調査や防護柵の増設、捕獲等の対策を検討していきたいと考えております。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)大平湿原において、ネット柵が試験的に設置されたということです。積雪量も多く、気象条件も大変厳しい場所だと思いますので、ぜひ設置後の推移を検証していただきたいと思います。カメラやGPSも活用されているということですので、各協議会にてしっかりと情報共有をして有効な対策を検討していただきたいと思います。しかし、現状のままですと鹿の食害はより一層加速度的に広がっていくことが予測されます。鹿の天敵が不在であること、狩猟者が減少していること、暖冬による越冬率の向上などを要因としてニホンジカの生息数が増加しています。また、ニホンジカは繁殖力が非常に高く、一度増え始めると個体数の増加が加速します。また、森林伐採や林道整備などによる移動経路の確保、気候変動による新たな生息地の拡大などが挙げられます。そして、鹿は特定の植物を好んで食べるため、その植物群落は集中的に被害を受け、短期間で大きな影響が出やすいと言われています。このように鹿の食害は、生息分布域の拡大と個体数の増加による植生への圧力となって、一度始まると非常に早いスピードで進行し、手遅れになる前に早急な対策が求められます。
ここで伺います。食害への対策として、今後考えられることはありますか。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)食害の今後の対策ということはいかがなものかという話ですけれども、今後の食害への対策内容は、尾瀬や他の地域において実施している事例を参考にいたしますと、防護柵の設置や個体の捕獲等が挙げられます。ある程度の効果が見込める状況となれば範囲を広げていき、効果が低いとなれば別の対策を考えていかなければならないと思われますが、国や県におきましても財政的に非常に厳しい状況にあるということもございます。広域的に防護柵の設置や鹿の頭数制限等も含めて今後専門部署との調整や検討が課題となってくると思われますので、町としても対応してまいりたいと考えております。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)答弁いただきましたとおり、防護柵の設置と個体数の調整の組み合わせが最も効果が高いものと思われます。繰り返し答弁でも触れられておりますとおり、国も県も自治体同様に財政的には非常に厳しい状況にある、そのことも理解をいたします。既に各協議会などで連携をしていることと思いますが、それぞれの役割を協力しながら果たしていくことで重層的に対策を講じていくことが欠かせないと思います。
ここで伺います。林野庁や環境省、群馬県林業試験場との連携をどのように強めていきますか。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)国、県等の連携強化につきましては、各協議会におきまして定期的な会議を重ね、情報を共有する中で様々な問題を中長期的に考察し、国や県、中之条町及び草津町の関係機関はもとよりボランティアガイド協議会や鳥獣保護員、自然保護指導員、自然公園指導員、六合山岳会、六合区長会等々にご協力をいただき、知恵を出し合いながら問題解決に向けて連携を深めていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)答弁にありましたとおり、国や県だけではなく隣接する草津町、そして住民の理解と協力が欠かせないと思います。六合の誇る芳ヶ平湿地群や野反湖、住民の協力を得ながら守り後世に伝えていく、この取組をぜひ根本的に強化していただきたいと思います。また、問題解決には財政的な困難が伴うことも今回の答弁からも深く理解をいたします。国立公園なので、国民共有の財産として入園料無料の原則があることも理解をしております。それゆえ、駐車場を有料化することや来場者に対策の経費を負担してもらうことを、これも難しいというのが原則だというふうに思います。しかし、国立公園であっても来訪者が訪れる目的とする高山植物そのものの存在がなくなってしまえばその魅力は減ってしまい、訪れる人の数も応じて減少することが当然予想されます。そうならないためには、訪れる人に受益者負担を求めることは何ら不適切ではないと考えます。既に野反湖で実施されているトイレ利用時の協力金のような取組をより一層広めることはできると思います。また、先ほどから参考事例に挙げている日光や尾瀬の国立公園など、駐車場の利用料を求めている国立公園もあります。食害の対策に必要な費用をそれだけで賄うことは現実的ではありませんので、ほかにもクラウドファンディングの活用や企業版ふるさと納税の活用などを検討できるのではないでしょうか。そして、地元の方や野反湖を、芳ヶ平を愛する方たちは柵の設置や下刈りなどの作業には喜んで応じてくれると思います。住民やボランティアの方の力も借りながらこの問題に一丸となって取り組んでいけるよう、町としての取組を強めていただくことを要望して、2つ目の質問項目を終えます。
カスタマーハラスメント、特に町職員への影響と対策について
では、最後の項目に移ります。顧客や取引先が理不尽な要求をするカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラへの対策が急務となっております。労働者を保護するために全企業に対策を義務づける改正労働施策総合推進法が6月4日に成立しました。中之条町でも昨日本会議に条例が提案されたところです。住民や取引業者と日常的に接しているのが窓口対応をはじめ接遇を行っている役場の職員です。職員が安全で安心して日常業務に当たれることがそのまま町民生活の向上につながるものと思います。
まず、伺います。町職員に対するカスタマーハラスメントに値する行為の発生事例を把握していますか。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)先ほどの鹿の食害の関係で、ちょっと一時訂正をさせていただきたいと思います。原沢議員からお尋ねありました食害の対応ということで、野反湖で国、県の定点カメラを設置しているという答弁をさせていただきましたが、協議会の名前ですので、間違っているといけませんので訂正をさせていただきますが、「野反湖自然休養林」って申し上げましたけれども、「湖」がないので、「野反自然休養林」ということでご訂正をお願いできればと思います。よろしくお願いします。
それでは、カスタマーハラスメントに対する事例把握をしているか。これは、社会的に今ハラスメント行為が非常に問題化になっているということはもう原沢議員もご承知のとおりだと思います。そのことによって精神的、身体的苦痛、あるいは体調を崩されているという方もおりますので、そういったことに今回条例を出させていただいて、制定をさせていただきました。町職員に対するカスタマーハラスメントに当たる行為の発生事例を把握しているかというお尋ねでありますけれども、カスタマーハラスメントに値する行為に限らず苦情やクレームは役場窓口だけでなく、各町有施設において事案が発生し、また発生する可能性はございます。そうした事案が発生した場合には、その内容や対応の経過などについて、その都度報告を受けておりますし、複雑な事案等の場合には今後の対応も含め関係職員と相談しながら対処いたしております。そういう意味では、いわゆる報告、連絡、相談という形で発生事案の把握に努めておりますし、加えて確認についても指示しているところでございます。その中で事案によりましては、先ほど申し上げました苦情やクレームに端を発し、カスタマーハラスメントに発展していく場合もございます。度を超えた悪質な行為につきましては、警察をはじめ関係機関と連携し対応していく場合もございますし、事案の内容によっては法律の専門家等と相談をしながら対処していくなど、発生事案により適切に対応を行ってまいります。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)様々な業務を担う町職員のみなさんの安全、安心、これがカスタマーハラスメントのような行為によって安心が保たれなくなるような事態が起きないよう様々対策が取られ、状況に応じて警察や法律の専門家などとも相談しながら対処を行っているということでした。
それでは、現在町職員に対するカスタマーハラスメントへの対策として行っていることはありますか。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)町職員に対するカスタマーハラスメントへの対策について行っていることはあるかというお尋ねであります。カスタマーハラスメント対策に関しましては、行政に限らず町全体の問題との認識から、今回の6月定例会議において条例の制定につきまして提案をさせていただきました。提案説明でも申し上げましたとおり、カスタマーハラスメントが社会問題化する中において、顧客等からの過度な要求等は苦情やクレームの範囲を超え、経済活動全体に関わる重大な問題であると認識をいたしております。何より人口減少により働き手の不足が深刻化している中にあって、カスタマーハラスメントを起因とした行為が結果として事業者の経営に多大な影響を与え、さらに就業者の心身に深刻なダメージを与えることは事業活動の継続そのものを困難にする要因にもなりかねません。こうした状況を勘案し、カスタマーハラスメントへの理解が広く周知され、豊かで安心した町民生活が送れるよう努めてまいりたいと考えております。町職員の対策ということですが、役場も一つの事業所でありますので、この条例が職員の指針となればというふうに考えております。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)このカスタマーハラスメント、非常に重大な問題なので、条例も提案されたということでした。本当に重要なことであり、町役場の職員だけでなく町の事業者で働く人たちが安心して働き続ける環境をつくっていく必要があると私も考えております。しかしながら、条例ができたから即カスタマーハラスメントが発生しなくなるというものではありません。大事なのは、ハラスメントが発生しないように具体的な対策を講じていくことだと思います。接遇に当たるにせよ、管理者として働くにせよ、職員がハラスメントに対して正しい理解と対応策を日常的に心得ていることが大事だと考えます。また、カスタマーハラスメントへの対策として、通話の自動録音サービスが有効だと言われております。
ここで伺います。今後職員研修を行ったり通話の自動録音サービスを取り入れたりする予定はありますか。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)原沢議員おっしゃるように、条例を制定したからカスタマーハラスメントがなくなるというふうなことはなかなか難しいのかなというふうに思います。ただ、それに対応する手立ては考えていかなければならない、そんなふうに思っております。セクハラ、パワハラのハラスメントも現在では多岐にわたっておりますけれども、カスタマーハラスメントではありませんでしたが、昨年度、職員を対象にハラスメント研修を実施をいたしました。条例などの制度整備と並行して研修の必要性も感じておりますし、こうしたハラスメント研修のメニューの中にカスタマーハラスメントを取り入れていくことも検討してまいります。先ほどご質問いただきました職員に対するカスタマーハラスメントへの対策という点でもこうした研修は有効であると考えております。詳細は分かりませんが、ある行事では事業者に対して既にこうした研修を独自で行ったというような話も聞こえておりますので、役場職員についても例えば県や町村会等が主催する研修に参加したい意向があれば、積極的に参加を促すよう配慮していきたいと考えております。
通話の自動録音につきましては、ある一部の電話に限っては録音機能を備えたものもございますが、例えば役場庁舎内の電話端末に機能を導入した場合、費用面等において高額となってしまうと思われますので、検討が必要であると考えております。ただし、電話番号履歴は現在でも確認できるようになっております。また、役場庁舎1階等には窓口業務等へのトラブルへの対応として数台の防犯カメラを設置しており、常時録画、録音をしておりますし、防犯カメラにつきましてはセキュリティー面も含め役場庁舎以外の施設でも導入しているところでございます。
以上です。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
○1番(原沢香司)繰り返しになりますけれども、町民の生活向上には働くみなさんが安心であることが欠かせません。ぜひ職員のみなさんが安心して働き続けることができるよう、可能な限りの対策を講じていただきたいと思います。役場の取組というのは、やはり町の事業者の一つの指針になると思いますし、役場がやっているのだからうちの事業者でもこういった取組を進めようというモデルケースになると思いますので、引き続き可能な限りの対策を講じていただくことを要望申し上げまして私の一般質問を終わります。ありがとうございました。