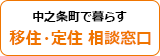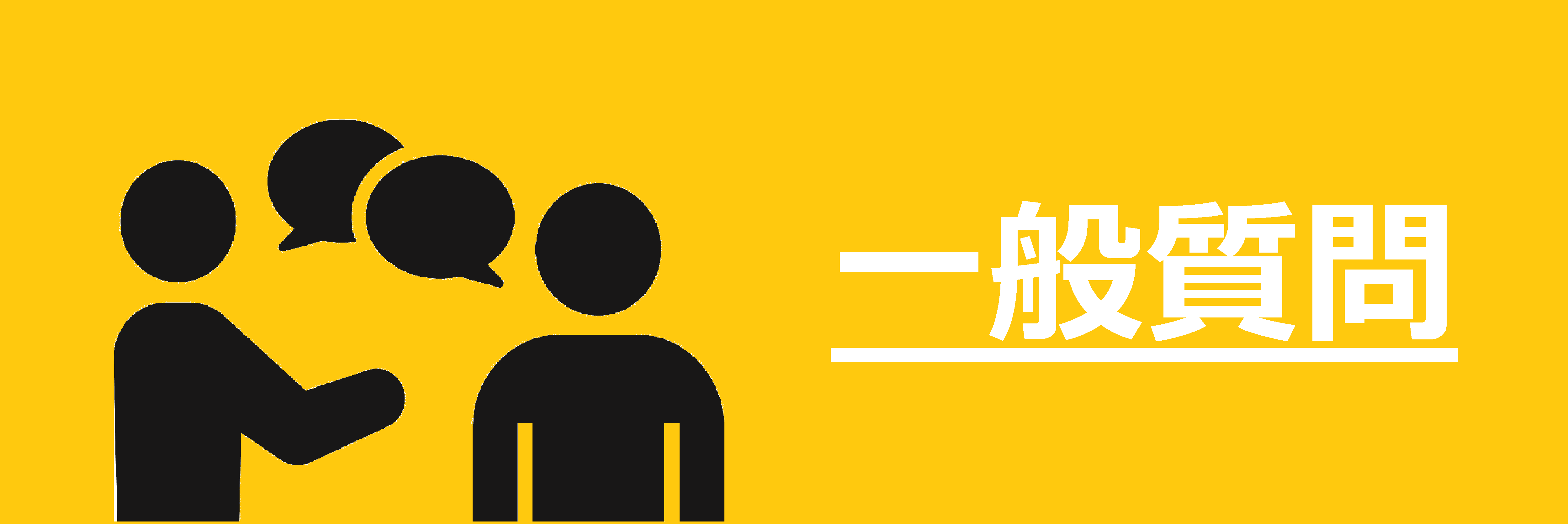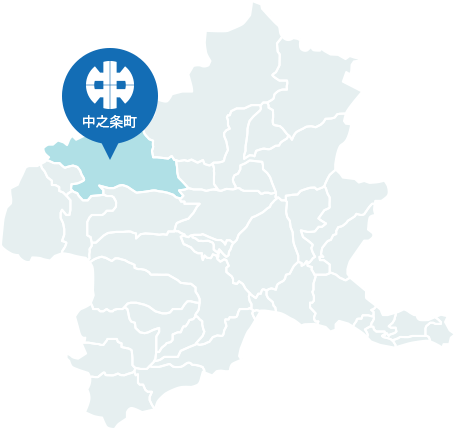本文
令和7年3月定例会議 一般質問(佐藤力也議員)
03 6番 佐藤力也議員 令和7年3月定例会議一般質問
〇6番(佐藤力也)みなさん、こんにちは。議長の許可をいただきましたので、令和7年中之条町議会3月定例会議一般質問を行いたいと思います。申し遅れました。議員番号6番、佐藤力也です。よろしくお願いいたします。
今回の質問でございますけれども、2つの大項目でございます。まず、1つ目は安全・安心な町づくりについて。そして、もう1つが観光振興と町の経済活性化についてでございます。
〇安全・安心な町づくりについて
それでは、まず初めに安全・安心な町づくりについてご質問させていただきます。まず、消防団支援といたしまして、消防団支援隊についての進捗についてお伺いをしていきたいと思っております。ですが、今回消防支援隊の設置におきまして、その進捗についてお伺いする予定だったのですけれども、昨日町のほうより中之条町消防団支援隊設置条例の制定についてということで議案が上程されてございました。ですので、その確認ということで内容を見たところ、1点だけ今後検討していただきたい点がございましたので、その点について1つだけ質問させていただきたいと思います。この条例の最初の項目にある設置目的には、中之条町内で発生する火災の被害の軽減及び地域消防力の強化が目的だとうたわれております。条例の中身については今後細かい修正が必要になることも出てくるかもしれませんが、特段指摘する点はないと考えます。しかしながら、消防団の活動は火災発生、有事のみならず、平時の予防消防も非常に重要な活動と考えております。この点について1点だけ検討していただきたい点があるので、申し上げます。
それは、火防まわりです。火防まわりは、これまでも消防団が大事な活動の一つとして、予防消防としてやってきた活動でございます。そういった消防団の負担軽減、そして地域の方とのコミュニケーションを取りつつ、火の取扱いへの注意喚起と一緒に消火器や火災警報器の設置の確認を今までどおりしていただき、設置が確認された場合には交換時期や動作確認の指導を、また設置がない場合は設置の推奨及び取り付け交換作業の補助などをしていただければ、高齢者や体の不自由な方も助かるのではないでしょうか。
昨年の12月議会での一般質問で、私は火災警報器の設置における支援はできないかと町長に質問をさせていただきました。町長からは、財政的支援は難しいが、設置の補助については検討する旨の答弁をいただきました。その一つの方法として、支援隊による火防まわり参加をぜひ検討いただきたいと考えますが、いかがでしょうか、町長の見解をお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)支援隊の活動についてのお尋ねをいただきました。消防支援隊、これは昨日提案させていただいたものに書いてあると思いますので、佐藤議員、十分ご理解をいただいておるということを確認させていただきながら答弁をさせていただきます。
町内で発生する火災、それから災害等、地域消防力が低下しているという状況の中にあって、消防団員の方々、本団を中心にこれから消防力、防災力を維持していかなければならないだろうという観点の中で支援隊という考え方があったのだと思います。それが2年間かけて今回上程をさせていただいたということでございます。昨日の条例の中にもありましたけれども、あくまでも後方支援、消防団の中にあっての指示をいただいた後方支援という位置づけでありますのは確認をさせていただきたいと思います。そういった中で火防まわりをどうとかこうかと、今お尋ねいただきました。これにつきましても消防団員、消防団がしっかりと2年間かけて、あくまでも消防団の組織の下部組織として消防団から依頼のあったものについて後方支援していただきたいのだということで進めてきました。消防委員会にも2月にそれを諮っていただきまして、確認をしていただいて、今回の条例の制定ということになりました。中身については、4月1日から条例が施行されてから修正を加えることはもちろんあると思いますので、それはまた消防団の意思を十分尊重しながら考えていかなければならないだろうというふうに考えております。
また、火災報知機のお尋ねありましたけれども、これについては12月定例会で述べさせていただきましたが、実施をされている県内の自治体に状況を確認し、郡内の町村や吾妻広域消防本部と連携を図りながら研究をしてまいりたいと考えておりますが、また火災報知機につきましては、県内自治体の状況を確認したところ、取付け、取替え支援につきましては、消防職員の支援となっており、吾妻広域消防本部に問い合わせたところ、現状ではなかなか難しいというお考えをお聞きをいたしました。よろしくお願いを申し上げます。
〇議長(安原賢一)6番、佐藤さん
〇6番(佐藤力也)ご答弁ありがとうございます。
町長のおっしゃるとおり、この条例制定につきましては、長い年月かけて消防団、そして町消防委員のみなさんが練り上げた条例だと私も承知しております。ただ、もしこれから予防消防という意味でそういった追加というのですか、必要とあれば、これからも検討していただくことはできないかという要望でありというところですので、ここでどうこうというものではなくて、これから活動していく上でそういった新しい課題とか出てきたときには対応していただければいいかなという要望でございますので、そういったことで受けていただければいいかなと思います。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)要望ということで今ご提案をいただきましたが、あくまでも消防団の考え方を尊重するということが第一義でありますので、佐藤議員からこういうお話がありましたということは消防団、本団を含めて、団員のほうにお伝えをさせていただきたいと思います。
〇議長(安原賢一)6番、佐藤さん
〇6番(佐藤力也)よろしくお願いいたします。
続きまして、消防団応援の店の事業というところで、消防団応援の店事業のこれまでの町の取組についてお伺いしていきたいと思います。まず、この消防団応援の店の事業というところは、いつからどのような目的でこの事業を開始したのか、事業内容の説明をお願いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)佐藤議員も加盟をされていると思いますけれども、内容や目的は理解されていると思いますけれども、当事業は消防団員を、地域を挙げて応援し、消防団員の増加、地域力、防災力の充実、強化を図ることを目的に平成29年度に群馬消防団応援の店の募集があり、町として令和2年度に中之条町消防団応援の店の募集を行ってございます。
〇議長(安原賢一)6番、佐藤さん
〇6番(佐藤力也)続いて、質問いたします。
これまでの成果について、募集当初からこれまでの協力店の登録数の変遷を含めてお伺いいたします。
〇町長(外丸茂樹)消防団応援の店は、日頃お仕事を持ちながら、ご家族のご協力の下に訓練等に従事し、火災など、いざという時に活動していただく消防団員やご家族を含めて割引サービスなどを実施いただいている店舗でありますけれども、県内でも約280店舗、町内でも40店舗ほど登録をいただいております。登録数につきましては募集当初から変化はありませんが、引き続き周知を図ってまいりたいと思います。
〇議長(安原賢一)6番、佐藤さん
〇6番(佐藤力也)丁寧な説明、ありがとうございました。
このデータは前回のデータとそう変わっていないのかなというところでございますけれども、なぜそういった確認をさせていただいたかといいますと、この消防団応援の店について、町長にも以前一般質問でやらせていただいたので、ご承知はしていると思うのですけれども、令和5年12月の定例会議で初めて質問させていただきまして、その後令和6年3月の一般質問では、個人でアンケート調査を行って、その結果を町のほうに提示させていただきました。そのとき、町長からは、全国的にこうした店舗が広がっているということは成果が上がっているものかなと理解しており、中之条町にとってもいただいた情報を踏まえて、今後また精査して研究をしてまいりたいと考えているとの答弁をいただきました。しかし、その後約1年が経過しようとしておりますけれども、特段町の動きはなく、アンケート調査にご協力いただいたお店の方からも「まだ町から何の連絡も来ないけれども、どうなっているのか」といったお話を多数いただいております。その当時、あのアンケート調査データをお渡ししたのですが、もともと登録しているお店の内容確認ですとか、まだその応援の店の存在すら知らなかった店舗さんもたくさんいらっしゃったので、もうそういった時に当初の目的ということで、もう一度募集をかけていただきたいというお話をさせていただきました。恐らくホームページですとか町報には少し載っているのかなとは思うのですけれども、待っている店舗さんは結構いらっしゃいますので、丁寧な説明をもう一度お願いしたいと考えておりますが、これまで町といたしまして、そういった動きがなかったのはなぜなのか、その理由をお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)消防団応援の店につきまして、佐藤議員からアンケートにつきましては大変ありがとうございました。
アンケートの回答の中には否定的な意見もあり、あくまでも自主的にご協力をいただいておる状況になっております。現在加入していただいている方につきましては、次年度団員章の更新に併せて周知を行います。また、町内で新しく店舗を開業された方もおられますが、町ホームページや広報等において、引き続き周知を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(安原賢一)6番、佐藤さん
〇6番(佐藤力也)ありがとうございます。
まず、この質問で周知方法というところで、のぼり旗の配付だったり、幾つか提案をさせていただきました。特に団員の方がこの事業を知らないというところがこの事業があまり進んでいかないところなのかなと思いまして、先ほど町長も団員に対しての周知を行っていただけるということを申していただきましたので、ぜひよろしくお願いいたします。
それでは、次の質問に移りたいと思います。次は、防災計画についてお伺いをいたします。まず初めに、この防災計画について、中之条町では町全体の防災対策として、中之条町地域防災計画を作成しております。この計画は、災害対策基本法第42条に基づき、町内で発生し得る自然災害、地震、風水害、土砂災害などへの対応を定めて、具体的な内容としては、災害時の組織体制、避難場所の指定、住民への情報伝達手段、防災備品の備蓄などが含まれております。今回は、その計画の一環として備蓄米の取組についてお伺いいたします。
まず、初めに町では、これまでに備蓄米に関して具体的にどのような取組を行っていたのかお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)防災計画の中の備蓄米についてのお尋ねをいただきました。町では、防災用の非常用備蓄食につきましては、防災計画により必要数を確保し、計画的に更新を行っております。令和5年度米の利用促進として、町ブランド米の花ゆかりをアルファ化米にし、災害用備蓄食として地産地消に取り組んでおります。また、令和6年6月に町内の米農家でつくる中之条町おいしい米づくり研究会と米穀の調達に関する協定を締結をさせていただき、大規模災害発生時には会員保有の備蓄米の提供を受けられるようにお願いをし、対応しているところでございます。
〇議長(安原賢一)6番、佐藤さん
〇6番(佐藤力也)ありがとうございます。
備蓄米に対しての町の取組について説明をいただきました。今後のその備蓄米に関する計画というところは今までどおりということなのでしょうか。特にこれから新たな取組を行っていくこと、改善することというところがあればご回答いただければと思うのですけれども、なければいいです。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)今後その備蓄米について何かお考えがあるかというお尋ねをいただきましたけれども、大きく話しますと、国では100トンの備蓄をしております。年間20万トンずつ、一番最初にやったものは5年たつと20万トン、牛の餌、食料に、飼料米として廃棄をしています。これは、国家が国民に、もしも米が足りなかったときには困るという安全な主食の確保という観点で行っているものだと思います。
今回特に変わったのが農林水産省がこの令和の米騒動で高騰する米に対して、初めてその運用を変えて、21万トン放出するという報道がされております。しかしながら、まだそれでも恐らく今年の秋には米が不足するだろうという予想が立っております。私も最近1週間に1回はベイシアとかそういう小売店へ行きますと、行くごとに上がってきています。まだ高く上がっている、高値になっているという状況があると思うのです。この状況は何が起因するかというと、農政の、やはり大きな誤りもあったのかなと、お金をかけて転作をかけて、転作を奨励して、作付面積を減らしていったと、そこに来て、コロナ、あるいは物価高騰に加えて、小さい農家でも米を作るの、もうこんな金かかるのなら、やめようというような状況が出てきたのだと思うのです。ですので、私の考えとすれば、今回小規模農家に対する支援、本当に些少ですけれども、こういった形の中で中之条町の中山間地における耕作放棄地を少しでも減らして、中之条町で米を1粒でも多く作ってもらえるような、そういう支援をすることが、ひいては米の備蓄米というようなことにもつながってくるのではなかろうかと、こんな考え方を持っています。あわせて、農業というのはご存じのように耕作放棄地が増えれば増えるほど有害鳥獣、あるいは土砂崩れがあります。こういったものを本当に中之条町の農家の方々高齢化もしています。労力はありませんけれども、こういった耕作意欲を少しでも保ってもらうようにすることも備蓄米確保の一つの考え方かな、こんなふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。
〇議長(安原賢一)6番、佐藤さん
〇6番(佐藤力也)町長のお考えをお伺いいたしました。この分野については町長に勝る人はいないかなと思っておりますので、これ以上私からは言うことはないのですけれども、本当に町長のおっしゃるとおりで、これは本当に国策として進めていかなければいけない問題だというふうに認識をしております。そこで、当町の町の中の問題といたしまして、これから1つ質問させていただきたいのですけれども、これは提案になるのかなと思うのですが、現在備蓄米というところは先ほど町長からもご説明がありましたが、中之条町で収穫されたブランド米花ゆかりを150キログラムを使って、それをアルファ化米として加工して備蓄しているということですけれども、先ほども町長もおっしゃっていましたけれども、最近の米不足問題、それに伴う米の価格上昇への対応策として、今後ブランド米として、その基準に満たないお米ももちろん、花ゆかりにならないお米もあると思うのです。そういったお米での対応というところも考えていかれればいいのかなと思うのですけれども、また新米を米不足時の対応策と災害時の備蓄用として、町として独自に一定量備蓄し、こちらやはり保存する状態ですとか場所ですとかいろんな課題はあるかとは思うのですけれども、これからの対応を考えていくということで、その年の米の流通状況に応じて町民に安価で提供したり、そこで余ったお米をアルファ化米として利用するという、そういったサイクルをしていくという考えもあるかなと思うのですけれども、いかがでしょうか、町長の見解をお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)米の花ゆかりにならなかったお米の利用ということも含めまして、中之条町の現在耕作面積は年々減ってきております。その令和の米騒動でありますけれども、では果たして米の生産農家に所得が増えているのかということが反映させているのが米の店頭で売っている価格がそのまんま反映されているということはなかなか米農家としてはないのだと思うのです。昨日も福田議員からもお尋ねありました、機械が非常に高騰している、併せて肥料が高騰している、農薬が高騰している、燃料も高騰しているということになりますと、それに見合ったお米を作ろうと農家の方は努力をして、一等米で80以上の食味を持って、花ゆかりとして生産をして、おいしい米を作っていただこうということで農家は取り組んでいるわけでありますから、昨年のことを例にとりますと、猛暑に加えまして、白濁米ができた。それに加えまして、カメムシ、この被害が著しくなっております。やはりこれにかける農家の選別費用、これも増加してきています。ですので、この令和の米騒動というのはちょっと不思議なところがありまして、なぜそれが農家のほうに所得として反映されていないのか、けれども店頭に行けば倍もする、しかも輸入米がどんどん今入ってきているという状況になりますと、米農家のことを考えたりしますと、安い米をそういうふうにするのがいいのでしょうけれども、米農家のことを考えれば、ある程度の適正な価格を維持できるような農政、あるいはそういうことを考えていかなければならない、そういったことを考えると、どのくらい米を町として、こんな小さな町でストックして、備蓄米にするのだと、それを確保しておく施設も必要でしょうし、米の農家もそこへ預けられるような米を供出できるものか、併せて災害が起きたときは協定を結んでいますから、協力をしますよという形で、米の農家の方々もやっぱりそれなりの価格を保たなければならないので、町とすれば安い米を集めて、それをストックしておいて出せばいいのでしょうけれども、やっぱりそのへんのところが安い米というのもあるのでしょうけれども、そのバランスも含めて、小さい自治体として、その備蓄米を保管するにはやはりいろんなハードルが高いのではないかというふうに考えておりますので、ご提案は確かに納得できるところもありますけれども、これはやはり国策としてやっていることでありますので、我々小さい自治体としてはいろいろな方策を考える中において、備蓄米についてはちょっとハードルが高いからと、こんなふうに思っています。
〇議長(安原賢一)6番、佐藤さん
〇6番(佐藤力也)ご答弁ありがとうございました。まだまだ私も勉強不足でございますので、町長のおっしゃるとおりだなと納得するわけでございますけれども、いずれにせよ農家、農業支援、新規就農者支援というところ、今回も重点交付金のところで農家支援をやるということで上程されていますけれども、今後も農家支援のところをしっかりと力を入れていただければと思います。よろしくお願いいたします。
続きまして、防災計画の重要性についてご質問させていただきたいと思います。町では、町全体の地域防災計画とは別に、各行政地区単位で自主防災組織として住民が主体となって地区防災計画の策定を推奨されています。これにより各地区の特性や課題に応じた具体的な防災対策を講じることが可能になり、そこで避難行動要支援者への対応や自主避難計画を重ねることによって、災害時の犠牲者を一人でも減らすことにつなげていこうとしているわけですが、本当に重要なのはその後の訓練にあると私は考えております。これまでに地区防災計画を策定した行政区が次の段階として避難訓練や避難所体験などを行ってきておりますが、そういった実際に行動することが何より大切だと考えます。そして、全ての行政区において、速やかに地区防災計画の策定、各避難計画の策定が進み、避難訓練実施に進んでいくために一番重要なことは町民のみなさん一人一人が災害に対しての怖さを知り、自分の命は自分で守るという意識を持つことだと考えます。防災意識の向上こそが様々な計画策定のスピードを上げ、避難訓練というところにつながると考えます。そのために何をしたらよいのか、その一つの手段として災害被災地復興ツアーを提案いたします。災害被災地の視察に重点を置いた復興支援と災害の恐怖、厳しさを体感し、防災への意識を高め、訓練や万が一の有事に備えるためのツアーです。テレビや新聞、インターネットでのニュースで災害被災地の様子や情報は町民の皆様もおおむね知っていることと思いますが、実際現場に行った方、避難所の様子を見た方にお聞きしますと、その状況は予想をはるかに上回る悲惨な状況、厳しい状況だと言います。テレビでは、人道的配慮から報道規制がかかり、あまり悲惨な状況は流せないのだそうです。百聞は一見にしかずといいます。被災地の実際の状況を見て、感じて、聞いて、それを一人でも多くの町民に伝えていただくことで、防災意識の向上に役立つと考えます。
参加者については、まず災害時にリーダーとなる行政区の区長様や地区防災士の方の参加を募り、その後状況によって一般町民の募集を考えるやり方がよいのではないかと考えます。また、町からは防災安全課危機管理係の方などの同行が加われば、さらにその効果は増すものと考えます。防災に力を入れていくと、力強くおっしゃっている外丸町長、ぜひこの計画を実行に移していただきたいと考えますが、いかがでしょうか、町長の見解をお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)当初、最初の初日にお話をさせていただきましたけれども、今現在大船渡市でまだ鎮火のめどが立たないというような状況で、15道府県から2,000人を超える緊急援助隊が派遣をされております。当吾妻郡広域町村圏振興整備組合の消防職員も第1班が28日から4日間行きまして、本当に危険を顧みず消火活動していただいたという報告を隊長からお伺いいたしました。今少しで死んでしまうのではないかというような状況の中で消火訓練をしていただいたそうであります。あわせて、今第2便が向かっておりますけれども、また鎮火のめどが立たないという状況であります。
以前、東北大震災で吾妻広域消防がやはり緊急援助隊で向かいました、幾日もかかりましたけれども。それもやはり消防本部からの報告聞きますと、想像を絶するような光景を目の当たりにするという状況を聞きましたけれども、行った消防隊員も本当にストレスを感じるような、自分の気持ちがとても抑え切れないような、そんな状況になったのだという話を聞きました。恐らく佐藤議員のおっしゃることも分かるのですけれども、この震災復興ツアー、これを計画としてはどうかというお話でありますけれども、能登半島地震の対応といたしましては、復興支援として、職員の派遣を行ったり、募金等を行ってまいりました。町では、令和2年度から防災に専門的な見識のある職員を配置し、各地域において避難所運営訓練、防災会の設立や自主避難計画の作成に向けて、地域の方々のご協力の下に取り組んでまいりました。
地区防災会につきましては、72地区、率にして83%の地域において組織設立がなされており、自主避難計画の策定につきましては42地区、率にして48%の地域で策定をされております。
お尋ねの震災復興ツアーということでありますけれども、受入れ等、様々な問題がございますし、能登半島の復興復旧がなかなか進まないということがマスコミでも報道されております。子どもさんなんかもまだまだ学校に安心していけない、どうして家が再建できないのだろうかというような悲痛な声がマスコミを通じて現在まだ進んでいます。恐らく能登半島という地形の状況もあるのかと思います。それに加えて、集中豪雨でまた第2回目の災害を受けたと、心が2回折れたという話も聞いております。そういったことを考えますと、いまだにこの寒い中、我々はいいのですけれども、仮設住宅にご不自由な生活されている方まだまだ大勢いると思います。そして、また復興に携わる自治体職員、あるいはだんだん、だんだん時間がたって薄れてきているように思われますけれども、まだまだボランティアがあそこへ入って、一生懸命関係の方々と復興に取り組んでいます。そういった思いをする時に、議員提案の震災復興ツアー、これについては現在検討する考えはございません。
〇議長(安原賢一)6番、佐藤さん
〇6番(佐藤力也)まず、初めにお断りしておきたいのですけれども、担当課の職員の方とは今回ツアーについてお話をさせていただいた時に、能登の話もさせていただきましたけれども、今回能登とは限定しておりませんので、そこだけはご理解いただければと思っております。
このツアーについて、本当に時と場所、どういった状況でやるかというところももちろん非常にデリケートで大切なところになるかと思います。今の段階では検討はしないということでございますが、そういったことで町長がお考えならしようがないかなと思います。ただ、今まで防災安全課の職員の方による地道な、そういった災害時の状況の説明ですとか、避難行動、避難所開設の訓練ですとか、そういったところの努力があって、今避難訓練を行えている行政区が増えてきているということは承知しておりますので、そういったところの横の連携といいますか、いろんな方の情報、協力というところをこれから町としても募っていき、そういった普及に努めていただければありがたいかなと思います。そういう私が住んでいる沢田14区もまだ一番最初の連絡網しかできていない状況ですので、そういった中でどうしたら本当にその計画が進んでいくのかというところも相まって今回の質問に至ったわけですけれども、そういったところをちょっと理解していただければうれしいかなと思います。よろしくお願いいたします。
続きまして、通告にあります3番、防犯対策について質問させていただきます。令和6年12月に防犯対策について質問をさせていただきました。その中で、支援の拡充を要望いたしましたところ、本3月議会に上程されました令和7年度当初予算案に防犯カメラについて1万円まで引き上げるという提案を町からいただきました。そういうことについては、まず感謝申し上げます。ありがとうございます。
しかしながら、役場に申請に行く手間と時間と交通費を考えると、1件につき、防犯カメラ以外の部分で2,000円の補助はちょっと少ないのではないかと、せめて3,000円ぐらいに上げて欲しいといった声も数多く聞かれます。今ガソリン代も大分上がっていますし、バス代もしかりで、そういったことを考えますと、2,000円ではちょっとという声を結構聞くのです。また、補助金を設立してまだ1年足らずということかもしれませんが、その補助金自体を知らないという方も結構まだ多くいらっしゃるようです。そこで、防犯対策補助金について関連して質問をいたします。
まず、利用実績について報告をお願いいたします。そして、その後この補助金の周知をどのように行っていくのかを伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)防犯対策のお尋ねでありますけれども、防犯対策補助金につきましては、令和6年度に犯罪の抑止と安全で安心なまちづくりを推進するため、防犯対策に係る機器等の設置につきまして補助をさせていただきました。議員おっしゃるように、ガソリン代も上がっていますから、2,000円というのは少ないというご指摘はそういう意見もあるのだろうなというふうに受け止めさせていただきます。初めてつくったものですから、これからその事業実績等も踏まえて、また検討する余地はあろうかと思います。
利用実績ということでございますけれども、3月1日現在で12件の申請がございます。詳細につきましては、防犯カメラ3件、センサーライト5件、迷惑電話防止機能付電話機3件、補助錠1件ということでございます。
それから、補助金の周知というお尋ねでありますけれども、令和6年度当初に毎戸に配布をされました個人向け補助金等一覧に掲載させていただいております。また、町ホームページにも掲載をさせていただいております。広報によりお知らせをいただきました。区長会議でお知らせさせていただいております。それについてもまだご存じない方がいらっしゃるとすれば、今後も周知については進めていきたいと、このように考えております。よろしくお願いいたします。
〇議長(安原賢一)6番、佐藤さん
〇6番(佐藤力也)この周知について、前回もいろんな周知情報をご提案させていただきましたので、活用いただければと思います。特に防災無線やデータ放送、そういったところの活用をぜひご検討いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
関連してなのですけれども、この申請について、役場に申請書を持ってくるということがほとんどなのかなと思うのですが、今登庁しなくても、登庁というのは役場に来なくてもインターネットとウェブ等での申請が今可能なのかどうかというところがもし分かれば教えていただきたいのですが。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)昨今様々な申請方法があると思います。ウェブでの申請になりつつありますが、本申請に関しましては、申請書だけではなく、領収書の写しや口座番号の写し等、添付書類がございます。今後ウェブでの受付ができるようになるまでは現状でご理解をいただければと考えておりますけれども、なお防犯……
(「以上です。いいですか」の声)
〇議長(安原賢一)ここで。すみません。
(「でも、午前中にたぶんこの部分に関しては終わるから」の声)
〇議長(安原賢一)終わる。
(「はい、1番については。切りのいいとこでいいですか」の声)
〇議長(安原賢一)では、6番、佐藤さん
〇6番(佐藤力也)はい、ありがとうございます。今のところはできないということで、この補助金だけではないのですけれども、先ほど登庁するとガソリン代がかかるとかという問題もウェブでの申請ができれば解決いたしますので、これからそのITというところいろいろ導入されていると思いますので、うまくやっていって欲しいなと思います。よろしくお願いいたします。
今後の補助金の拡充について町長の見解を伺おうと思いましたけれども、もうすぐ時間ということですので、最後町での防犯カメラの設置というところの要望をして、前半戦終わりにしたいと思います。
町民の身体、生命、財産を守る上で防犯対策補助金の拡充をすることはとても大切なことです。町民の要望にぜひお応えいただきたいと思いますけれども、個人に対しての支援とは別に町として各要所への防犯カメラの設置台数を増設したほうがよいのではといった意見も町民の方から多く聞かれます。町全体で、町としての防犯対策のレベルを上げて、犯罪抑止につなげてほしいとの意見です。この点について、町では今後どのような取組を考えているのか、もし見解があれば、お伺いして終わりにしたいと思います、前半を。お願いします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)防犯対策につきましては個々の対策だけで防げるものではありませんので、町といたしましても安全で安心なまちづくりを推進しておるところでございます。
防犯カメラにつきましては、町内に28か所設置してありますが、設置につきましては、吾妻警察署からの要請並びに行政区からの要望を吾妻警察署と協議し、必要であると判断した場合は町で設置をしている状況であります。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)質問の途中ですが、ここで暫時休憩とします。再開は午後1時とします。
(休憩 自正午 至午後1時00分)
〇議長(安原賢一)再開します。
◎ 発言の訂正
〇議長(安原賢一)先ほどの佐藤議員からの質問の町長の答弁の中で、間違いがあったということで訂正をしたいということなので、許可します。町長
〇町長(外丸茂樹)議長のお許しをいただきましたので、午前中佐藤力也議員に対しまして、私のほうから大船渡市へ、吾妻広域消防本部の職員が緊急援助隊で行っているという話をさせていただいたときに、「消火活動支援」ということを申し上げるべきだったのですが、「消火訓練」というふうに申し上げたというふうに指摘を受けましたので、そこは訂正をさせていただいて、「消火活動支援に行った」というふうにご訂正をお願いしたいと思います。申し訳ありませんでした。
〇議長(安原賢一)引き続き、佐藤力也さん、質問をお願いします。6番、佐藤さん
〇観光振興と町の経済活性化について
〇6番(佐藤力也)それでは、続きまして観光振興と町の経済活性化についてご質問をさせていただきます。
観光振興における課題について。令和6年度の一般質問におきまして、私は町の観光振興や中之条ビエンナーレの課題、そして地域経済の活性化について、以下の点を指摘し、改善を求めました。
1、観光資源の保護と整備においては、景観維持のための取組、駐車場や公衆トイレの整備、観光案内所、休憩所などの施設の充実、地域住民との協働による観光振興策。
2、中之条ビエンナーレの課題解決については、これも駐車場不足問題への対応策、人手不足、ボランティアの確保、作品展示場の分散による地域経済の活性化。
3、まちづくりと観光戦略の推進として、四万温泉の新たな観光スポットの調査、準備、まちなか商店街の活性化対策、以上の課題に対して、令和7年度当初予算の編成にあたり、町として具体的にどのような施策を講じるのかをお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)観光振興と経済活性化についてのお尋ねの中で、観光資源における課題、令和7年度はどういうことかというお尋ねでありますけれども、昨年の6月、9月、12月の定例会議における一般質問において答弁をさせていただいたとおりでございます。
関連した内容では、令和7年度当初予算に計上させていただきました事業といたしましては、四万地区の清流をイメージした整備の継続事業費を計上させていただいております。また、各種イベントの開催の目的とPRにつきましては、夜桜のライトアップ事業を継続させていただきます。町民の皆様をはじめ、町外の皆様にも来園いただきたく、前回の装飾を上回るライトアップを催し、多くの方々に足を運んでいただきたいと思っております。
ビエンナーレにつきましては、今年度が第10回目となりますが、令和7年度が開催年ということで、予算計上させていただいておりますが、地域の方々の配慮した会場運営に努めさせていただきます。また、パスポート料金の見直しを行い、環境整備等へ充てたいと考えております。
商工関係につきましては、引き続き各種団体への助成や町内事業者への経営安定化施策を継続いたします。住宅リフォーム補助金や事業継続補助金等、前年度同様に令和7年度当初予算に計上しております。
新年度当初予算に計上されているもの、いないものございますが、全てのご要望にお応えすることは非常に難しい状況でございますので、優先順位をつけさせていただき、令和7年度当初予算を編成させていただきました。ご理解のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。
〇議長(安原賢一)6番、佐藤さん
〇6番(佐藤力也)ご答弁ありがとうございました。
私がここで1つさらに駄目押しといいますか、お願いしておきたいのはやはり駐車場問題でございます。これは本当にビエンナーレだけに限らず、常態化している問題ですので、ぜひこういったところ、新しい観光スポットの創設も大事なのですけれども、ずっと課題となっておりますので、もう分かり切った課題を最初にクリアするということも非常に大事なことと考えますので、ぜひご検討お願いいたします。
続きまして、経済の活性化というところで質問させていただきます。私はこれまで町の経済活性化、給付金の迅速化、事務手数料の軽減、さらには町職員の業務負担の軽減削減という観点から電子マネーを活用した地域通貨の導入を要望してまいりました。しかし、キャッシュレス決済を導入している事業者が少ないことなどを理由にいまだ実現に至っておりません。そこで、まず町内のキャッシュレス決済導入店を増やすことを目的に、さらには町外からの交流人口の増加による経済活性化を図る手段として、自治体キャッシュレスキャンペーンを実施してはいかがでしょうか。
近年多くの自治体がペイペイなどの決済サービスと連携し、キャッシュレス決済を利用した消費喚起キャンペーンを実施しております。例えばキャッシュレス決済を利用した際に、一定割合のポイント還元を行う施策は消費者の購買意欲を高めるとともに、住民サービスにもつながり、事業者側のキャッシュレス決済導入を促進する効果も期待できます。さらに、中之条町商工会で発行しているプレミアム商品券代替手段としてもキャッシュレス決済を活用することも検討すべきではないでしょうか。現在紙の商品券は、利用の手間や事務負担が大きい一方で、電子マネーによる決済を導入すれば、より利便性の高い仕組みとなり、町内の消費拡大にもつながります。財源の確保についても課題として指摘されていますが、ほかの自治体での取組も発表されていることから、当初国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の活用での提案をしようと思っていたところでございますけれども、その交付金を使っての提案は町のほうからされてしまいましたので、このタイミングではちょっともう遅いかなというところで、今回はそこではいたしませんけれども、ほかの財源というところで、入湯税やふるさと思いやり基金の活用を提案いたします。入湯税の活用に関しては、四万、沢渡、六合地区の温泉観光地は中之条町観光協会や商工会に属しており、観光振興を目的とした入湯税、目的税の一部をキャッシュレス促進策に充てることは可能ではないのかなと考えます。
以上の提案に対して、町長の見解をお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)電子マネー、いわゆる地域通貨の導入につきましては、令和6年9月議会において答弁をさせていただいておりますけれども、「町内におけるキャッシュレス決済の浸透を踏まえつつ、町としても行政窓口でのキャッシュレス決済の拡大などの取組を推進し、導入につきまして検討してまいりたい」とお答えをさせていただきました。その後の9月以降大きな進捗はなく、現時点での具体的な実施は予定しておりません。
QRコード決済等のキャッシュレス決済は便利で、多くの方が利用されており、今後は町内においても徐々に普及は拡大するものと考えられます。当初におきましても令和6年1月に、ドコモによるキャンペーンを実施し、一定の効果がございましたが、利用された店舗は限定的な状況となっております。キャンペーン実施時におけるポイントにつきましては自治体の負担となりますので、費用対効果も踏まえて、実施につきましては慎重に検討してまいりたいと考えております。
〇議長(安原賢一)6番、佐藤さん
〇6番(佐藤力也)このキャッシュレス決済、地域通貨導入というところでございますけれども、なかなか導入に進めないという。いろんな理由があるとは思うのですけれども、キャッシュレス決済を使えないお店がネックという部分はもちろんありますし、使う側がやはりそこに対応できないという高齢者の方も当町ではたくさん多うございますので、そういうことも考えて、今回の給付金についても紙ベースのところでやるのかなというところもございます。とはいえ、やはりこれからはそういったキャッシュの時代が来るわけでございますので、そこで使っ・・・キャッシュレス決済で、例えば給付金とかをデジタルでやった時にそのお店ではないと使えないから、そのお店で買物しないのかといったら、そうではないと思うのですよね。そのポイントをためて、別のお店で使う、もう使いたいものが、買いたいものがあれば、そこで使うということにもなると思いますので、そういったところは柔軟な考えで、これからまた検討していただければなと思います。よろしくお願いいたします。
続きまして、経済振興における財源確保について質問させていただきたいと思いますが、大変申し訳ございませんが、(1)の入湯税の使途についてというところと、(2)の部分、順番入れ替えてご質問させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。中之条町における観光振興のための財源確保について、町はどのように考えているのでしょうか。AIに、「中之条町の観光振興における財源の確保にはどのようなことが考えられるか」と質問したところ、まず最初に挙げられたのが既存の税収を活用することでした。具体的には以下のような提案がありました。「まず、入湯税の活用、四万、沢渡、六合などの温泉地がある中之条町では入湯税が観光振興の重要な財源となる。税収を活用し、観光施設の整備やキャッシュレス決済の導入支援などの施策に充てる。2、宿泊税の導入。近年観光地では宿泊税を導入する自治体が増えており、中之条町でも検討の余地がある。観光客の負担にはなるが、観光資源の維持、向上につながる活用が可能」、そして2番目に、「国、県の補助金、交付金を活用する」というところで、先ほどのお話にもあるのですけれども。そして、その次に「ふるさと納税の活用、企業版ふるさと納税の活用」、そして「ビエンナーレなどでの取組にもある民間との連携による資金調達としてクラウドファンディング、企業スポンサーシップ、観光イベントなどの観光施設の整備に対し、企業からの協賛金を募る」というところです。最後に、「観光収益の再投資」ということで、「町営施設や公営駐車場の料金の設定を見直して、観光客からの収益を確保」というところで、この公営の駐車場というのはまだできていないので、あれなのですけれども、四万温泉でも駐車場の有料化というところを今検討して、土木事務所のほうに今問合せをしているところでございます。以上の回答をAIが導き出しました。
さて、観光振興を進めるためには持続可能な財源確保が不可欠です。町長の耳にも既に入っているかもしれませんが、町観光協会におかれましても検討されている入湯税のさらなる活用においての増税や宿泊税の導入検討など、今後町としてどのように取り組んでいくのか、町長の見解を伺います。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)財源確保のお尋ねでありますけれども、入湯税は地方公共団体が特定の行政需要の経費を支弁する目的で課す税であり、地方税における目的税は地方税法に税目などが定められております。入湯税につきましては、温泉施設における入湯に対し、入湯客に課税される地方税であります。
また、宿泊税はホテル、旅館などの宿泊施設に宿泊する場合に宿泊料金に応じて課税される法定外目的税であります。入湯税の増額、宿泊税の導入につきましては、現在のところ考えておりませんけれども、今後の県内及び郡内の動向は注視してまいりたいと、そのように考えております。
〇議長(安原賢一)6番、佐藤さん
〇6番(佐藤力也)今町長の答弁にあったとおり、この入湯税は目的税ということで、例えば固定資産税ですとか住民税、そういったところの収入が増えますと、国からの交付金というのが下げられてしまうという、バランスを取られてしまうという部分があるのですが、この目的税はそこには関係しない税金ですので、収入が増えれば、税収が増えれば増えるほど自由に使えてよくなるという、簡単に言ってしまえば、そういう税金なわけですよね。そういったところの税収を増やして、これから観光振興に使うかどうかという、そういった質問だったわけですけれども、周りの動向を見つつ検討していくという町長の答弁を今いただきましたので、もちろんそれも大事なことですので、やっていただければいいかなと思います。
ここで1つだけ言っておきたいのが先ほど宿泊税の話をいたしました。入湯税の増税と宿泊税の導入、どちらがいいかという話もこれから出てくるのかなと思いますけれども、中之条町においては、やはり温泉施設のほうが圧倒的に多いので、入湯税の増額のほうがいいのかなと考えます。AIもそう言っていました。
それでは、最後にこの入湯税の使い道について質問をさせていただきます。中之条町では、四万、沢渡、六合といった温泉地を有し、観光振興や環境整備のための重要な財源として入湯税を徴収しておりますが、その使い道について、宿泊事業者を中心に宿泊者から預かった税金が地元事業者に直接還元されるような扱い方をして欲しい、四万、沢渡、六合などの組合等の補助金の配分を増やして、温泉地の維持、発展に役立てるべきという意見、要望の声が寄せられております。現在の入湯税の使途を拝見しますと、中之条ガーデンズのような観光施設の整備や観光振興事業など、町全体の観光振興に資する形で案分されているようですが、町としてはこれまでどのような考えに基づいて、このような配分を行ってきたのでしょうか。また、今後各温泉地の観光事業者への支援を強化するために、補助金、目的税の配分の増額を検討する考えというのはあるのか、お伺いをいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)地方税法に規定する入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるために課税するものであり、当町においてもその趣旨に沿って各種事業に充当いたしております。
観光振興や観光施設の整備はもちろんですが、観光地の環境整備により入湯客の効用を高めたり、防災対策など安全安心の確保も重要な施策でありますので、総合的に事業を加味した中で充当を考えております。
また、中之条町には多くの温泉地域があり、旅館等の営業施設の数も地域により大小様々であります。目的税の趣旨等を考慮し、納税額や人数等に関わりなく、こうした目的税を幅広く有効に使うことで、町全体の観光振興につなげていければと考えております。
佐藤議員が入湯税の増額をということでありますけれども、税ですから、増税ということになりますので、そのへんはやっぱり慎重に考えていかなければいけないのかなと、こんなことも付け加えさせていただきます。
〇議長(安原賢一)6番、佐藤さん
〇6番(佐藤力也)入湯税について町長に答弁いただきましたけれども、この入湯税の使い道というところで、いろいろの考え方が、町としてあって、こういった配分になっているのかなということは分かりますし、使い方について別に特段おかしいということではないのです。ただ、やはりどこに使うかという中で、観光施設、中之条ガーデンズに約3,500万の令和5年度の入湯税の中で2,200万ぐらいがガーデンズで使われているということで、ガーデンズの運営がそれありきの運営を考えていらっしゃるのか、それともたまたま頑張ってやっていたけれども、そこが足りないというところで、その入湯税を使ったのだよという、そういう順番なのか、そこをちょっと聞きたいのですけど。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)中之条ガーデンズに入湯税のというか、その使用されている。佐藤議員ご存じだと思うのですが、令和3年度に中之条ガーデンズが開園をいたしました。その当時、もう既に佐藤議員は議員でいらっしゃったと思うので、この開園をするにあたっては、前町長が非常に思い入れを持って開園をしたということを踏まえますと、まだ今年で5年目ですから、やはりこの5年間の中である程度整備ができてグランドオープンができたと、しかしながらやっぱり経費の縮減というのは考えていかなければならないというふうに十分私も思っております。今の経費がどんどん、どんどんつぎ込むのがいいとは一切思っておりませんけれども、ただ5年しか経っておりません。造るのに相当の税金を投入したわけでありますので、そういった活用も考えながら経費の節減をして、観光としての中心地としていこうと、「花と湯の町なかのじょう」ということで、折田町長の時にテーマを決めました。これもやっぱり継承していくのも我々の責任であろうと思いますし、しかしながらやっぱり経費の節減というのはしっかり考えていかなければならないと思いますので、入湯税も含めて、しっかりこのお金の使い道については考えていきたいと、このように思っています。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)6番、佐藤さん
〇6番(佐藤力也)よろしくお願いいたします。
「花と湯の町なかのじょう」ということで、花はもちろんなのですけれども、湯というところが私は先にあると思っているので、そっちをおろそかにして、花のほうを頑張るというのは逆なのではないかという意見も結構聞いているので、両方やらなければいけないのはもちろんなのです。分かるのですけれども、両方がお互いに切磋琢磨というか、相乗効果でよくなっていくのが一番だと思いますので、そういったことになるようにこれからもいろんな検討を重ねてやっていただきたいと思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。