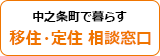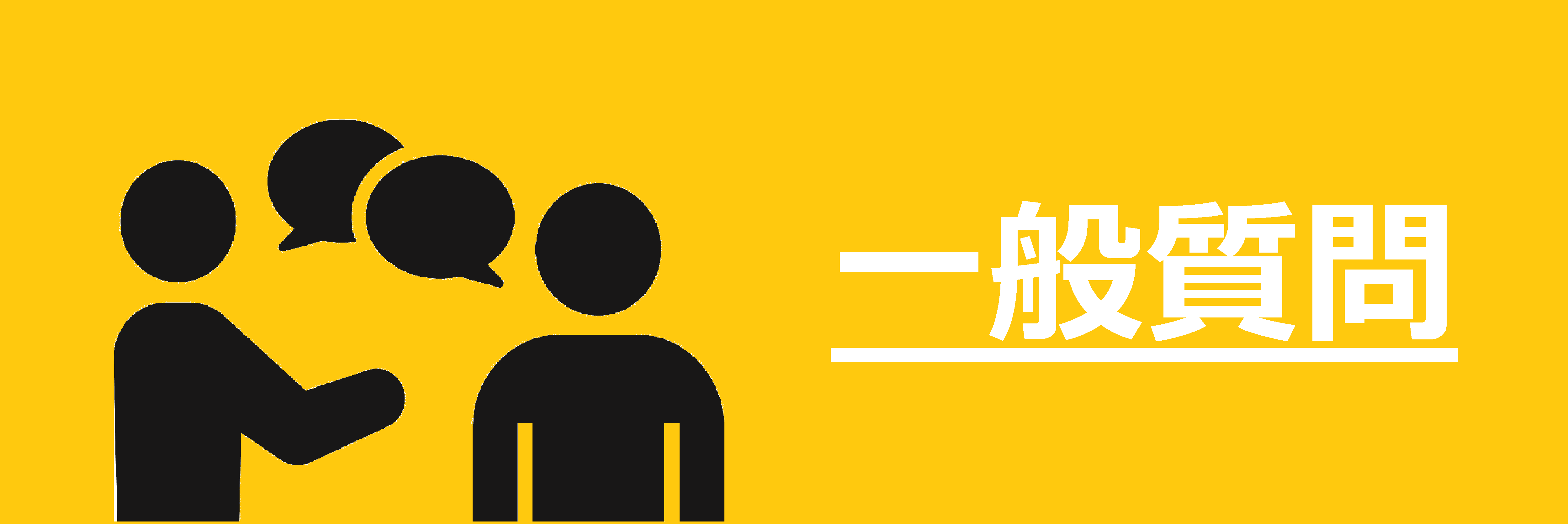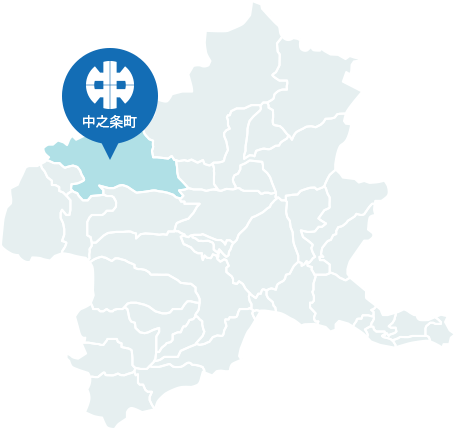本文
令和6年12月定例会議 一般質問(関美香議員)
07 7番 関美香議員 令和6年12月定例会議一般質問
〇7番(関 美香)議長よりお許しをいただきましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。質問の内容は、1、子育て支援について、2、不登校への支援について、3、窓口対応について、以上の3項目です。よろしくお願いいたします。
〇子育て支援について
まず初めに、子育て支援についてお伺いいたします。令和6年3月定例会議の一般質問において、中之条地域における認定こども園設置について質問させていただきました。中之条町の子育て支援においてこの問題は重要であり、さらに議論を深めるべきと考え、中之条地域における幼稚園、保育所について質問させていただきます。まず初めに、令和7年度の中之条地域における幼稚園、保育所の利用状況についてお伺いをいたします。
〇議長(安原賢一)教育長
〇教育長(山口暁夫)関美香議員の質問にお答えさせていただきます。
毎年10月に翌年度の幼稚園及び保育所への入園希望者の申込みを受けております。令和7年度の申込み状況ですが、伊勢町保育所が133名、中之条保育所が128名、中之条幼稚園が28名、沢田幼稚園が19名、六合こども園が12名となっており、今年度と同様、保育所の利用を希望されるご家庭が多い傾向に変わりはございません。また、令和7年度に3歳児となるお子さんだけを取上げてみますと、2歳児までは保育所を利用していて、3歳児になる段階で幼稚園を利用されるお子さんは6名おりました。利用者が保育所に偏っている状況から、各幼稚園では園開放の際や、令和6年度から中之条幼稚園に移設した子育て支援センターでの活動などを通じて、幼稚園教育の魅力を啓発しております。
また、教育委員会では、幼児教育の在り方を検討する中で、中之条小学校に配置している外国語指導助手、ALTを幼稚園にも派遣し、英語教育の充実に取り組んでおります。さらに令和7年度からは、中之条幼稚園でも保育所と同じ最長11時間の預かり保育を可能にするとともに、長期休業中の預かり保育料を1時間単位の利用料に細分化するなど要綱を改正し、幼稚園における幼児教育の特色や利便性の向上に向けた取組を行っております。
以上でございます。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)令和7年度の利用状況において、今年度と同様、保育所の利用を希望されるご家庭が多い傾向であること、確認させていただきました。また、教育委員会では、幼児教育の在り方を検討され、幼稚園における幼児教育の特色や利便性の向上に向けた取組を行っているとの答弁もいただきました。
令和7年度からは、中之条幼稚園でも保育所と同じ11時間の預かり保育が可能となること、また長期休暇中の預かり保育料を1時間単位の利用料に細分化されることをお伺いし、これらの取組によって、利用者の偏りが少しでも解消されるよう期待をしております。
答弁にもあるように、保育所の利用者が増加していることにより弊害が生じていると認識をしております。具体的には、出産のため産前産後8週間の保育所利用を考えていた方が定員に達したため、入所を諦めざるを得ない状況、また保育所の運動会において保護者の観覧人数が2名までと制限されたことなどが挙げられますが、保育所の利用者増加によって生じている弊害に対して、どのような見解をお持ちなのかお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)教育長
〇教育長(山口暁夫)この件につきましては、こども未来課長より答弁を行います。
〇議長(安原賢一)こども未来課長。
〇こども未来課長(山本伸一)こども未来課の山本です。
ご質問の件につきまして、制度上、保育所の利用定員は保育室の面積が基準となり、ゼロ歳児や1歳児であれば1人当たりに必要な保育室は3.3平方メートルとされ、2歳児から5歳児は1人当たり1.98平方メートルとされております。このことから、施設で受入れ可能な最大定員が決まり、そこから運営方針や保育士の人数などにより、実際の定員が決められるものです。当町では、できる限り待機児童を生じさせないよう、令和5年度から保育所の定員を最大定員、伊勢町保育所では158人、中之条保育所では159人としておりますが、年度途中などに入所を希望された際に、入所を希望する年齢が定員いっぱいになっている場合にはお受けできないこともございます。また、両保育所を建設する際は、実際の利用者数を100人程度と想定して建てられたものと考えられ、現在140人程度のお子さんをお預かりしていることから、トイレや手洗い場、遊具、駐車場の数が不足している状況です。これらに対し、保育所で創意工夫をしながらやりくりをしておりますが、大きな課題となっております。
保育活動につきましては、新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことから、プール活動の再開に対するご要望もございますが、県の指導監査により、安全を確保できる十分な人員措置が取れない場合は、安全を第一に考え、プールではなく水遊びを充実させることとされており、入所児が増え、これを解決できるだけの保育士の余力人員は配置できていないことから、令和6年度も再開を見送ってまいりました。さらに、保育参観やお遊戯会の開催、それらの行事の観覧者数の制限解除などについてもご要望をいただいており、保育所において対応できる方法を検討しておりますが、観覧場所や駐車場の確保など、施設面や環境面が大きな課題となっております。
以上です。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)両保育所を建設する際、利用者数を100人程度と想定して建てられたと考えるが、現在は140人程度のお子さんを預かっている状況や、保育士の余力人数、人員を配置できていないことから、施設面や環境面で大きな課題を抱え、その中で創意工夫をされ、運営している状況であることを改めて確認させていただきました。
そういう状況の中、大変恐縮ではありますが、利用者増加によって生じている問題への対応を求めたいと思います。産前産後8週間の入所を考えられていましたが、定員に達しているため入所できず、一時預かりを利用される方から負担を軽減してほしいとのお声を伺っております。保護者の負担でありますが、利用料金の支払いやお弁当やおやつ、布団の持参などが挙げられます。一時預かりを利用する保護者の負担軽減について検討すべきと考えますが、見解をお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)教育長
〇教育長(山口暁夫)一時預かり、いわゆる一時保育事業は、当町に住所を有し、保育所や幼稚園などに在籍していない乳幼児を対象に、保育の必要性の有無にかかわらず、急な用事や短期のパートタイム就労のほか、保護者の方がリフレッシュしたいときなどの際に利用していただけるものです。また、急な転勤により本町へ移住された方や、妊娠による産前産後前後8週ずつなどで年度途中に保育所への入所を希望された際に、既に保育所の定員がいっぱいとなっている場合には、一時保育事業をご利用いただくことがございます。利用料金は、ゼロから2歳児では8時30分から12時30分までの半日が700円、8時30分から16時30分までの1日が1,500円、3歳から5歳児は半日が300円、1日が650円となっております。利用料金につきましては、こども家庭庁が進める、こども誰でも通園制度が令和8年度から全国展開される計画となっておりますので、これらの制度も確認しながら、保護者の負担軽減を検討していきたいと考えております。
また、利用時間によってはお昼の弁当やおやつ、お昼寝用の布団を持参いただく必要がございます。お昼やおやつは、保育所児と同様に提供できればよいのですが、現在は入所児の数が多いことや、アレルギー対応など調理場の業務負担も大きく、毎日利用する人数や対象児が違う一時保育のお子さんに対し、安心安全な給食提供が難しい状況がございます。お昼寝用の布団に関しましては、入所児の全てのご家庭にも持参していただいております。一時保育のお子さんだけでも貸与できればよいのですが、布団の衛生面や管理面から持参していただく必要があると考えております。国の政策などもあり、今後さらに一時保育の利用希望者が増加することが想定されることから、保育室の確保や保育士の配置人数、利便性の向上も含め検討を行っていきたいと考えております。
以上でございます。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)一時保育のお子さんへのお昼やおやつについては、保育所児と同様の提供が厳しいこと、また衛生面や管理面から布団の持参が必要であることも十分理解しております。
教育長から、今後さらに一時保育の利用希望が増加することが想定され、保育室の確保や保育士の配置人数、利便性の向上も含め、検討を行っていきたいとのお考えを示していただきましたので、一時保育に関する保護者の負担軽減についてぜひ検討していただきたいと思います。
急な転勤により中之条町へ移住された方や出産による産前産後8週間など、時期を問わず保育所への入所を希望される場合において、既に保育所の定員がいっぱいになっている際には、一時保育の利用があることからも、保護者の負担軽減について検討すべきと考えますが、町長の見解をお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)幼児保育に対しましては、一時保育だけでなく、夜間保育や病児保育、日曜日や祝日、年末年始にも保育を希望されるなど、各ご家庭の状況により様々な要望があるとは承知をいたしております。なかなか全てのご要望をかなえることは難しい面がございますけれども、例えば一時保育に対しては、利用料の免除や減免も考えられることから、利便性の向上なども含め、検討させていただきたいと思います。
まずは、教育委員会で協議検討を行っていただき、その結果に基づいて予算措置など必要な対応を取っていただきたいと考えております。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)町長から、一時保育に対しては利用料の免除や減免も考えられるとの見解を示していただきましたので、教育委員会で前向きに協議していただき、来年度に向けた予算措置を要望させていただきます。
対応として、もう1点、保育所の利用者が増加していることから、広報紙への入所募集記載においては配慮が必要ではないかと考えます。広報誌に募集記載があるのにもかかわらず、定員に達しており受入れできないとの回答に納得いかないというお声をいただいております。広報紙への入所募集の記載においては、定員に達した場合、受入れできない旨を書き加えるなど、町民に寄り添った対応をしていただきたいと考えますが、見解をお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)こども未来課長
〇こども未来課長(山本伸一)関議員ご指摘のとおり、保育所の入所募集に対する記述に不足の点があり、保護者の皆様にご迷惑をおかけしましたことに対しまして、心からおわび申し上げます。
事業や制度を理解している職員が作成することにより、当然のことと捉えてしまい、本来住民の皆様にお伝えしなければならない必要な事項が欠落ししてしまう場合がございます。今後は今まで以上に住民目線に立って物事を捉え、複数人でのチェックも重ねながら取り組んでいきたいと考えております。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)今後は今まで以上に住民目線に立って物事を捉え、取り組んでいくとの答弁をいただきました。
今回一時保育について、また広報紙への入所募集記載に対するお声をいただき、私自身、町民の方々に寄り添うことの大切さを再認識し、いただいたお声を町政へ届けたいとの思いから質問をさせていただきました。入所募集の記載については、今後のご対応をどうぞよろしくお願いいたします。
最初に申し上げましたが、中之条町の子育て支援において、中之条地域の幼稚園と保育所の今後の方向性、またその計画を示すことは先送りのできない課題であると考えます。保育所の利用人数が幼稚園と比べ圧倒的に多く、それによる問題が生じていることからも重要な課題であると考えております。
以上のことから、中之条地域におけるこども園設置の方向性、そして設置はいつ頃を想定されているのか、お伺いいたします。
〇議長(安原賢一)教育長
〇教育長(山口暁夫)まず、幼稚園は学校教育法に基づき学校に位置づけられ、保育所は児童福祉法に基づき児童福祉施設に位置づけられております。認定こども園は、平成27年4月から始まった子ども・子育て支援新制度により新設された設置基準であり、4つの種類に分けられます。1つは、学校かつ児童福祉施設の両方に位置づけられる幼保連携型、2つ目は学校に位置づけられ、幼稚園に保育所機能をプラスした幼稚園型、3つ目は児童福祉施設に位置づけられ、保育所に幼稚園機能をプラスした保育所型、4つ目は主に民間事業者が設置するものとして、幼稚園機能と保育所機能を合わせ持った地方裁量型でございます。町教育委員会でも、今後の幼児教育の在り方として、認定こども園設置の必要性も含め検討しており、国の政策や保護者のニーズ等を考えると、認定こども園の設置も必要と考えております。
しかし、現在の乳幼児数と、現有施設の状況などから思案すると、現状の施設を認定こども園化することには課題も多いため、今後の出生件数の状況等を注視しながら、5、6年先を見据えて方向性を検討していきたいと考えております。
以上でございます。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)国の施策や保護者のニーズ等を考えると、認定こども園の設置も必要と考えておられること、また現状の施設を使い認定こども園化について思案され、5年から6年先を見据え、方向性を検討していきたいとのお考えを示していただきました。
先ほども申し上げましたが、中之条地域における幼稚園と保育所の今後の在り方については先送りのできない大きな課題でありますので、今後の検討を注視していきたいと思っております。
また、中之条地域の認定こども園設置の検討において、学童保育の今後についても併せて検討すべきと考えております。6月定例会議の一般質問で、長期休暇中の学童保育について質問させていただきました。その中で、学童保育の利用希望者が増加しているとの答弁をいただき、共働きで子育てをされているご家庭が増加している状況を実感しております。学童保育は、子ども達が安心して放課後や長期休暇を過ごす上で重要な施設であると考えます。以上のことから、中之条地域の認定こども園設置の検討において、学童保育についても併せて検討すべきであると考えます。
また、学童保育の安全性や利便性の向上において、中之条小学校併設を検討事項に加えていただきたいと考えますが、この点についても併せて答弁いただきたいと思います。
〇議長(安原賢一)教育長
〇教育長(山口暁夫)学童保育の必要性につきましては、特に小学校低学年の児童や、学校の長期休業中における要望が多いことは承知しております。教育委員会といたしまして、今後の幼児教育の在り方を検討する中で、余剰施設が生じ、学童保育などへの利活用ができるようであれば、管轄する住民福祉課と協議、検討を行っていきたいと考えます。また、中之条小学校への併設につきましても、その方向性が示されれば、前向きに協力していきたいと考えております。
以上でございます。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)学童保育の必要性について、小学校低学年の児童や長期休暇中の要望が多いとの答弁をいただきました。また、先ほど幼児教育の今後の方向性については、5年から6年先を見据えているとのお答えをいただきましたので、学童保育の今後についても住民福祉課をはじめ、関係各所と十分協議していただき、子ども達が放課後や長期休暇をより安心安全に過ごすための検討を重ねてお願いいたします。
それでは、この質問において最後になりますが、中之条町の子育て支援充実の観点から、中之条地域におけるこども園設置と学童保育の今後について、また学童保育については中之条小学校併設についても併せて検討を進めるべきと考えますが、町長の見解をお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)様々なご意見を伺う中で、中之条地区における認定こども園の必要性は感じており、以前には担当課長へ幼稚園のこども園化に向けた検討を指示したこともございました。しかし、教育長の答弁にもございましたとおり、課題も多いことから、教育委員会でしっかりと協議をしていただき、今後の方向性を検討していきたいと考えております。
中之条町には学童保育所が中之条地区に民間で2か所、六合地区には公立で1か所ございます。現在、待機児童もなく希望する方を受入れて、受入れは全てできている状況でございます。今後の状況の変化により、新たな学童保育所の施設整備が必要になる状況となった場合には、小学校への併設や学校敷地内、空き教室等の利用も視野に入れ、関係機関とともに検討していきたいと考えております。放課後、子ども達が安全安心に過ごせるように、皆様からご要望を伺いながら、関係各所と十分な協議を行ってまいりたいと考えております。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)町長から、中之条地域における認定こども園の必要性を感じ、幼稚園のこども園化に向けた検討を指示したことがあるとの答弁をいただきました。
教育長と町長の答弁、また国の施策や保護者のニーズ等を考えると、認定こども園の設置へかじを切っていくことは明らかであると感じております。ただ、現在の乳幼児数と現有施設の状況などから、こども園化するには多くの課題があることを再認識いたしました。先ほども申し上げましたが、中之条地域における今後の幼児教育の在り方は、子育て支援において重要な課題でありますので、今後の検討を注視していきたいと思います。また、学童保育の今後についても、子育て支援充実の観点から、子ども達の安全性や利便性の向上が図られるよう、併せて検討していただきたいと考えますので、どうぞよろしくお願いいたします。
〇不登校への支援について
それでは、次に不登校への支援についてお伺いをいたします。2023年度の文部科学省の不登校調査によると、群馬県内の公立小学校で30日以上欠席した不登校の児童生徒数は、前年比318人増の4,700人で、2001年度以降の調査において最多を更新したとの報道がありましたが、中之条町における小中学校の不登校児童生徒数の現状をお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)こども未来課長。
〇こども未来課長(山本伸一)小中学校の不登校児童生徒数につきまして、令和5年度の状況で申し上げますと、小学校では少ない月で7名、多い月で10名となっております。中学校では少ない月で7名、多い月で14名となっております。年度当初は新たな気持ちで取り組もうとする気持ちからか比較的少なく、ゴールデンウイーク明けから徐々に増え始め、夏休み明けから秋にかけさらに増加していく傾向にございます。過去3年間の状況を見ましても、若干の増減はありますが、ほぼ同じような状況でございます。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)過去3年間の不登校児童生徒数において、若干の増減はあるが、答弁いただいた人数とほぼ同じような状況であると確認させていただきました。
一般的に保健室登校や遅刻、早退の日数も考慮し、欠席日数が15日以上30日未満である状態が不登校相当と認識をしておりますが、不登校児童生徒とともに、不登校相当の児童生徒も全国的に増加傾向であるとの報道を見聞きしております。中之条町の小中学校における、不登校相当の児童生徒数の把握についてお伺いをいたします。
〇議長(安原賢一)こども未来課長。
〇こども未来課長(山本伸一)文部科学省の調査では、不登校児童生徒とは、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因、背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるために、年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由によるものを除いたものと定義されております。また、毎月報告が義務づけられている群馬県の調査では、年間30日以上のほかに月6日以上休んでいる者についても不登校の対象となっております。
ご質問の不登校相当の児童生徒数については、文部科学省や群馬県の不登校の定義には満たないものの、学校を休みがちな者が該当すると考えられますが、明確な定義がなく、把握をしておりません。不登校相当とは少し意味合いが違うかもしれませんが、本町では今年度の2学期から、保健室及び心の相談室の利用者数について、それぞれの場所を月に5日以上利用した人数を調査しております。10月の状況で申し上げますと、保健室利用は小学校で2名、中学校で11名、相談室利用は小学校で8名、中学校で7名となっております。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)今年度の2学期から保健室及び心の相談室の利用者数について、月5日以上利用した人数を調査していること、またニーズについても示していただきました。
中之条町の不登校支援の代表的な取組である教育支援センター「虹」は、不登校児童生徒の基礎学力の補充や、生活習慣改善のため、子ども達や保護者に対する相談や指導を通して、子ども達の社会的自立を目的としており、令和6年度からは指導員が1名増員され、体制の充実が図られているところでありますが、全国と同様、中之条町においても不登校の児童生徒の増加、そして休みがちな児童生徒や保健室や心の相談室を多くの児童生徒が利用されている状況から、さらなる居場所について、検討の必要性を感じております。
以上のことから、多様な居場所づくりと学習支援における校内フリースクール設置について見解をお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)教育長
〇教育長(山口暁夫)町では多様な居場所づくりとして、学校内に心の相談室、学校外に教育支援センター「虹」を設置しており、学校の保健室も活用しながら、児童生徒の困り感の内容や程度により、それぞれの居場所を使い分けて対応しております。
先ほど答弁させていただいたとおり、保健室、心の相談室ともに多くの児童生徒が利用しており、その困り感も様々です。校内フリースクールと呼べるものかは分かりませんが、中之条中学校では、教室に入れなくても登校することが可能で学習に取り組める生徒に関しては、心の相談室のほか空き教室なども使い、心の相談員やクラス担任等の教師により、プリント学習や個別指導を通じて学習の補完に取り組んでおり、個々の状態に合った対応を実践しております。
以上でございます。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)教室に入れなくても登校が可能で、学習に取り組める生徒に対する学習の補完について確認をさせていただきました。
校内フリースクールについて調べたところ、多様性を認め、それぞれの特性に応じた学びの場であり、答弁いただいたように個々に合った対応が大切であると考えますので、今後についても誰一人取り残すことのない学びの場の確保に努めていただきたいと考えます。
また、多様な学びの場を確保する観点から、群馬県が不登校児童生徒の居場所として今年6月に開設したつなぐんオンラインサポートについてお伺いいたします。つなぐんオンラインサポートの対象は、県内の小中学校と高校、特別支援学校などに在籍し、原則30日以上通学できない児童生徒でありますが、インターネット上の仮想空間メタバースを通して、自宅にいながら学習や悩み相談ができる新たな学びの場が開設されたと認識しておりますが、つなぐんオンラインサポートの利用状況についてお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)こども未来課長。
〇こども未来課長(山本伸一)つなぐんオンラインサポート、略してつなサポと呼ばれるものですけれども、これはメタバースと呼ばれるインターネット上の仮想空間の中で、アバターと呼ばれる自身の分身を操作し、自身に合った学習を行ったり、ほかのアバターとの交流を通じてコミュニケーション力や自ら学ぶ力の育成につなげていくことを目的に開設されています。特に完全不登校で家族以外の人との交流がないような場合、社会性を育むきっかけとして有効でありますので、小中学校においても、必要に応じ情報を提供してきました。本町でも利用している児童生徒がおりますが、具体的な人数等に関しましては、個人の特定につながることも考えられますので、差し控えさせていただきます。
以上です。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)完全不登校の児童生徒の社会性を育むきっかけとして有効であり、小中学校において必要に応じ、情報提供し、利用されている状況があること、確認させていただきました。
先ほど申し上げましたが、つなぐんオンラインサポートは、インターネットを使い自宅に居ながら学習や悩み相談ができる新たな学びの場であり、不登校支援において必要に応じて活用すべきと考えております。
そこで、1点確認させていただきたいのですが、つなぐんオンラインサポートの活用において、中之条町はメディア機器の使用を制限するアウトメディアに取り組んでおられることから、つなぐんオンラインサポートの活用とアウトメディアの整合性について見解をお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)教育長
〇教育長(山口暁夫)本町のアウトメディアの目的は、子ども達がテレビやDVD、ゲーム、スマートフォン、インターネットなどの電子メディアの過剰な使用や誤った使用による健全な成長の阻害と犯罪被害の防止を目的にしております。あくまでも過剰な利用や誤った使用が問題となるものであり、全く使わせないといったことではございません。
小中学校への1人1台端末の導入の際にも、トリプルトゥエンティ(20-20-20)ルールをつくり、電子メディアを使用するときには30センチ以上目を離して、20分ごとに20秒以上、20フィート、約6メートル離れた場所を見ることを指導しております。つなサポにおいても、メタバース上で指導員やスタッフがサポートしており、休憩を含む適切な指導が行われているものと考えております。
以上でございます。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)中之条町において電子メディアを使用する際は、ルールに基づいた指導が行われており、つなサポにおいても休憩を含む適切な指導が行われているであろうとの考え、示していただきました。
不登校への支援において、電子メディアを必要に応じ、また適切に使用することにより、新たな学びの場の確保につながると考えますので、つなサポについても、今後も不登校支援に取り入れていただきたいと思います。
最後に、不登校の児童生徒の増加、そして多くの児童生徒が保健室、心の相談室を利用し、困り事についても様々な状況であることから、支援は多岐にわたり、大変なご苦労があろうかと思いますが、今後も不登校への支援について、学校現場、教育委員会、こども未来課の連携を密にしながら、児童生徒それぞれの状態に合った対応を実践していただけるよう、引き続きの取組をどうぞよろしくお願いいたします。
〇窓口対応について
それでは最後の質問に入りたいと思います。窓口対応についてお伺いをいたします。役場の窓口には日々様々な町民のみなさんが来庁され、その対応は多岐にわたっていることと思います。来庁者の満足度に大きく影響し、町民との良好な関係を築く上においても、職員の接遇をはじめとした窓口対応の品質を向上させることは、大切な取組であると考えます。
そこで、窓口対応の品質向上における具体的な取組についてお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)窓口対応の品質向上における取組についてお尋ねいただきました。役場に限らず、町の各施設には、町民だけではなく多くの来庁者がいらっしゃいます。訪れる目的や内容は様々で、各種証明を取りに来る方から補助金などの申請や相談のほか、ご意見や苦情を受けることも多々ございます。最初に対応するのは窓口の職員であり、特に視察や観光目的で町外から来庁された方にとっては、町に対しての第一印象になるかもしれませんので、そういった意味でも大切な業務であると認識をいたしております。特に高齢者や身障者などへの配慮は安心感にもつながり、親切な対応が必要であると考えております。
町では、入庁2年目程度の職員を対象に接遇研修を実施しており、研修のメニューの中には電話対応などもございます。また、希望する職員には接遇研修でなくても、例えばクレーム対応など、多種多様な個別研修を受講できる機会を設けておりますので、そういった研修を活用し、スキルアップ等に努めていきたいと考えております。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)来庁された方に最初に対応するのは、窓口の職員であり、町に対する第一印象になる場合も考えられるので、大切な業務であり、特に高齢者や身障者などへの対応は配慮と親切が必要であるとの考えを示していただきました。また、職員の接遇研修や個別研修を通してスキルアップに努められている点についても確認させていただきました。
答弁いただいたように、ご意見や苦情を受けることも多々あることから、窓口対応において、職員のみなさんは様々なご苦労されていると思います。
そこでお伺いしたいのは、窓口対応において町民と良好な関係を築くためには、来庁された町民に寄り添った対応が求められると考えますが、取組の具体的な事例についてお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)取組の具体的な事例について答弁させていただきます。
先ほど高齢者や身障者への配慮に触れましたが、そもそも来庁者の中には業者等と異なり、なかなか役場へ来庁する要件もないことから、初めて来庁される方も少なくありません。どこの部署でどのような手続をするのか分からず戸惑う姿も目にしますので、案内所を設置して対応しております。
町民に寄り添った具体的な事例ということでございますが、1例を挙げれば窓口のワンストップ化がございます。これは、職員提案の中から生まれたもので、今では多くの自治体で見られるようでありますが、当町ではいち早く取り入れた対応方法であったものと思っております。例えば親族等がお亡くなりになられたときは、火葬手続はもちろん、その後に各種手続が必要となりますが、お客様が手続に来庁された際に、それぞれの窓口に移動し手続を行うものではなく、各部署が連携することで、1つの窓口で各種手続が完了できるよう、職員自身が入れ替わり対応し、ワンストップ化を図っております。もちろんワンストップで完了できない手続もございますが、これもお客様のご負担の軽減になる取組であると考えております。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)親族等が亡くなられたときの手続で来庁された際、それぞれの窓口に移動し手続を行うのではなく、1つの窓口で各種手続が完了する窓口のワンストップ化を紹介していただきました。また、どこの部署でどのような手続をすればよいのか分からない来庁者に対しては、案内所を設置して対応されており、町民に寄り添った取組に努められていることを確認させていただきました。
窓口において、難聴の方や聴覚に障害をお持ちの方に対しては、より丁寧で配慮した対応が求められると考えますが、具体的な取組についてお伺いをいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)窓口対応におきましては、町民の皆様に寄り添った対応を心がけているところでございますが、難聴の方や聴覚障害をお持ちの方へ配慮した窓口対応といたしましては、住民福祉課窓口において、次のような取組を行っております。職員の声が聞き取りづらい難聴の方へは、遠聴支援機「みみ太郎」を用意しております。こちらは、人間の耳と同じ働きをする人工耳介を搭載しており、両耳にイヤホンを装着することによって自然な会話を行うことができるものであります。
ほかにも窓口には耳がご不自由な方のために、耳マークの指差しシートを設置し、希望される方には筆談や大きめの声で対応しております。この耳マークにつきましては、社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会が普及を進めており、耳が不自由な方の立場や存在を社会一般に認知していただき、コミュニケーションの配慮などの理解を求めていくためのシンボルとなっております。また、聴覚に障害を持っている方のコミュニケーション手段である手話の利用に際し、当町では専門の手話通訳者を設置し、窓口対応や日常生活への支援を通じて安心した地域生活を送ることができるよう、福祉の増進に努めているところであります。
今後も難聴の方や聴覚に障害をお持ちの方に対しても、よりきめ細やかな配慮と対応を心がけ、町民の方々に寄り添った柔軟な対応を図ってまいりたいと考えております。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)難聴の方への窓口対応として、聞こえをサポートする「みみ太郎」を設置されており、また耳マークシートを設置し、希望される方には筆談や大きめの声で対応されているとのこと。さらに中之条町では手話通訳者が常駐されており、聴覚に障害をお持ちの方の窓口対応はもちろん、日常生活への支援を通じて福祉の増進に努められていることを伺い、手話通訳者の常駐は聴覚に障害をお持ちの方にとって大変ありがたい取組であると感じております。
それでは、最後になりますが、窓口対応の品質向上において、難聴の方との意思疎通をより図ることが大切であると考えており、難聴の方との意思疎通に役立つ軟骨伝導イヤホンについてお伺いをいたします。軟骨伝導イヤホンは、耳周辺にある軟骨の振動を通じて音が聞こえる仕組みになっており、難聴の方が来庁した際、軟骨伝導イヤホンを使うと付属の集音器が職員の声を拾い、イヤホンを通じて本人にはっきりと届きます。イヤホンを耳の穴に入れなくても明瞭に聞こえる上、清潔を保てます。また、担当課によってはプライバシーに触れる相談内容もあり、職員は大きな声を出しづらい場面もあるかと思います。軟骨伝導イヤホンを使うことにより、大きな声を出さなくても済むことから、難聴の方が安心して相談できる環境づくりに役立つと考えます。
以上のことから、窓口対応の品質向上において、軟骨伝導イヤホンを導入すべきと考えますが、町長の見解をお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)関議員のおっしゃった軟骨伝導イヤホンでございますが、軟骨伝導を活用したイヤホンの導入が全国の自治体にも広がってきており、聞こえのサポートをしていることは報道等にて承知をしているところでございます。
軟骨伝導イヤホンを利用することの利点といたしましては、耳周辺の軟骨を振動させることによって音を伝えるため、音漏れを防ぐ効果が高く、大声を出す必要がなくなることにより、窓口等でのプライバシーに配慮することができるとともに、イヤホンの形状につきましても、穴がない丸型のイヤホンのため、耳垢が固着することなく、衛生的に使用できること等が挙げられます。また、聞こえることのすばらしさを実感することによって、難聴改善にも取り組むきっかけを生み出し、認知症の予防にも役立つと言われております。
群馬県内におきましても一部の自治体において導入が始まっており、新たに軟骨伝導イヤホンを窓口導入することによって、より一層の住民サービスの向上や職員の窓口業務における負担軽減、また利用者が安心して相談できる環境づくりにつながる可能性がございますので、今後の有用性を含めた環境整備に向けた研究及び設置に向けた調査を進めていきたいと考えております。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)7番、関さん
〇7番(関 美香)町長から軟骨伝導イヤホンを窓口導入することによって、より一層の住民サービス向上や職員の窓口業務における負担軽減、利用者が安心して相談できる環境づくりにつながる可能性があるとの答弁をいただきました。
吾妻郡内で導入されている町村はまだないので、先日高崎市役所の保険年金課を訪問し、軟骨伝導イヤホンを視察してきました。実際使わせていただき、職員の方が普通より小さな声で話されても明瞭に聞こえ、イヤホンを耳のくぼみに乗せて使用するので、衛生的であると感じました。
また、答弁にもありますが、軟骨伝導イヤホンを使うことにより、難聴の改善に取り組むきっかけを生み出し、認知症の予防に役立つことが考えられます。訪問した保険年金課の課長さんは、自分の母親に軟骨伝導イヤホンをプレゼントし、母親が大変喜んでいるとのお話をしてくださいました。
以上のことから、今後の有効活用も含め、新年度に向けた導入への前向きな検討をお願い申し上げ、私の質問を終了いたします。大変にありがとうございました。