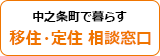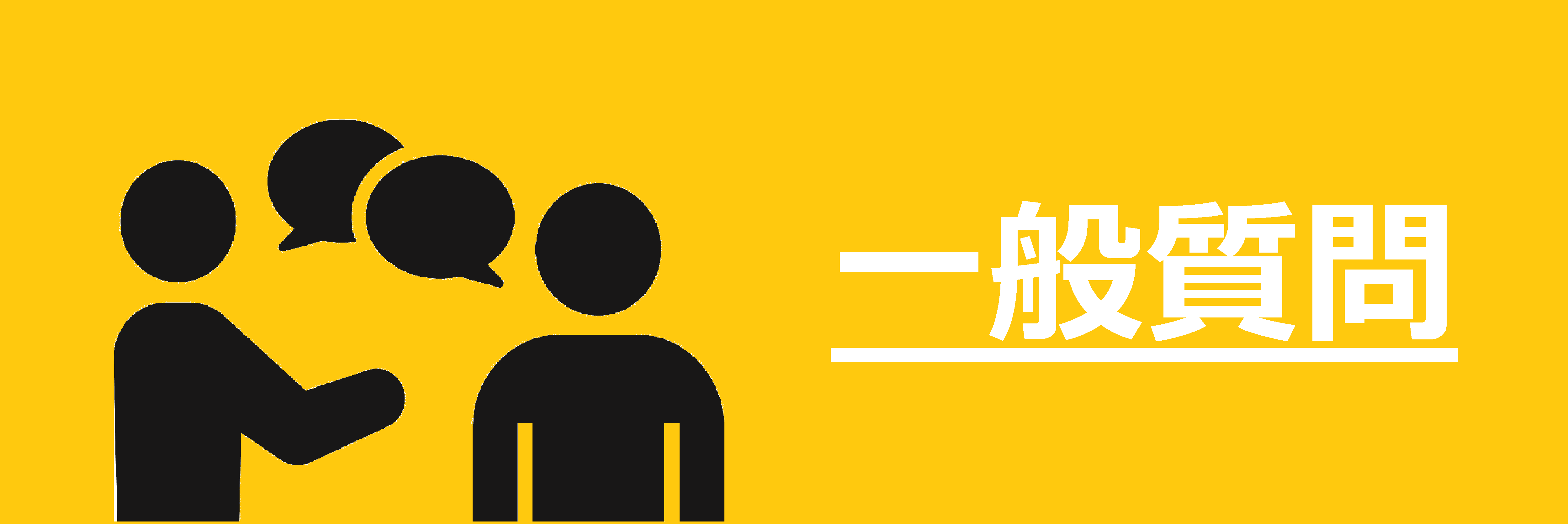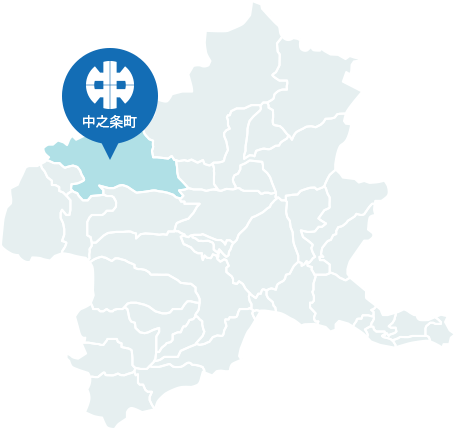本文
令和6年12月定例会議 一般質問(原沢香司議員)
02 1番 原沢香司議員 令和6年12月定例会議一般質問
〇1番(原沢香司)通告に基づきまして、私からは3点について質問をいたします。まず、行政区組織について、次にマイナンバーカードと健康保険証を連携させることについて、最後に消防団組織の現状について、以上の3点です。これまでの一般質問で取り上げた問題もありますが、経過や情勢の変化も踏まえて質問いたしますので、町長の答弁をいただければと思います。
〇行政区組織について
まず、1点目が行政区組織についてです。基礎自治体である中之条町において、さらに基礎をつくっているのが行政区組織です。行政区の中にはさらに隣保班を組織するなどして、住民の自治活動を促進するためにご尽力いただいていると理解しております。町の広報や文書の配布など、町の行政事務を円滑に行う上で欠かすことのできない組織ですし、町政を運営する上でこの行政区は本当に必要な存在だと思っています。一方で、高齢化と独居率が高くなる中、住民同士の見守り活動を行い、地域の人同士で安否を確認し合う上でも、また地域の防災、防犯という面からも大変重要な役割を果たしているのが行政区の活動であると日頃から考えております。
今日は、中之条地区の区長さんたちが傍聴に来てくださっておりますが、日頃の活動にご尽力されていることに心からの敬意を表します。
この行政区ですけれども、みなさんの実感としても高齢化と人口減少による活動力の低下は否めないのではないでしょうか。役員さんの高齢化が進み、新しい人材の育成が難しいこと、区長さんのなり手がいなくて四苦八苦している、そういう話もいろんなところで伺います。新しい住民が増えている地区もありますが、行政区に加わらない選択をする方もいるようですし、先日私がお話を伺った方は、そもそも行政区というものがあること自体を知らなかったということでした。都市部からの移住者が増え、海外国籍の方が住まわれ、多文化共生社会の進展に伴い住民ニーズが多様化する中、従来の行政区組織ではなかなか対応し切れない、そういう現状もあると思います。
ここでまず伺います。住民票を町に有する町民のうち行政区組織に加入していない人数を把握していますか。また、そのうち海外国籍の人の人数を把握していますか、答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)それでは、原沢香司議員の質問にお答えをさせていただきます。
少子高齢化や人口減少が叫ばれる中において、地域コミュニティーの現状として、議員がおっしゃる地域組織への加入問題や地域行事等への参加者の減少は当町に限らず全国的に大きな課題であると認識をいたしております。組織への加入や参加は、地域コミュニティーの維持という短絡的なことではなく、例えば日頃から顔を合わせ、会話を交わすことで、災害時の迅速な対応や犯罪の抑止など、安心安全な生活を持続的に行う上でも最も有効なことであると考えております。しかし、いわゆる行政区の付き合いはしないという考えの方が増えている中で、町では全体的な実態把握は非常に難しく、人数など詳細は把握できてございません。
一方で、転入時に区長さん等へご挨拶に行きたいのですが教えていただけますかといったお声掛けをいただくこともございます。基本的には、町として行政区への加入等を強制できないことから、各行政区において対応いただいておるところとなっております。各行政区においては対応は異なりますが、例えば区費等を支払わず、組織への未加入世帯へは町からの配布物や区内の連絡などはしないなどの対応を取っている行政区が多いのではないかと思っております。
それから、外国籍の人の人数は把握しているかということでございますけれども、海外国籍の人の場合は、就労等の関係で短期的な居住の場合もございますので、先ほど答弁をいたしましたとおり、海外国籍の人数につきましても把握できていないというのが現状でございます。よろしくお願いいたします。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
〇1番(原沢香司)なかなか行政区へ未加入の方の人数を把握するのは難しいという答弁でございました。また、海外国籍の方についても同様ということでございます。
人数の方が多いか少ないかということはもちろんなのですけれども、答弁にありましたとおり、町からの配布物ですとか、区内の連絡が行き届いていない世帯があるということは、住民サービスに対して大きなやはり差異を生んでしまっているということだと思いますので、何かしらこれから対応をするべき事態だと考えております。
次に伺いますけれども、町へ転入届を提出する際に、行政区組織について案内を行っていますか、答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)転入する際の案内を行っているかというお尋ねでございますけれども、戸建ての家を建てて転入してこられた方などからは、区長さんの名前などを聞かれることもございますけれども、通常、転入者の方に対して行政組織への案内等は行っておらないのが現状でございます。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
〇1番(原沢香司)案内は、現状行っていないという答弁でございました。
行政区に入る入らないというのは転居された方の判断になりますので、行政区というものがまずあって、どういう役割を果たしているのか、そのことはぜひ転入時に教えていただきたいと思うのです。区長さんはじめ、みなさん懸命の努力をされているにもかかわらず、やはりこれまでの行政区組織のやり方でこのまま続けていくと、今後の運営はより厳しくなる一方だと思っています。若い世代の方や移住者を含む多様な住民が参加しやすい仕組みをどうやったら構築していけるのか、具体的に行政区の活動内容を魅力的にするために何ができるのかを今から考えていくことが必要ではないでしょうか。
私は、先日中之条町が主催する未来戦略ミーティングにお邪魔いたしまして、お話を端のほうで伺いました。みなさんやはり今中之条町に住んでいることに対して、町に魅力を感じて、どうしたらこの町をもっとよくできるのか、とても真剣に考えて議論をしていらっしゃいます。2年目の取組になりますけれども、昨年お邪魔した際にも大変強く感じたことですが、本当にみなさんの熱意あるお話、今年も引き続いてやられていることに本当に中之条町の未来はまだまだ捨てたものではないし、これから可能性があるということを強く感じた次第です。
冒頭に紹介した行政区の存在自体を知らなかった。このお話は、未来戦略ミーティングに参加した際に伺ったものです。現在、ミーティングでは参加者のみなさんに興味のある話題を自由に話してもらっていると思います。自由に話ができるということはよいことである一方、制限がなくなってしまって、なかなか政策の実現可能性から離れていってしまう、そういったことも危惧されます。せっかく熱い思いのある方たちが集まっている未来戦略ミーティングですので、自由にお話をする一方で、行政の課題を解決してもらうために知恵を借りる、そういうことをお願いしてもよいのではないかというふうに感じています。例えば行政区の活動を活性化するために何が必要か、みなさんに考えてほしいと問題を提起すれば、みなさん町に住む若者、当事者として真剣にアイデアを寄せてくれるのではないでしょうか。ぜひ未来戦略ミーティングの参加者のみなさんと一緒に、今後の行政区の在り方を考えていく、そういう活動にチャレンジをしていただければと思い提案をさせていただきます。
ほかにも行政区の活動をこれから次の世代に引き継いでいくためにはいろいろと考えられると思います。私自身は今伊参地区に在住し、現在副区長の任にあたっていますけれども、区の構成要因の中では最年少でありまして、ほかの方はみなさん私の親の世代か、それよりもさらに上の方が行政区の仕事を担ってくださっています。道路清掃やその他の行事に出ること自体が難しい。先ほど同僚議員の質問でも触れられましたけれども、やはり地域のコミュニティーを持続していくのが本当に大変だ、こういう状況がこのまま推移すれば、区の活動が維持できなくなってくることは目に見えています。区の割り振りが適当であるのか、世代構成や地理的条件なども加味しながら検討していくことが必要だと考えます。
行政が主体となり、区長さんたち当事者から現在の状況も聞き取り、これからの住民自治組織のあり方を根本から考えていく努力を強めていただきたいと思います。いずれにしても、住民同士がお互いに気遣い、地域を共につくっていく活動が今後ますます重要になることは間違いがありません。場所場所により課題も解決策も様々だと思います。それぞれの区の実態に即し、今後の活動の展望が持てるように行政には多大な支援をしていただくことをお願いして、最初の質問を終わります。
〇マイナンバーカードと健康保険証のひも付けについて
次に、マイナンバーカードと健康保険証をひもづけることについて伺います。いわゆるマイナ保険証ですが、3日前、12月2円をもって新規の健康保険証が発行されなくなったことをめぐり、報道でも盛んに取上げられております。これまでの一般質問でもこの問題を取り上げ、国民皆保険制度が壊される危機だと指摘してきましたが、いよいよそれが現実のものになってきています。この問題、基本的には任意であるマイナンバーカードの取得と、全く別の制度である健康保険証をひもづけるという、そもそもの発想に政策的な必然性も根拠もない、そういう類いのものであると私は考えています。しかしながら、国の施策として決まってしまった以上、現場のみなさんはその事務を全うするために大変な苦労を強いられていると思います。
まず、現状を伺いたいのですが、中之条町における連携の状況と、これまでに連携を解除された方がいるかどうか、答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)私も原沢議員と同様に、このところテレビ報道、あるいは新聞などでこのマイナンバーカードの関係について聞かない日はないぐらい、恐らく新しい制度に移行するということで、国としても、それから国民の方々も不安を抱いているということは十分承知をいたしております。
そこで、今のご質問でございますけれども、中之条町の連携状況につきまして報告をさせていただきます。中之条町の人口に対するマイナンバーカードの保有枚数率は79.1%であります。全国や群馬県の平均を上回っている状況にございます。そのうち国民健康保険加入者のマイナ保険証登録者は73.1%となっております。10月1日現在のマイナ保険証による資格確認利用率は0.23%となっており、全国平均は上回っておりますが、まだまだ利用がされていない状況でございます。
議員ご質問のひもづけ登録が解除された実績でございますが、令和6年11月30日現在では、令和5年度においてひもづけ誤りによる解除が1件あった状況にございます。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
〇1番(原沢香司)答弁いただきましたとおり、取得率、連携率とも他の町村より高いということでございました。現場で事務や窓口対応されている職員のみなさんのご尽力のたまものだと思います。
一方で、やはりマイナ保険証の利用率は大変低いという状況です。町長も触れられましたけれども、報道においてはマイナ保険証をめぐる混乱が非常に大きいこと、以前の一般質問でも指摘いたしましたが、実際の利用に対して個人情報の漏えいなど、不安を抱いている方がとても多いこと、こういったことが利用率が低い原因です。
そして、いよいよ12月2日をもって現行の保険証が発行されなくなった。実際に会う人会う人に保険証への不安の声を伺います。まず、「保険証と資格確認書の違いが分からない」、また「家族が寝たきりで窓口に申請に行くことができない。代理で申請に行くことができるのか」など、保険証は健康と命に直結するものですから、不安が大きいのも当然です。施策の内容が分かりづらく、マイナンバーカードを持っていればそのまま保険証として利用できるのではないか、そういうふうに誤解をされている方も実際にいらっしゃいました。
このような状況を受けて、政府は、ひもづけられたマイナンバーカードと健康保険証のひもづけを解除できるようにしたということです。ひもづけが解除できれば、資格確認書が発行されて現行の保険証と同様に医療を受けることができます。
次に伺いますが、連携解除を希望する方はどのようにすれば解除を行えるのでしょうか。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)原沢議員おっしゃるように、12月1日からそういうふうに移行されました。これは、国で決定したことでありますけれども、我々地方自治体にとりましては、町民の方々にやはり丁寧にこれからも国の施策でありますけれども、説明をしたり、ご相談に乗らせていただくということは心がけていかなければならないというふうには自治体の長として考えてございます。
そこで、その解除ができるのかというお話でございますけれども、利用登録を解除するには申請が必要となります。解除を希望する方は、解除申請書を加入している医療保険者に提出し、解除申請を受け付けた各保険者は解除のデータ登録を行います。その後、おおむね1、2か月程度でマイナポータル上の健康保険証利用登録の申込状況画面に反映され、解除が完了する、こういった流れになってございます。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
〇1番(原沢香司)町長に答弁いただきましたとおり、解除するためには国民健康保険の加入者であれば、役場の窓口に出向いて、そこで書類に記入して申請をするということなのです。連携登録自体はデジタルでできるのに、解除のためには紙を書いて提出をしなければいけない。そして、実際の解除には長ければ2か月を要する。登録するのはスマホの上で完結できるわけなのですけれども、解除には大変な手間と時間がかかる、何とも間が抜けた話なのですけれども、これが我が国のデジタル化の現状だということだと思います。
次に伺います。連携が解除できるということは、国民健康保険に加入している町民の方に周知されていますか。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)現在、国民健康保険加入者の方に対しまして、個別に連携登録解除の案内はしておりません。他の市町村の状況等を確認しながら、ホームページへの掲載等、周知の方法につきまして検討してまいりたいと考えております。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
〇1番(原沢香司)国民健康保険の加入者である町民の方、本当に多くの不安を今抱いているところだと思います。本当にニュースを見てどうすればいいのだというようなことを私のほうにも相談に来られる方いらっしゃいますので、ぜひ分かりやすく解除のお知らせをできるだけ速やかに行っていただきまして、先ほど町長もおっしゃられたとおり、町民の不安の声にお答えいただきたい。
また、ホームページで告知を検討するということでございましたけれども、不安を抱えている多くの方はインターネットを利用しない、またはできない世帯、世代の方がほとんどですので、ぜひ書面なり、音でなり、告知を行うことを要望させていただきたいと思います。
この問題、そもそも現状使われている保険証が存続されれば、マイナ保険証のトラブルは全く問題なく解決いたします。町長には町村長会や国会議員への要請などでもぜひこのことを取上げていただきたいと思います。町民の不安を払拭し、誰もが安心して医療を受けるためにぜひお願いをいたします。このことを申し上げて、マイナ保険証についての質問を終えます。
〇消防団のなり手不足と負担軽減について
続いて、3問目、最後の質問です。昨年も消防団のなり手不足と負担軽減について一般質問で取上げました。今年度から外丸町長の防災に対する強い思いから、防災安全課が設置され、日々町民の安全を守るために尽力されております。消防団の所管も総務課から防災安全課に移管され、より一層活動への支援も強化されていることと思います。
ここで伺います。昨年同じ時期と比べて消防団員の数の推移を教えてください。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)原沢議員おっしゃるように、今年度から防災安全課を設置させていただきました。特に私が申し上げるまでもなく、本年元日には大きな能登半島の地震があったということから、地域住民の方々も本当に防災に対する考えが非常に強く考えておるというふうに理解しておりますし、その一方で、やはり消防団の方々に対する我々の期待というのも非常に大きく高まっておりますけれども、相反して消防団の人数の確保が非常に難しいというのは本当に現状でありまして、これは全国的にそういう状況にありますけれども、こういった状況をやはり防災力の観点からも考えていかなければならないということは押さえておきたいと思います。よろしくお願いします。
それで、お尋ねの団員数の推移でございますけれども、消防団員数の推移につきましては、本年3月の定例会議におきまして、条例の一部改正をご議決いただいたときに、第3分団の組織再編による部の統合と併せて定数の改正を行ったところでございます。定数につきましては、改正前が338名、改正後が298名となり、実団員数につきましては令和5年度289名から現在280名の団員数となってございます。よろしくお願います。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
〇1番(原沢香司)防災安全課の新設、そして日頃の業務を、本当に防災様々やることありますので、大変な中、本当にみなさんが尽力されて消防団の支援も行っていることを重々承知しております。しかしながら、定員が40名減り、実団員数が9名減っているということで、簡単に団員数の減少には歯止めがかかっていないというのが現状であると認識しています。
昨年の12月定例会議の一般質問において、消防団員の負担軽減こそが団員の減少を止め、消防団を存続させるために不可欠であると訴えました。
次に伺いますが、消防団員のなり手不足を解消するため、隊員の負担軽減は図られていますか、答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)一遍に成り手不足を解消するといったような特効薬はございませんけれども、団員の負担軽減について、消防団の方々とご相談をさせていただきながら、行政としても取り組んでおるところでございますので、実態をお話させていただきます。
昨年、同じような質問をいただきましたけれども、町といたしましても行事等を精査する中で、負担軽減を図ってまいりました。しかしながら、行事の内容によっては、警備などの安全性の確保や緊急時の対応などにおいて、消防団の方々のご協力をいただかなければならない場合がございます。負担軽減という点では、団長等を中心として、就労形態の変化等の状況を勘案し、少しでも団員の負担軽減となるよう検討を行っているところでございますけれども、今月12月末に実施される各詰所での年末夜警会においては、実施期間を今までは25日から31日までの7日間お願いをいたしておりましたが、27日から30日までの4日間に短縮したいと考えております。今後も団員の負担軽減を図ってまいりたいと考えておりますけれども、いずれにいたしましても、消防団長、それから消防団の幹部の方々と、そういった形についてはしっかりと議論をさせていただきながら、消防団員の方々の負担軽減を図ってまいりたいと、このように考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
1番(原沢香司)本当に町長おっしゃるとおり、特効薬があればこんな楽なことはないのですけれども、やはりみなさんの就労の形態、また生活、ライフスタイルの変化、本当に様々な要因があって、今消防団はなかなかなっていただける方がいないという状況でございますけれども、歳末夜警会について、昨年の一般質問でも見直しを求めたものです。本当に忙しく日々を過ごしていらっしゃる団員たちにとって、特に年末の夜警会大変だという声、いまだに聞いていますので、日程が短縮されるということ、本当に大きな一歩前進であると思います。ぜひ引き続き団長をはじめ、消防団のみなさんと協議していただき、さらなる負担軽減を推し進めていただきたいと思います。
ほかにも定期点検や競技会など、現場の団員たちが負担が大きいと感じていることがあります。まずは現場で尽力されている現役の団員たちからしっかりと声を聞いていただき、これからも組織を存続させるために何が必要なのか、精査することが必要であると思います。繰り返しになりますが、消防団は地域にとって絶対に必要な存在です。団員のなり手不足に歯止めがかかっていないことを直視して、これから団の存続を図っていくために何が負担になっているのか、どうすれば活動が持続できるのかを、団員の声に基づいて考えていくことが必要であると思います。引き続き負担軽減のための対策をしっかりと検討いただくことを重ねて求めます。
最近、地元紙でも報道されましたとおり、群馬県内でも消防団のなり手不足を受けて機能別消防団を組織する自治体も増えてきています。従来の消防団には時間的な制約や体力的な負担から参加が難しい人でも、自分のスキルや都合に合わせて活動できるため、より幅広い層の人材を確保できること。特定の分野に特化した活動を行うことで、より高度な専門性を身につけた消防団員を育成することができること。災害の種類や規模に応じて必要な人員を迅速に動員することができること。全員が全ての活動に参加する必要がないため、団員の負担を軽減し、長期的な活動の継続を促すことができること。それら全て多様な人材の活用や専門性の強化、柔軟な対応、団員の負担軽減が、機能別消防団のメリットとして挙げられると思います。
一方で、様々な機能を持つ団員が連携して活動するために、円滑なコミュニケーションや連携体制を構築するのが難しいこと。また、指揮命令系統が複雑化すること。費用の負担が増大することが予想されること。また、基本的な消防活動の担い手の減少などが機能別消防団のデメリットとして挙げられるのではないかと思います。
ここで、中之条町における機能別消防団組織についての検討状況について伺います。答弁を求めます。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)今お尋ねの機能別消防団についての検討でありますけれども、これはもう人口減少、少子化が大きなもうとにかく要因の中で、消防団員の方々の確保が難しくなっているのは、これはもう当然のことでありますけれども、そういった中におきまして、地域が中之条町は広うございますので、高齢化も進んでおります。やはり消防団員の皆様方だけではもうカバーできない状況がだんだん出てくるのではないだろうかと、そんな考えもありますので、お尋ねの機能別消防団、これは全国的に今そういう検討されているようでございます。当中之条町でも今その検討を始めたところでありますので、その実態、状況についてお話をさせていただきます。
地域を代表するボランティア団体の消防団は、消防、防災を担う上でその中心的な組織の一つあるということは間違いがございません。そういった意味におきましても、組織の存続は必要不可欠である一方、地域コミュニティーの変化や少子高齢化によりまして、非常に難しい状況であると認識をいたしております。以前より検討されております消防団に対する後方支援につきましては、消防団の本団の皆様を中心に、現在入隊条件や活動内容、報償費等、人数等の協議を行い、来年度設立に向けまして現在検討を進めているところであります。消防団員の方々も消防団長を中心にこの問題には本当に真剣に今取り組んでいただいておりますので、ぜひ地域の皆様方、今日おいでの区長さんの皆様方にも、そういったことをご配慮いただいてご協力いただければと、このように考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
〇議長(安原賢一)1番、原沢さん
〇1番(原沢香司)機能別消防団について、来年度の設立に向けて調整中ということでございました。先ほど述べました、いろんなメリット、その反面デメリットもあると思いますので、よく精査をしていただきまして、中之条町にふさわしい組織を形成していっていただきたいと思います。
私の周りにも消防団の活動、本当に大事だし、何か役に立ちたい。だけれども、なかなか正式な団員になるにはハードルが高いという方も多くいます。
また、消防団の活動内容や重要性を周知する広報の活動も欠かすことができないと思います。また、消防団活動と仕事を両立させるためには、働き方、ここの問題も併せて考えていくことが必要になってくると思います。いずれにしても、消防団員のなり手不足という問題は地域全体の防災力に影響を与える深刻な問題です。機能別消防団の導入は、この問題解決の一つの選択肢であると思いますが、慎重な検討と準備が必要だと思います。地域の実情に合わせて最適な解決策を見つけていくことが重要だと思います。ぜひ安心安全なまちづくりのために、消防団組織の在り方をしっかり検討していただくことを重ねて求めまして、私の質問を終わります。