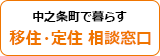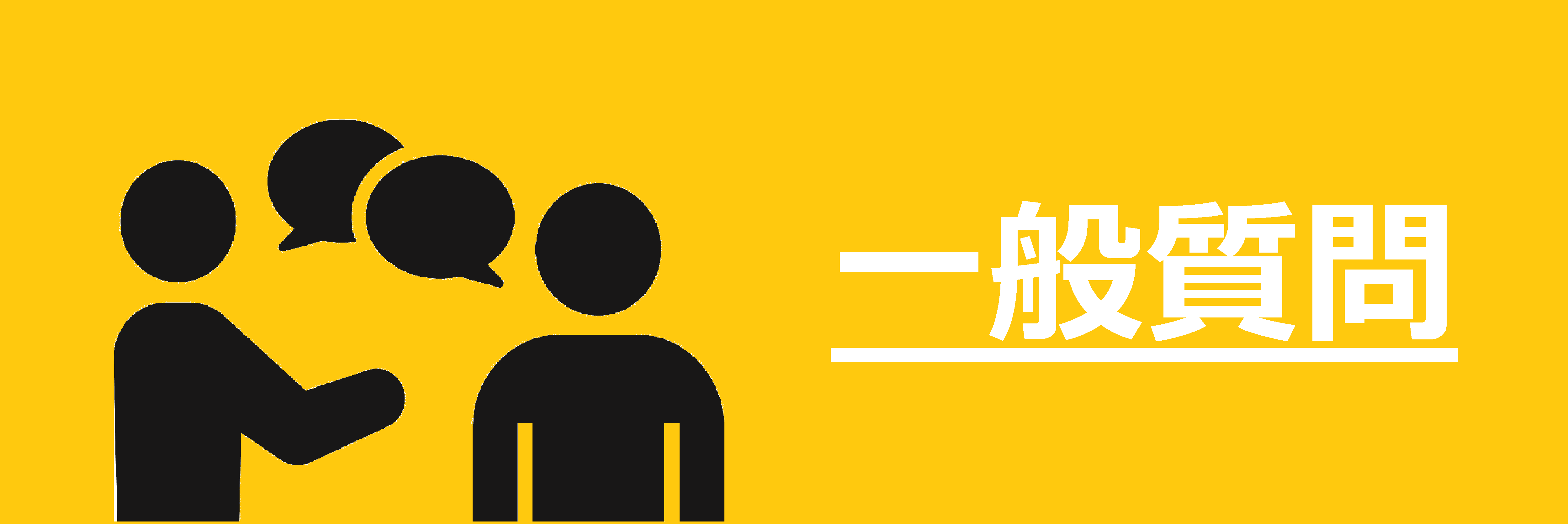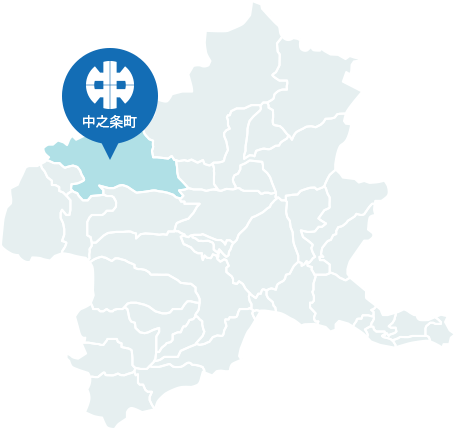本文
令和6年12月定例会議 一般質問(冨沢重典議員)
01 9番 冨沢重典議員 令和6年12月定例会議一般質問
〇9番(冨沢重典)おはようございます。今日は、区長会中之条地区の区長の皆様が傍聴に来られているということで、先日のまちなか5時間リレーマラソン、大変お疲れさまでした。ありがとうございました。
それでは、議長のお許しを得ましたので、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。
〇地域クリーン作戦補助金について
最初に、地域クリーン作戦補助金についてお伺いいたします。行政区や町民からの声がございましたら、お答えをお願いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)それでは、冨沢重典議員のご質問にお答えをさせていただきます。
地域クリーン作戦補助金につきましては、高齢化現象などから、行政区における運営が大変になってきているという状況から、少しでも地域を支援したいとの考えの下、令和5年度に創設をさせていただきました。行政区の区長さんからは、「大変ありがたい」、「少しでも補助があれば助かる」などの声をいただいておりまして、町といたしましては大変効果が上がっていると認識をいたしております。
〇議長(安原賢一)9番、冨沢さん
〇9番(冨沢重典)令和4年12月定例会議の会議録の一部を読ませていただきます。人口減少と高齢化が進む中、地域によっては地域の生活環境を維持することが大変になってきております。伊参地区にあっては、高齢化率が50%を超える状況でもあります。区長さんをはじめ、住民の方々から「道路愛護も大変だ」、「町道の草刈りも大変になってきている」、「町でも支援してもらいたい」、「町道維持管理作業に補助を考えてもらいたい」といった声が聞かれています。これからも道路愛護、町道の草刈り等、地域の方々のお力を借りなくてはなりませんが、県で実施しているクリーン作戦の町としての地域クリーン作戦のような補助制度を考えて、地域を少しでも応援していきたいと考えます。また、地域コミュニティー、絆を維持することも同じ状況になってきており、地域の方々の声を聞き、少しでも支援ができればと考えますと述べております。
確かに県で実施しているクリーン作戦の町としてのクリーン作戦のような補助制度を考えると言われておりますが、その前文で、高齢化が進み町民から「道路愛護も大変だ」、「町道の草刈りも大変になってくる」との声や、地域コミュニティー、絆を維持することも同じ状況になってきているとおっしゃっております。初め町長の所信を聞いたとき、まさか役場の職員を派遣するのか、本当に可能かなどと思いながら聞いておりましたが、当初予算に上がってきていたのは、各行政区に年2回、合計2万円の支給というものでした。出さないよりは出したほうがいいと思い、当初予算は賛成いたしましたが、何ら解決になっていないと思いますが、いかがでしょうか。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)確かにお金だけで解決ができる問題とは考えておりませんけれども、先ほどのご質問で答弁をさせていただきましたけれども、金額は2万円ではありますけれども、区を代表される区長さんからは、私や担当課に寄せられる意見といたしましては、感謝の意を込めていただけるようなそういったお話もいただいております。地域コミュニティーや行政区の維持において効果があったものと認識をいたしておりますし、これが全ての解決策とは思っておりませんけれども、少しでも地域の方々に寄り添った、そういった気持ちを表す意味でも、これからも引き続き実施してまいりたいと、このように考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
〇議長(安原賢一)9番、冨沢さん
〇9番(冨沢重典)職員の皆様にも地域があり、あちらもこちらもとは難しいと思います。何とか地域の方々に協力していただかないと成り立ちません。また、地域コミュニティー、絆を維持するのも同じ状況になってきているとおっしゃっておりますが、地域によっては人口減少とともに、コミュニティーの場である公民館の維持も厳しくなってきていると考えます。私は、以前から公民館の水道はほとんど使用しないのだから、基本料金を免除したらどうかと言っております。役場からは、休止にして使う月だけ再開したらどうかと言われましたが、うっかり忘れて使えなかったり、非常時に使えなかったり、リスクが多くて行う公民館は少ないと思います。どうせ休止にすれば、基本料金は町に入ってこないのですから同じことです。公民館や集会所等、基本料金を免除したら大変喜ばれると思うので、強く要望して、次の質問に移ります。
〇乳幼児おむつ等助成事業について
乳幼児おむつ等助成事業についてお伺いいたします。この質問も以前から何度も質問させていただいている事業ですが、以前は1歳になるまでから、現在は2歳になるまでと拡充した事業です。町長の思いをお聞かせ願います。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)乳幼児のおむつの補助についてのお尋ねでありますけれども、子育て支援の一環といたしまして、乳幼児を持つ保護者の方々に意見をお聞きした中から平成27年度より始めた事業でございます。事業内容は、満2歳になる前の乳幼児にかかった紙おむつや、お尻拭き等の購入費用の80%、月額上限3,000円まで補助をするものでございます。令和5年度より対象年齢を満1歳から満2歳へ拡充をさせていただきました。本事業において、おむつ等の購入費用の助成をすることで、保護者の方の経済的負担を軽減をさせていただき、中之条町の子ども達の健全な育成を図り、健やかな成長を切に願うものでございます。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)9番、冨沢さん
〇9番(冨沢重典)今どこで購入しても月額上限3,000円まで支給する制度です。町内、町外の利用状況、また町内業者からの声があればお聞かせ願います。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)利用状況についてのお尋ねでございますが、おむつ等の購入先といたしましては、令和5年度の実績で見ますと、町内が52.3%、郡内が16.3%、郡外が24.8%、インターネット購入が6.3%となっております。購入件数を5年前の平成30年度と比較をいたしますと、町内においては51.1%の増加、インターネット購入については97.9%の増加となっており、逆に郡内、郡外ともにそれぞれ10%の減少となっている状況でございます。町内での購入の増加の一因といたしましては、町内に薬局が増えたことにあり、またインターネットの普及により自宅まで届けてもらえる通販の利用が増加傾向にあるものと考えております。保護者の方からは、「毎日使うものであり、費用負担も大きいので大変助かっている」、「インターネットでの購入もできるため助かっている」という声をいただいております。なお、町内業者からは特にご意見等はいただいておらない状況でございます。
〇議長(安原賢一)9番、冨沢さん
〇9番(冨沢重典)私は、中之条町で商売し、税金を納めていただいたお金が簡単に町外に出ていってしまうことは問題だと思います。町の補助金ですから、せめて町内で回すべきと考えますが、いかがでしょうか。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)冨沢議員おっしゃるように、確かに町からの助成金でありますから、町内で購入していただくことが最もよい方策であろうと考えております。しかしながら、本事業の対象者が目を離せない乳幼児を抱えた保護者の方であることを考えますと、利便性を優先させることが一番と思われ、実際に対象者からも現行制度での継続を望む声もいただいております。そのため、購入先として町内はもとより、里帰りのときや旅行先、インターネットでの購入等と幅を広げておく必要があると考えます。町への還元につきましては、入学準備応援費など、ほかの施策で行っている事業もありますので、本事業につきましては現行制度での運用についてご理解をいただきたいと思っております。よろしくお願いします。
〇議長(安原賢一)9番、冨沢さん
〇9番(冨沢重典)これも以前から申し上げておりますが、金額の割に役場の担当者も保護者も事務手続が大変なように感じますし、何より町の補助金が町内で回らないことが問題だと思います。利用者がほぼ上限の3,000円に達しているようですし、おむつはどこで購入しても、町の補助金3,000円は町内で買物していただくのがよいと思います。
そこで提案です。あくまでおむつの購入補助であっても、家庭の財布は1つです。また、事務手続も簡素化したほうがよいと思いますので、出生届を提出していただいたとき、中之条商品券を3,000円分掛ける12か月分、3万6,000円分お渡しし、1歳児には検診時に1年分お渡しするというのはいかがでしょうか。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)この乳幼児おむつ等購入費助成事業につきましては、制度開始後10年を経過するところでございます。保護者の皆様方にも既に周知されて定着している事業でございます。ご提案の商品券での支給につきましては、過去にも議会でご質問をいただき、お答えいたしたところでございますが、以前に答弁させていただきましたとおり、商品券での支給となりますと、おむつ以外の商品も購入できることから、子育て支援という趣旨が曖昧になる、こういった懸念もございます。また、先ほど申し上げましたとおり、利便性を考慮し、里帰りのときや旅行先、あるいはインターネットでの購入等も対象としているため、子どもから目を離せない保護者の方からは大変好評をいただいております。申請につきましても、毎月しなくてもよく、乳幼児健診等のついでや都合のよいときに数か月分まとめての申請を奨励するなど、申請への負担軽減に努めております。今後も利用者のご意見をお伺いしながら、より使いやすく充実した制度を目指してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
〇議長(安原賢一)9番、冨沢さん
〇9番(冨沢重典)インターネット等でおむつを購入されてしまっていても、その分のお金が3,000円浮くわけですから、それが中之条町の商店街に落ちないのは、いささかいまだに納得できない問題でありまして、ぜひ利用者や町の職員の負担軽減を図ることとともに、せっかく納めていただいた税金が町として容認して町外に出してしまうということが今後ないように前向きにご検討いただければというふうに思います。
〇福祉タクシー利用料金助成事業について
次の質問に移ります。この質問も再三お伺いしている質問ですが、福祉タクシー利用料金助成事業についてお伺いいたします。現在利用できる条件をお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)福祉タクシー利用助成事業につきましてのお尋ねでございますけれども、障害者や加齢等の理由により自動車の運転ができない方、または免許を返納した方など、移動手段に制限を受ける方たちを対象にタクシー料金を助成することで、医療機関への通院や買物、社会参画等への継続した地域生活の支援を行うものでございます。利用対象となる方につきましては、中之条町に住民登録があり、町税等の滞納がない方のうち、1といたしまして運転免許証を所有していない満65歳以上の方、2といたしまして運転免許証を返納した方、3といたしまして該当する身体障害者手帳や療育手帳、精神保健福祉手帳を所持している方が対象となってございます。
助成内容といたしましては、高齢者の方は助成券1枚500円分としての利用できる券の60枚つづりを1冊、追加として20枚つづりを1冊まで購入でき、障害をお持ちの方は60枚つづりを2冊まで無料交付をいたしております。令和元年度より現在の福祉タクシー利用制度に移行し、事業展開をいたしておりますけれども、令和5年度の実績は、高齢者349名、障害者85名の利用者に対し、60枚つづりが505冊、20枚つづりが177冊の合計682冊の交付実績がございます。
〇議長(安原賢一)9番、冨沢さん
〇9番(冨沢重典)現在は免許を所持している場合、この事業を利用できないわけですが、要綱の第1条に、交通手段がないために日常生活に支障を来している町民と書いてあります。何らかの理由で車の運転ができない時期があった場合、交通手段がなくなる方がおられます。私に相談に来てくれた方は、独り暮らしで定期的に瞳孔を開いて目の検査をしているそうです。ふだんは周りに迷惑をかけたくないため車の運転をしているそうですが、眼科に通うときは帰りに運転ができず、路線バスもないためタクシーを利用しているそうです。十分日常生活に支障を来していると思います。
また、交通弱者は不安でなかなか免許の返納は難しいと思います。そもそもこの助成事業、高齢者の事故防止の観点から拡充した事業だと思います。返納を呼びかけるのも大切かもしれませんが、運転をする回数を減らすのも大切だと考えます。体調が優れないときは無理して運転せず、タクシーを気軽に利用していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
〇議長(安原賢一)町長
〇町長(外丸茂樹)本事業の利用事業者といたしまして、11月末現在一般のタクシー会社が1社、介護対応ができる福祉タクシー会社が8社となっております。利用者からは、「自分で車を運転できないのでとても助かっている」、「介護タクシーも利用できるため有効活用ができる」といったお声をいただき、障害をお持ちの方や移動手段に制限を受けている方の地域生活支援として福祉タクシー利用助成事業は総じて好評をいただいておるところでございます。
なお、本事業の対象外となる方は、例えばけがをして一時的に自動車を運転できない方等におかれましては、冨沢議員がおっしゃるように、中之条町福祉タクシー利用助成事業実施要綱におきましても、第1条の趣旨にて、交通手段がないために日常生活に支障を来している町民に対して助成するとなってございますが、第3条の助成対象者として、前述いたしました自動車免許証を有しない満65歳以上の方などを対象としており、対象外となっております。対象外となられた方から、直接的に役場、福祉係窓口への問合せ等は特にございませんが、免許返納者や免許を持たない高齢者、また障害をお持ちの方といった日常的に移動の困難を感じている方は、本事業を対象としていることから、一時的な移動困難者としての対象外となっている方への支援やその範囲の設定については課題の一つであると考えております。
今後も利用対象となる方々の家庭環境や生活状況、また地域特性を踏まえた上で、ニーズを把握しながら総合的に適切な支援を図ることによって、日常生活における利便性や生活スタイルの向上、また外出機会の創出に努めてまいりたいと考えております。
また、役場内におきまして、庁内交通会議を通じて地域公共交通等における各移動支援策等の現状や課題について、担当者の意見交換や情報共有を図っておりますが、今後も総合的に公共交通の在り方を検討することによって、タクシー利用を含め、地域住民の方々が生活をしやすい環境づくりに努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
〇議長(安原賢一)9番、冨沢さん
〇9番(冨沢重典)タクシーの台数にも限りがあり、すぐに拡充は難しいと思いますが、あまり時間をかけずに拡充をお願いして、最後の質問に移ります。
〇アウトメディアについて
アウトメディアの取組について、現在の取組とスマートフォンの所持状況についてお伺いいたします。
〇議長(安原賢一)教育長
〇教育長(山口暁夫)この質問につきましては、こども未来課長よりお答えさせていただきます。
〇議長(安原賢一)こども未来課長
〇こども未来課長(山本伸一)こども未来課の山本でございます。ご質問の件について、私のほうから答弁させていただきます。
まず、現在の取組でございますが、本町では平成26年3月にアウトメディア推進委員会を設置し、本町の子ども達がテレビやDVD、ゲーム、スマートフォン、インターネットなどの電子メディアの過剰な使用や誤った使用による健全な成長の阻害と犯罪被害の防止を目的に、一貫して小中学生のうちは携帯電話やスマートフォンを持たせないことをアウトメディアの決まりとしており、毎年年度当初にチラシを配布するなどして周知しております。
次に、小中学生の携帯電話やスマートフォンの所持の状況につきましては、毎年度実施しているこどもの学び・生活支援計画及び英語力向上支援計画「ステップ」に関する調査において、ふだん1日当たりどれくらいの時間、携帯電話、スマホで通話やメール、インターネットをしますかの問いに対し、携帯電話やスマートフォンを持っていないと回答した児童生徒の人数から、不所持率を算出しております。この調査結果から、中学生では、令和元年度には不所持率は75.2%でしたが、年々その数字が下がってきており、令和5年度では不所持率は45.9%となっております。また、中1、中2、中3と学年が上がるごとに不所持率は下がる傾向にあります。このことから中学校においては約半数以上の生徒が携帯電話やスマートフォンを所持しているものと捉えております。
以上です。
〇議長(安原賢一)9番、冨沢さん
〇9番(冨沢重典)実態は、もう少し深刻かもしれません。スマートフォン所持を禁止しているのに所持をしている生徒がいるということは、保護者が持たせたいと考えていることになりますが、生徒や保護者にアンケート等を行っていればお聞かせ願います。
〇議長(安原賢一)こども未来課長
〇こども未来課長(山本伸一)アウトメディア推進委員会ではスマートフォン等を持たせない方針としておりますので、所持に対する希望調査等は行っておりません。一部中学校に寄せられている保護者のご意見として、「スマホの所持を制限することは実態や時代に合っていない」、「スマホは必需品である」、「持っている前提で適切な使い方やマナーなどについて指導してほしい」などの声をお聞きしております。しかし、一方で、「町及び学校がスマートフォン所持の禁止を掲げてくれているのでありがたい」といった意見も少なくはなく、中学生までは持たせたくないと考えている保護者にとって、町や学校の方針が子どもを説得する正当な理由となっているご家庭もあるようでございます。
以上です。
〇議長(安原賢一)9番、冨沢さん
〇9番(冨沢重典)オーストラリアでは16歳未満のSNSを禁止する法案が可決され、賛否が分かれているとの報道もあります。使わなければSNSによる犯罪に巻き込まれるリスクは減りますが、幼い頃から親とSNSになじませたほうがよいとか、16歳になって法律から解放されたときが心配だとか、常に進化を続けているインターネット産業に人類は直面しているわけですから、正解はないと思いますが、中之条町のスタイルも義務教育中に犯罪に巻き込まれなければよいと捉える方もいるかもしれません。
実感として我が子に中学校卒業後、携帯電話を持たせると依存症のように使い続けます。注意してもなかなか効き目がありません。いきなり解放するリスクはあると感じています。何でもかんでも禁止は楽かもしれませんが、GIGAスクール構想でもう既にインターネットと付き合っているわけですから、上手な使い方を教育したほうがよいのではないでしょうか。答弁をお願いいたします。
〇議長(安原賢一)こども未来課長
〇こども未来課長(山本伸一)文部科学省から令和2年7月に通知された、学校における携帯電話の取扱い等についてにおいて、学校における携帯電話の取扱いが示されております。これによると、携帯電話は学校における教育活動に直接必要のないものであることから、小中学校においては学校への児童生徒の携帯電話の持込みについては原則禁止とすべきであるとされており、文部科学省のこの方針は10年前から変わっておりません。
一方、携帯電話を緊急の連絡手段とせざるを得ない場合、その他やむを得ない事情がある場合も想定されることから、中学校では一定の条件の下で持込みを認めるべきであることも示されております。具体的な条件としては、次の4つになります。まず1つとして、生徒が自らを律することができるようなルールを学校のほか生徒や保護者が主体的に考え、協力してつくる機会を設けること、2つ目が学校における管理方法や紛失等のトラブルが発生した場合の責任の所在が明確にされていること、3つ目がフィルタリングが保護者の責任の下で適切に設定されていること、4つ目として携帯電話の危険性や正しい使い方に関する指導が学校及び家庭において適切に行われていること。
議員のご質問にもございましたとおり、一般社会に広くデジタルデバイスが普及し、学校教育においても1人1台のデジタル端末を持たせるGIGAスクール構想に基づくICT化が行われております。もちろんこの流れに歯止めはかけられませんし、将来には児童生徒がスマートフォン等を持つことが当たり前になる時代が来ることも考えられます。このことから、本町においても生徒自らが律することができるルールづくりや、スマートフォン等の危険性、正しい使い方に関する指導に向けた取組を検討していきたいと考えております。
以上です。
〇議長(安原賢一)9番、冨沢さん
〇9番(冨沢重典)家庭のことは家庭で責任を持ってもらい、学校での制限は学校が責任を持つ。所持している子どものほうが多い今、もう限界が来てると思います。
こんな話があります。月曜日に子どもが帰ってくると、昨日みんなでどこどこで遊んだんだって、保護者の方がなぜ誘われなかったか聞くと、私は連絡手段がないから誘われないのだそうです。保護者は、非常に申し訳ない気持ちになったそうです。何週も同じことが続いた後、そういえば最近言わないなと子どもに聞いてみると、私の前ではそういう話はしなくなったし、連絡し合っているかも私には分からないと答えたそうです。
私は、前教育長にスマートフォンを持っていない子どもがいじめられるようなときが来たらやめたほうがいいと言っておりました。もうそのときは来ているのではないでしょうか。答弁をお願いいたします。
〇議長(安原賢一)教育長
〇教育長(山口暁夫)本町の学校においてもスマートフォンによるアプリケーションの間違った使い方やSNSでの不適切な投稿によるいじめなど様々な事案により、その都度教職員が間に入って対応し、生徒への指導を要する事態が発生しております。このような事案に対し、学校においては、適切な使い方に対する指導を進め、生徒間で問題が生じた場合は必要な対応を行っていきますが、スマートフォン等に関する問題の解決は教職員だけに任せるのではなく、所有させている保護者の理解と協力が重要であると感じております。
スマートフォンやパソコンなど、インターネットを通じて世界中のありとあらゆる情報が得られたり、多種多様なアプリケーションによって生活を豊かにしてくれるものでもあります。しかし、子ども達にとって有害な情報も多くあり、使い過ぎによる健康被害や犯罪に巻き込まれる危険性も懸念されるものです。また、知らず知らずのうちに犯罪に加担したり、自身が犯罪を犯してしまうこともある危険性が十分にございます。また、大人では思いも及ばないような使い方や機能により、教職員や保護者が分からないところでいじめなど様々な問題が発生していることもあります。
ご事情により子どもにスマートフォンを持たせる必要があるご家庭もあるかと思われます。しかし、スマートフォンなどをお子様に持たせるからには、ご家庭でしっかりとしたルールをつくり、保護者の管理の下で使用させることは必要不可欠なことと考えます。また、問題が生じた場合、保護者は学校と協力して解決に向け取り組んでいただく必要があることもご理解いただきたいと思っております。
教育委員会としては、メディアコントロールやメディアとの向き合い方などへの取組も検討してまいりますが、子ども達を守るためアウトメディアを推進し、中学校以下の子ども達には携帯電話やスマートフォンを持たせない方針に変わりはございませんので、今後も粘り強く啓発を行っていきたいと考えております。そして、メディアに頼らない対人関係能力、豊かな心の育成に取り組んでまいりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。
以上です。
〇議長(安原賢一)9番、冨沢さん
〇9番(冨沢重典)いずれにしましても黙認するのではなく、早急に答えを出していただくことを強く要望して、すみません、スムーズな答弁いただきまして大分予定時間早いのですけれども、私の質問を終わりにします。