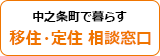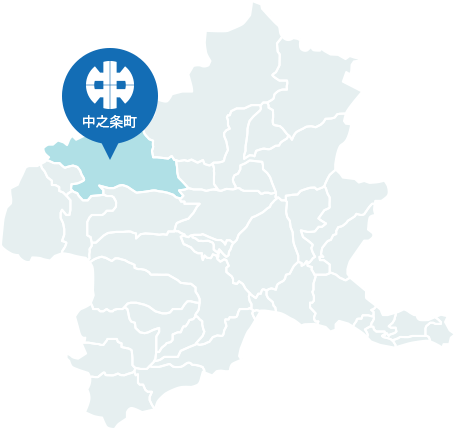ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
わが家の防災対策
災害に備えて、確認しておきましょう
- [地震]その時の心得10カ条
- [地震]わが家の安全対策
- [地震]生活を維持するための備え
- [地震]自主防災組織をつくろう
- [火災]火の用心~6のポイント~
- [火災]万一火が出たら~3のポイント~
- [風水害]台風・大雨・集中豪雨に備える
- [風水害]土砂災害に備える
- 避難
- [安否]家族・親戚等の連絡方法
- [緊急]応急手当、いざというときのために
1.[地震]その時の心得10カ条
![[地震]その時の心得10カ条の画像1](/uploaded/image/1564.gif)
![[地震]その時の心得10カ条の画像2](/uploaded/image/1565.gif)
- まず落ち着いて身の安全を図れ!
- すばやく火の始末!
- あわてて外に飛び出さない!
- 非常脱出口の確保!
- 火が出たら初期消火を!
- 狭い路地・ブロック塀・がけ・川べりには近づかない!
- 正しい情報をつかみ落ち着いた行動を!
- 隣近所と協力し合って救出・救護を!
- 避難は隣近所と集団で! 持ち物は最小限に!
- 山崩れ・がけ崩れに注意!
2.[地震]わが家の安全対策
- 家具類の転倒・移動防止
- ガラスの飛散防止・落下物の防止
- ブロック塀の安全点検
3.[地震]生活を維持するための備え
- 水の用意
- 食糧の用意
- 燃料の用意
- 照明・情報の用意
4.[地震]自主防災組織をつくろう
- 行政区単位で自主防災組織をつくろう
- 日頃から活動し、災害に備えよう
5.[火災]火の用心~6のポイント~
![[火災]火の用心~6のポイント~の画像](/uploaded/image/1566.gif)
- 台所
- ストーブ
- ふろ
- たばこ
- 子供の火遊び
- 放火
6.[火災]万一火が出たら~3のポイント~
- まず、大声で知らせる
- 落ち着いて初期消火をする
- 早く避難する
7.[風水害]台風・大雨・集中豪雨に備える
- 気象情報をよく聞き 早めの対応を!
- 物干し竿が飛ばされないようにする
- 鉢、プランターなどベランダの小物を取り込む
- 排水溝の掃除
- 外回りの道具や箱類の取り込み
- 雨戸や窓の補強
8.[風水害]土砂災害に備える
- 土石流(鉄砲水)
がけ崩れ、地すべり - 危険な箇所には近づかない
- 兆候が現れたら避難する
9.避難
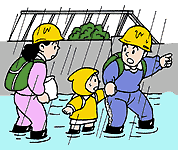
避難は、いつ、どんなとき
- 火災が拡大したとき
- 避難勧告が出たとき
- 自分で判断して
※避難するときは、町で決めた避難場所に避難しましょう!
避難に備える
災害時要援護者(高齢者・障害者等)の避難に備える
一時避難や避難生活に備える
避難のルールと服装
家族や隣近所の人と声をかけ合って、集団で避難する
高齢者・障害者等の避難を優先する
警察官や自主防災組織のリーダー等の指示に従い、秩序よく避難する
電気のブレーカーを切り、ガスボンベの元栓を閉める
家族や知人のための連絡メモを見やすい場所に残しておく
ヘルメットや防災頭巾で頭の保護をする
靴は履き慣れたかかとが低いスニーカー等を履く
荷物は最小限で、両手をあけておく
長そで、長ズボンをはく
10.[安否]家族・親戚等の連絡方法
- 緊急連絡先を用意しておく
- 携帯電話等のサービスを利用
NTT災害用伝言ダイアル「171」について(NTT東日本へリンク)<外部リンク>
ドコモ「iモード災害用伝言板」(NTTドコモへリンク)<外部リンク>
au災害用伝言版サービス(auへリンク)<外部リンク>
Softbank「災害用伝言板サービス」(ソフトバンクモバイルへリンク)<外部リンク>
11.[緊急]応急手当、いざというときのために
倒れたとき(意識障害)
- 絶対安静にする。つまり動かさない。しかし、危険な場所、きゅうくつな所、寒冷な戸外などで倒れたり、止血などの処理に不便なときは、最小限の範囲で動かすのはやむをえない。その際、首や頭を大きく・急激に動かさないように注意する。
- 気道を確保し、衣服をゆるめてらくにする。
- 吐くときは顔だけでなく、身体全体を横向きにさせ、首を水平に保つために頬の下にあて物をあてがう。
- 意識が回復しても安静にさせ、立たせたり歩かせたりしない。
してはいけないこと
- 意識を失っている患者の身体をむやみに動かしてはいけない。
- 正気にもどってもゆすったり、抱き起したり、水を飲ませたりしてはいけない。
骨折の手当
- 必ずむくみがくるので、局所の圧迫物を早く取り除く(脱がせにくい靴や衣服は切り開く)。そのうえで、局所の安定を保つために副木を当てる。
- 複雑骨折(骨が露出している骨折)の場合は、傷の周りを消毒し、清潔なガーゼをあててから副木を固定する。
- 副木で固定したら、骨折部を低くしないようにして病院に運ぶ。
※副木は靴べら、いた、杖、傘などあり合わせのものを利用する。傷口が少しでも開いている所は、副木を消毒液で拭き、また、傷口に直接触れないようにする。
してはいけないこと
- 露出した骨には手を触れない。傷の消毒などもしない。
- 捻挫、脱臼などと勝手に判断しない。また、無理に動かさない。
切り傷の止血
- 傷口を押さえて「圧迫止血」をする。
- 圧迫止血で止まらないときは、止血点を押さえる(傷口より心臓側の血管を骨に向かって押しつける)。
- 大量出血の場合、棒で止血帯をねじってしめつける。15分おきくらいでゆるめる。
してはいけないこと
- 人はかなりの出血に耐えられるので、あわてて汚れたままで傷口を押さえないこと。まず、手を洗うなり消毒液で拭くなりしてから処理に当たる。
- 傷口の圧迫に、脱脂綿やちり紙を直接当てない。
- 薬を勝手に塗らないこと(医師の治療の妨げになる)。
やけどの手当
- やけどの部分を早く、十分冷やす。
- 衣服や靴下をむりに脱がさず、その上から水を静かに流して冷やす。
- 手足は水につける。
- 水ぶくれは破らないように注意する。
- 薬などは何も塗らないこと(医師の治療の妨げ、また感染症を起す)。
してはいけないこと
- やけどの皮膚はすぐに破れて細菌が感染を起すので、患部に触れない。そのためには薬を塗らない。
- 冷やすとき、水道の蛇口の水を直接傷口に当てない。