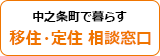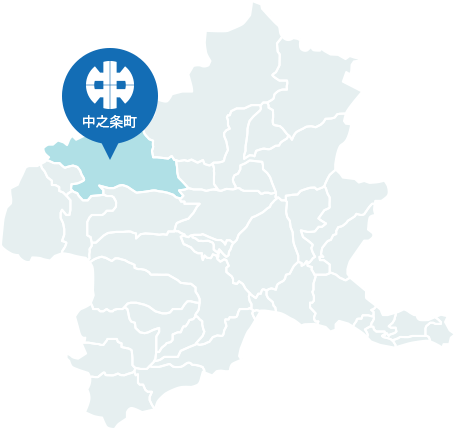本文
「クビアカツヤカミキリ」にご注意ください
町内でクビアカツヤカミキリによる被害が確認されました
特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」による被害が、令和7年7月に町内で確認されました。
また、クビアカツヤカミキリの幼虫も確認されています。
被害拡大を防ぐため、成虫を確認した際は速やかに足でクビアカツヤカミキリを踏みつぶす等により、駆除にご協力ください。
畑や農地で成虫やフラスを発見した場合は、中之条町役場農林課農業振興係へ情報提供をお願いいたします。
また、クビアカツヤカミキリの幼虫も確認されています。
被害拡大を防ぐため、成虫を確認した際は速やかに足でクビアカツヤカミキリを踏みつぶす等により、駆除にご協力ください。
畑や農地で成虫やフラスを発見した場合は、中之条町役場農林課農業振興係へ情報提供をお願いいたします。
特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」について
クビアカツヤカミキリは、サクラ・ハナモモ・スモモ・ウメの樹木に寄生し、幼虫が木の中を食い荒らします。
食害が進むと木を弱らせ、枯らしてしまうため、観光や農業に深刻な影響を及ぼしたり、倒木の被害を発生させる恐れがあります。
また、平成30年1月に特定外来生物に指定され、生きたままの運搬や販売、飼育、野に放つこと等が禁止となりました。
食害が進むと木を弱らせ、枯らしてしまうため、観光や農業に深刻な影響を及ぼしたり、倒木の被害を発生させる恐れがあります。
また、平成30年1月に特定外来生物に指定され、生きたままの運搬や販売、飼育、野に放つこと等が禁止となりました。
クビアカツヤカミキリの特徴
- 成虫の体長は2センチメートルから4センチメートル(触覚を含まない)
- 胸部(クビの部分)が赤く、全体的にツヤのある黒色
- 成虫は6月から8月にかけて発生
- 幼虫は樹木の中で2年から3年かけて成長し、さなぎになる。
- 幼虫が寄生する樹木は、サクラ、ウメ、モモ、ハナモモ、スモモ、プラム等のバラ科の樹木。
- 幼虫が寄生した樹木には、「フラス」(木くずやフンが混ざったもの)が大量に排出される。
- 「フラス」は幼虫の侵入孔から排出され、棒状(かりんとう状)で、木の下に大量に落ちる。
- 木の中で羽化した成虫は、縦に長い楕円形の「脱出孔」と呼ばれる穴を開け、木の中から脱出する。

クビアカツヤカミキリの成虫

木の幹から排出されるフラス

棒状(かりんとう状)のフラス
※写真は群馬県自然環境課より提供
関連情報
- 群馬県 特定外来生物クビアカツヤカミキリに注意してください<外部リンク>
- 群馬県 「ぐんまクビアカネット」の運用を開始しました<外部リンク>
- 群馬県 チラシ「サクラが危ない!」<外部リンク>
- ぐんまクビアカネット<入力フォーム>(群馬県)<外部リンク>
- ぐんまクビアカネット<マップ>(群馬県)<外部リンク>
※「ぐんまクビアカネット」ではクビアカツヤカミキリの目撃情報をスマートフォン等で報告・閲覧できます。ぜひご利用ください。
- マッピングぐんま パソコン用ホームページ<外部リンク>
- マッピングぐんま スマートフォン用ホームページ<外部リンク>
※「ぐんまクビアカマップ」では群馬県内のクビアカツヤカミキリの被害状況等を電子地図で確認することができます。「マッピングぐんま」から「自然・環境情報」、「ぐんまクビアカマップ」をお選びください。