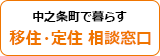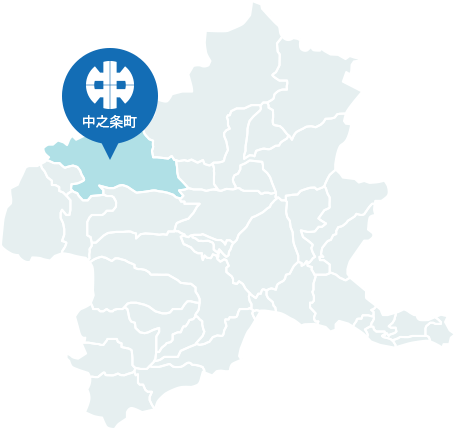本文
令和6年度・令和7年度の後期高齢者医療保険料の保険料率が決まりました
後期高齢者医療保険料率の改定
後期高齢者医療保険制度の保険料率は、2年に1度見直すこととされています。
令和6年度と令和7年度の保険料率は、次のとおり決定しました。
| 均等割額 | 45,700円 |
| 所得割率 | 8.89% |
| 賦課限度額 | 66万円 |
↓
| 均等割額 | 49,100円 |
| 所得割率 | 10.07% |
| 賦課限度額 | 80万円 |
保険料率の引き上げについて
後期高齢者医療給付費は、自己負担を除いた部分を、国・県・市町村からの負担金で約5割、現役世代からの支援金で約4割、残りの約1割を保険料によりまかなわれています。保険料率は今後2年間に見込まれる医療給付費等の費用と保険料等の収入をもとに算定します。
令和6年度と令和7年度は、こども・子育て支援の拡充のため、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金が導入されることや、引き続き団塊の世代の加入により、費用の増加が見込まれます。一方、後期高齢者負担率の見直しにより、現役世代からの支援金の割合が減少するため、収入の減少が見込まれます。これにより、保険料でまかなうべき割合が増え、保険料率の引き上げになっています。
ただし、激変緩和措置により、旧ただし書き所得(前年中の総所得金額等-基礎控除額)が58万円以下の被保険者は、所得割率を令和6年度に限り9.36%とします。
出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金は、子育てを全世代で支援する観点から令和6年4月1日より導入されました。支援割合を出産一時金に係る費用の7パーセントと設定しています。なお、令和6年度と令和7年度においては、高齢者負担の激変緩和の観点から、負担額を2分の1として保険料率の算定を行っています。
後期高齢者負担率は、医療給付費における後期高齢者負担(保険料)の割合で、国が決定します。後期高齢者医療制度を支える現役世代の負担上昇をできる限り抑えるため、後期高齢者1人当たり保険料と現役世代1人当たり後期高齢者支援金伸び率が同じになるように見直されました。
賦課限度額の改正について
中間所得層の負担軽減を図るため、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴い、賦課限度額を80万円に引き上げました。
ただし、激変緩和措置により、令和6年4月1日前に資格取得した被保険者及び障害認定を受けて資格取得した被保険者は、賦課限度額を令和6年度に限り73万円とします。
所得が低い方に対する均等割額の軽減
後期高齢者医療制度の保険料について、令和6年度の均等割額の軽減制度は次のとおりです。経済動向等を踏まえ、5割及び2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準が改正されました。
また、保険料率(均等割額)の変更に伴い、軽減後均等割額が変更になります。
| 軽減割合 | 軽減該当条件 | 軽減後均等割額 |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 | 13,710円 |
| 5割軽減 | 43万円+29万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 | 22,850円 |
| 2割軽減 | 43万円+53万5千円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 | 36,560円 |
↓
| 軽減割合 | 軽減該当条件 | 軽減後均等割額 |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 | 14,730円 |
| 5割軽減 | 43万円+29万5千円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 | 24,550円 |
| 2割軽減 | 43万円+54万5千円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 | 39,280円 |
10万円×(年金・給与所得者の数-1)の部分は年金・給与所得者の数が2以上の場合のみ計算します。年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
・給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)。
・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人。
・現年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人。